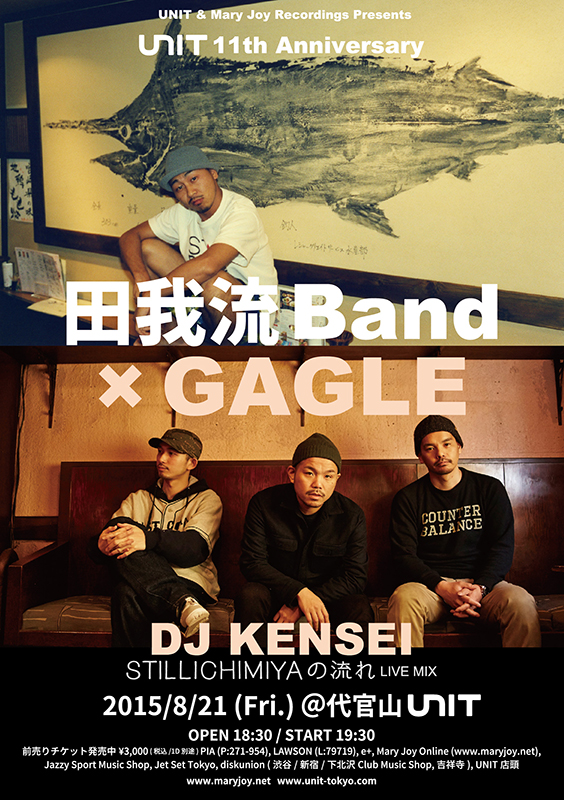8月の現状。8月の現場SOUND。8/14
 1 |
Keita Sano - Drummer Trix - Mister Saturday Night https://youtu.be/K9iVK7hzUyc |
|---|---|
 2 |
M-Age - Visitor (Air Liquide Mix) - RISING HIGH RECORDS https://youtu.be/m5lOBI0BNqE |
 3 |
Bobby Konders - Massai Woman - Nu Groove Records https://youtu.be/IjkYi4IFzQE |
 4 |
Nobody Home - Drum Journey - Home Records https://youtu.be/mea8cyIoqng |
 5 |
Eduardo de la Calle - Reliable Sources - Semantica Records https://youtu.be/WxAO5fvJb4M |
 6 |
Photonz - Osiris Resurrected - Hot Haus Recs https://youtu.be/jukzS-PrUrU |
 7 |
ANDREAS DORAU - Girls In Love (Grungerman Mix I) - Ladomat 2000 https://youtu.be/CHGvVWdfY-c |
 8 |
Don Disco - Swing Ibero - Immer https://youtu.be/eVP9VJ40RqY |
 9 |
The Mole - Alice, You Need Him - Wagon Repair https://youtu.be/ShTloE9aXPI |
 10 |
Ion Ludwig - Bon Gahel - Resopal Schallware https://pro.beatport.com/track/bon-gahel-original-mix/303801 |
気がついたら現場で使用頻度が高い楽曲を選曲しました。
毎月第一水曜日 REXITL @ OATH、毎月第四木曜日 SOUL SESSION @ bonoboでDJをしています。
ほか津々浦々各所で行脚中です。ダンスフロアで乾杯しましょう!
<DJ スケジュール>
8.17 the CAMP @ J-POP CAFE
8.21 NOISE ADDITC @ FOREST LIMIT
8.22-23 BEACH WHISTLE
8.27 SOUL SESSION @ bonobo
9.2 REXITL @ OATH
9.10 bar bridge
9.11 メスカリート
9.12-13 FUSION @ おおばキャンプ村
9.18 蜂
9.23 ZONGO @ orbit
9.24 SOUL SESSION @ bonobo
9.25 orbit
INFO⇒ https://twitter.com/Karinga_Kenzo