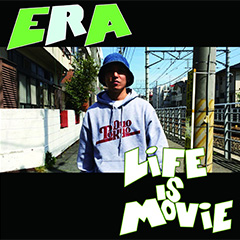はっきり言って今年は当たり年です。とくに、いままでは日本で観られなかったヨーロッパの映画作家の作品が続々入ってきていて、しかも水準の高いものばかり。だからそれらを映画館で体感することは僕たちにとって幸福でしかなく、連休はあの暗闇のなかで旅をしましょう……ということで、公開中の作品と公開予定の作品を。
■EDEN/エデン

監督 / ミア・ハンセン=ラヴ
出演 / フェリックス・ド・ジヴリ、ポーリーヌ・エチエンヌ、ヴァンサン・マケーニュ 他
配給 / ミモザフィルムズ
2014年 フランス
新宿シネマカリテ、立川シネマシティ ほかにて、全国公開中。
© 2014 CG CINEMA – FRANCE 2 CINEMA – BLUE FILM PROD – YUNDAL FILMS
▼Side A 野田努
映画のオープニングが最高。初めてクラブ・カルチャーを体験した青年は、お店が終わり人がいなくなったフロアにひとり残って、レコードを仕舞っているDJに歩み寄る。青年は、彼にとってその晩もっとも印象に残った曲が何という曲だったのかをDJに問う。DJはその曲のジャケを青年に見せる。画面に大きく写されるその美しいスリーヴ。そして曲がかかり、タイトルが出てオープニングがはじまる……。
その曲名をここで明かしてしまうと見る楽しみが半減するので言わないでおくけれど、しかし、90年代初頭のクラブ・カルチャーを体験している人がこれを見たら、まず泣くだろう。ハウス/テクノの名盤中の名盤、「エデン」というタイトルに相応しい曲だが、ぼくはまさかのこのオープニングに涙した。クラブ・カルチャーが好きな人は、最初の30分のためだけにこの映画を見ても損はない。
オープニングの次は、主人公の青年が親に嘘をついてウェアハウス・パーティに出かけるところだ。そこも時代をうまく描写している。いわゆるレイヴのシーンだが、かかっている曲はジ・オーブの“ラヴィング・ユー”と、まあ、わかっている選曲だ。
そして時代は進み、90年代のクラブ黄金時代が描かれる。映画のなかでは、その時代その時代のアンダーグラウンドのヒット曲が流れてる。90年代以降のクラブ・ミュージックを聴いていた人は、クレジットを見なくてもほとんどの曲名がわかるだろう。
ダフト・パンクの“ダ・ファンク”がかかるところも良い。あの曲は、当時は誰もが狂喜した完璧なアンダーグラウンド・ヒットで、多くのクラブ・ミュージック好きの耳をパリに向けさせる契機となった1曲だ。
とはいえ、この映画は「フレンチ・タッチ」を描いているものではないし、パリのクラブ・カルチャー史を描いているものでもない(ロラン・ガルニエもDJディープも出てこない)。語られているのは、クラブ・カルチャーに心奪われDJとなったひとりの人間の、およそ20年の人生だ。
90年代はよかった。が、移りゆく季節のなかで物事は思うようにはいかなくなっていく。時代に歓迎されたセンスも、時代が更新されるなかでズレていく。当たり前のことだ。ターンテーブルはCDJへと、そしてPCへと変わる……。
残念なのは、この映画がDJカルチャー/ダンス・カルチャーのラジカルなところにはまったく無頓着な点だ。初期のクラブ・カルチャーの、未知の世界に繫がる扉を開けてしまったかのような興奮よりも、恋人との世知辛い別れや金銭的な現実が前景化されていくわけだが、実際のクラブ・カルチャーに関わっている多くの人たちはもっとタフに生きている……し、じつは現実にはもっとおもしろい話がいっぱいあるのだよ(長生きしたら、書いたる!)。
せっかくこれだけの素晴らしいオープニングを作ったのだから、もったいなかったというか、話をもっと膨らませてもよかったのに……。まあ、それでも最初の30分は最高だけど。そう、オープニングですべてを許そう。
これは自慢だが、ぼくは映画の舞台となったシャンゼリゼ通りのリスペクトに当時行ったことがある。DJはジェフ・ミルズとディミトリ・フロム・パリスだった。最高のメンツだ。行って、朝までそこにいて──外国のクラブであのときほど女性から声をかけられたことはなかったので、「俺はパリならいけるのかも!」と思っていたら、友人からパリではこれが当たり前だと言われた。主人公もぼくのように大勘違いをしたのだろう──、まあ、とにかくリスペクトではずいぶん気をよくして、最後のひとりとしてそこを出た。通りから細い路地に入ると、いっしょに行ったフランス人は「ここがジャン=ポール・ベルモンドが『勝手にしやがれ』で倒れた場所だよ」と教えてくれた。(野田努)
▼Side B 木津毅
オリヴィエ・アサイヤス一派であるミア・ハンセン=ラヴの映画では、残酷なほどにあっけなく過ぎていく時間がつねに描かれていた。ミアの兄であるスヴェンがDJとして経験したことがもとになっている本作では、90年代前半からのパリ、フレンチ・タッチ・シーンがその勃興から描かれる……のだが、「シーン」以上にここで映されるのは時間の経過そのものである。つまり、ガラージに夢中だった大学生がDJとなり、音楽仲間たちとパーティを開き、ドラッグをやっていくつかの恋をして、そして……それらをひとつひとつ失っていくまでを。おそらくこの映画の観客が期待するような、ポップ史に刻まれるドラマティックな出来事はここではほとんど起こっていない。だが、ハンセン=ラヴ監督の『あの夏の子どもたち』(2009)において映画プロデューサーの自殺がすべてのその横を通り過ぎていく人びとの人生を少しずつ変えたように、重ね続けられるパーティの夜は主人公たちとその恋人たち、友人たち、仲間たち……の人生を動かしていく。それは「栄光と挫折」なんて華やかなものではけっしてなく、ディスコとハウスの名曲が連投される横で、ちょっとした、しかし取り返しのつかない失敗ばかりが積み重なっていく。
映画のなかでダフト・パンクはほんの少しだけ実名で登場するのだけれど、きわめて象徴的な存在としてそこにいる。彼らが巨大になっていくいっぽうでポール(=スヴェン)の人生からはありとあらゆるもの――人間関係だけでなく、音楽への情熱や未来への眼差しといったことも含めて――が退場していき、そして彼自身も「そこ」からの撤退を余儀なくされる。だからこれはフレンチ・タッチ版『インサイド・ルーウィン・デイヴィス』(https://www.ele-king.net/review/film/003843/)だが、余韻は本作のほうがはるかに切ない。
それでもこの映画を観た僕たちは知っている……彼らがたしかにそこにいたことを。『あの夏の子どもたち』で流れた“ケ・セラ・セラ”に涙したように、エンド・クレジットのパーティの映像には目頭が熱くなる。だって僕たちもまた、その夜が二度と戻らないことを身を持って知っているのだから。 (木津毅)
■夫婦の危機

監督 / ナンニ・モレッティ
出演 / シルヴィオ・オルランド、マルゲリータ・ブイ 他
配給 / パンドラ
2006年 イタリア
下高井戸シネマにて、特集上映〈Viva! イタリア! Vol.2〉中の一作として公開中。また、全国順次公開。
イタリア映画祭で上映されたきり、この映画が日本に入ってこないことをナンニ・モレッティ・ファンの僕はずっと怒っていた。が、この2015年の日本でこの映画がようやく正式上映されることに何か宿命めいたものを感じてしまう……なぜなら本作は、ベルルスコーニ政権下、イタリアの政治の危機に向き合って撮られた映画だからだ。原題は『カイマーノ』――強欲を暗示する「ワニ」のことだ。僕が今年日本で観るべき映画は何かを問われれば、絶対に本作を挙げるだろう。
とはいえ、この映画は単純なベルルスコーニ批判の映画ではなく、きわめて複雑な構造を取っている。まず、主人公は冷え切った夫婦関係に頭を悩ませ、また財政的にも窮地に陥っているB級映画のプロデューサー。そんな彼のもとに若い女性からある脚本『カイマーノ』が持ち込まれるのだが、斜め読みして企画を進めたら、なんてこった、ヒットなんてしそうもないベルルスコーニ批判の映画ではないか……。そもそも彼は「政治的な人間」ではない。だが気がついたときは映画制作は始まっている。何もかもうまくいかない――夫婦仲は悪化するいっぽうで、息子のサッカーの試合の応援にも行けない、映画の資金は集まらない、肝心のベルルスコーニ役は見つからないし、お土産のジェラートを買うことすらままならない。だが映画制作は動き出している。こんな映画を撮ったからって、経済も政治も生活も、何が解決するわけではない。だが、もう映画を作ることでしか何も始まらない。もう映画からは逃げられない。
本作は政治映画であると同時にコメディでありメロドラマであり、それに映画と映画制作への愛の告白である。ナンニ・モレッティはとくに90年代の作品においてエッセイ的に「映画とともに生きる」ことを体現していたが、本作においてそれは徹底したテーゼになっている。映画は主人公ブルーノにとって仕事であり生活であり、悩みのタネであり災厄であり希望そのものでもある。自身の監督作に(それこそウディ・アレンのように)よく主演するモレッティが「今回はチョイ役だなー」と思っていたら、詳しくは書かないが、ラストで彼が映画そのものをすべて背負ってしまう様には感動を通り越して完全に打ちのめされてしまった。監督の映画作家として負った責任の重さがそこにはあり、と同時にこの映画が素晴らしいのは、撮影現場で叫ばれる「アクション!」を聞く瞬間を待つ喜びに満ちているからだ。意味があるか、勝てるかなんてわかりっこない。だけど、この映画でモレッティと向き合った僕たちは、とにかくやるしかないのだ。 (木津毅)
■わたしに会うまでの1600キロ

監督 / ジャン=マルク・ヴァレ
出演 / リース・ウィザースプーン、ローラ・ダーン 他
配給 / 20世紀フォックス映画
2014年 アメリカ
全国公開中。
©2014 Twentieth Century Fox
女はひとりで南はメキシコ国境から北はカナダの国境まで約1000マイル歩くというバカな旅をしている。くじけそうになった瞬間に歌を口ずさみつつ、ひとり呟く。「ねえブルース、いっしょに歌って」……すると、そこにブルース・スプリングスティーンの“タファー・ザン・ザ・レスト”がほんの数秒重なってくる。いいシーンだ。いいシーンだし、音楽好きなら身に覚えのある光景だろう。
本作はシェリル・ストレイドによる〈パシフィック・クレスト・トレイル〉の踏破体験の映画化であり、シングルマザーの母を喪い悲しみに暮れるあまりヘロインと行きずりのファックに溺れていた彼女が自分に向き合った旅を描いている。であれば、(邦題にあるような)自分探しの旅の映画だと思われがちだろうが、原題が『Wild』であることからもわかるように、それよりも「荒野」に出ることで「野性」を取り戻しつつ荷物を減らすことについて語られている。冒頭、立ち上がれないほどの荷物を背負っていた彼女は自身の記憶とともに旅をし、いくつかの出会いを通じて、少しばかり身軽になるだろう。
過去の記憶がシームレスにフラッシュバックする映像はヴァレ監督らしい繊細な演出だが、そこでポップ・ミュージックが次々に流されるのもポイントだろう。とくにローラ・ダーン演じる母親との思い出はいつもサイモン&ガーファンクルの“コンドルは飛んでいく”とともにあり、だから気がつけば過酷な旅の道程でそのフォークロアのポップ・ヴァージョンが大音量で流れている。iPhoneではなく、記憶から音楽が流れ出す旅についての映画。観終えたら爆音でサイモン&ガーファンクルを聴きたくなる。それから荒野に旅立ってもいいだろう。 (木津毅)
■アメリカン・ドリーマー 理想の代償

監督 / J・C・チャンダー
出演 / オスカー・アイザック、ジェシカ・チャステイン 他
配給 / ギャガ
2015年 アメリカ
10月1日(木)より、TOHOシネマズ シャンテ 他にて全国公開。
© 2014 PM/IN Finance. LLC.
70年代のニューヨークを描いた優れたギャング映画の空気を彷彿とさせつつ、本作は1981年のニューヨークを舞台として『もっとも暴力的な年』とのタイトルを持っている。つまり、燃料業界で成り上がることを夢見た男の物語でありながら主役は「その年のニューヨーク」に他ならず、フレームの外で起こっていること――「時代」そのもの――に翻弄され、あがき続ける人間たちのドラマである。監督は1971年生まれの気鋭J・C・チャンダーで、だからリアルというよりは彼が憧憬した街の荒涼さが画面に充満している。実際にはドンパチやるギャング抗争映画ではなく、30日間の期限のなか資金を集めるために奔走するという大変地味な話なのだが、それでもグラフィティだらけの電車のなかで追跡劇があったりとどうにもスリリングだ。
『インサイド・ルーウィン・デイヴィス』で浮上したオスカー・アイザックの弱々しい発話が印象的で、貪欲に成功を追いながらもそのこと自体に疲弊しているようにも見える。その両義性がアメリカということなのだろう。 (木津毅)