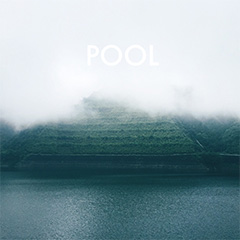Albino Sound Cloud Sports Pヴァイン |
それはどこで鳴っている?
それは25年前なら、ウェアハウスや小さなクラブだった。それは30年前ならベッドルームだった。それは35年前ならライヴハウスだったかもしれない。ま、インターネットの共同体でないことはたしかだろう。
で、それはどこで鳴っているんですか?
アルビノ・サウンドはしばし考える。
「……現実と明らかに乖離しているもの」と彼は重たい口を開く。
なんですか、それは? ファンタジー?
「ファンタジーとも違いますね。やっぱり現実が剥離しているというか。剥がされて浮いている1枚、みたいな」
それをファンタジーというのでは?
「それがファンタジーになる場合もあるし、もっとものすごい虚構というか彼岸みたいなというか……説明が難しいんですけど、僕は剥離感と呼んでいます」

ぼくがいろんな音楽を聴き出した10代の頃は、東京のシーンって完成されていたんですよね。で、そういうところに変な違和感があったんです。外から耳に入ってくるものと、生きている近くで起きていることの状況があまりにも違い過ぎていて、その間の隙間だったり不在感が自分の音楽のルーツになるんだと思います。
東京で生まれ、横浜で育った彼は、10代のときにポストロック、レディオヘッド、そしてクラークやボーズ・オブ・カナダの世界にどっぷりはまっていた。深夜のTVから流れるエレクトロニカに耽り、そして学校で音楽の話題を共有できる友人もなく、ただ黙々と聴いていた……という。
そして、17才の時の2004年の『スタジオ・ヴォイス』の特集に人生を狂わされる(松村正人が知ったら喜ぶだろう)。彼は、カンを知り、アーサー・ラッセルを知った。この頃は、ちょうど紙ジャケ再発が盛んな時期だったこともあって、ひと昔前なら聴くことさえ難しかったそれらの音源との距離は縮まっていた。
「とにかくアーサー・ラッセルにハマって、『ワールド・オブ・エコー』(1986年)がとくに好きになりました。ポストパンクにいったりとか、それこそニューエイジ・ステッパーズやディス・ヒートに夢中になって、最終的にクラウトロックにたどり着きました。ぼくはもともとは、クラブ・ミュージックではないんです。ひとりでギターを使ってドローンとかアンビエントとかをやっていたんですね」
「思春期の頃は、ポスト・カルチャーが蔓延していたというか、なんでも“ポスト”がつく世のなかだった。結局はエレクトロニカという言葉もそうですし……」
いわゆる細分化ですね。
「そうです」
苛立ちを覚えましたか?
「世代的に虚無感が支配していたので、ロスト感で生きていたところはあります(笑)」
話は逸れるけれど、アーサー・ラッセルの再評価は、この細分化の初期段階のときはじまっている。ぼくは、90年代末のUKで起きた再評価によって彼のことを知るが、彼の再発がレコ屋に出はじまめのが2003年以降である。
ラッセルとは、ジャンル音楽家であることを拒んだ何でも屋で、つまり、シーンが分断されていても越境的な個によって回路は生まれ得ることを証明した人物とも言える。松村正人がディスコで踊ることはない。しかし、ラッセルは踊ってしまった。
もっとも、ぼくが若い頃はシンプルに出来ていた。ロックのスター崇拝の文化やホワイティー一辺倒な世界観への違和感がそのままクラブ・カルチャーへの情熱に転換されたと言っても良い。好きなのは音楽、主役はリスナー。高い金払ってスターを崇めるくらいなら自分たちでやれ。その実践の場がクラブだったので、たとえどんなに実験をやっても、重箱の隅ばかりを見せびらかすマニアによる支配はなかったし、ふだん出会うことのない人たちが出会うことができた。重要なことは、踊れるか、ないしは何かを感じさせてくれるか、ないしは、いままで感じたことのない感情に直面させてくれるのか、そのいずれかだろう。
細分化後の世界のつまらなさとは、周辺だけで完結してしまうところであり、周辺小宇宙群を突破するダイナミズムが、いまのマージナルな文化にもあって欲しいとぼくは思うのだが、レッドブルを何杯飲んでも無理だろう。が、アルビノ・サウンドは、そのヒントは「カンとクラスターにある」と主張する。そうか、クラウトロックか……。
彼が打ち込みの音楽をやる契機となったのは、マウント・キンビーだという。マウント・キンビーは、ダブステップ以降のクラブ・サウンドにIDMを折衷したことで、一世を風靡した連中である。ぼくも彼らが出てきたときは興奮した。
「とくにライヴにやられました。ライヴでは彼らは歌うけど、その歌が下手じゃないですか(笑)? 完璧じゃないけど、彼らが向き合うなかで出てくるエモさに、がっちりと掴まれてしまいました。ぼくは彼らのエモなところに感動したんです。ああいうインディ・ロック的なユース感はマウント・キンビーにありますよね。“メイビーズ”とか。曲によりけりですけどね。あとはあの疾走感ですかね。とにかく、マウント・キンビーと出会うまで、家でひたすらパン・ソニックを聴いているような生活だったので(笑)」
「彼らはクラブ・ミュージックがやりたかったわけではなかっただろうし。おそらくですけど、ソフトの値段が下がって、ライヴをどうやるかを考えた結果、ああなったんだと思います。結果、ドラマーを後から入れていましたし。自分が音楽からすっぽり抜けていたときにあれが来たから、すごく新鮮な音楽に感じたのかもせれません」
「ぼくがいろんな音楽を聴き出した10代の頃は、東京のシーンって完成されていたんですよね。で、そういうところに変な違和感があったんです。外から耳に入ってくるものと、生きている近くで起きていることの状況があまりにも違い過ぎていて、その間の隙間だったり不在感が自分の音楽のルーツになるんだと思います。都市的な孤独だったりとか、言いようのない感情だったり。そこにも隙間がありました。それは音楽にも反映されていると思います」
彼の音楽が鳴っているところは、ここだ。
いわゆる既存のクラブにも100%感情移入できないし、汗だくのライヴハウスにも、そしてインターネット共同体にも、どこにも行く場所がない人たちの場所を確保すること。ここからは、NHKコーヘイからカリブー、ローレル・ヘイローからリー・バノンにいたるまでの、あるいはゴートからドリーム・プッシャーにいたるまでの一種の共通の感覚を引き出せる。
かつて商業主義にがんじがらめになったテクノは、エレクトロニカというジャンル名のもとで別の潮流となった──まあ、悲しい細分化の走りでもある──ことと、どこか似ているが、しかしこの新しいエレクトロニック・ミュージックの潮流は、どこにでもアクセスできるし、拒んでいないという点では、ニュアンスが違っている。
アルビノ・サウンドのデビュー・アルバム『クラウド・スポーツ』は、自分たちの居場所を探している人たちの、今日的な折衷主義の成果とも言える。ここには、いままで書いてきたような彼の影響、エレクトロニカ、ポストロック、そしてシカゴのジュークの影響まである。
なにしろ彼は、そう、あのリキッドルームのタイムアウト・カフェでふだんはフライパンを握っているのである。
「ぼくはあの場所で、基本的に鍋を振りながらいろいろな音楽を聴いている」と彼は言う。「見ているだけなので、ものすごく客観的にそこを見ていられたのは大きいです」
隣には太郎さんがいて、とくにエイプリルさんがDJしているし(笑)?
「ミニマルやってるひともジュークやってる人もいるし、ヒップホップをやっている人もいる。〈ブラックスモーカー〉は毎年ブラック・ギャラリーをやってらっしゃるし、ロスアプソンのTシャツ市もある。素晴らしい環境です(笑)」
この素晴らしい環境が、アルビノ・サウンドの作品にどれほど関わっているのかはわからないが、少なくとも、彼はフライパンを持ちながら日々アンダーグラウンドな音楽を意識せずとも吸収しているのである。
子供の頃はテレビで流れるJポップぐらいしか聴いていなかったんですよ。で、初めて〈ワープ〉系のような音楽を聴いたときに、『嘘をつかれていたんだ』と思ったんです。自分がいままで聴いていたものは嘘だったと
驚くべきことに、彼がエレクトロニック・ミュージックを作りはじめたのは、去年の3月からだ。つまり、2014年から2015年に作られているこのアルバムは、長年家に籠もって作り続けきた人の作品ではない。それが、人に聴かせたらあれよあれという間に好意的に受け止められて、いまこうして作品が出ることになったというわけだ。「数年前まではパソコンすらまともに使えなかった」と彼は笑いながら話す。
「人間的に群れるのも好きなほうじゃなんです。たとえば、本を読むと文字から音を想像できるじゃないですか? ぼくが好きなのはそれです。すごい国語的な感覚で音楽を作っている自覚はあります。だから自分らしさを出すものとして、言語的な作り方があるんだと思います」
彼は自分の音楽をこのように分析する。
「あと、曲作りはじめたときに、映像ディレクターをやっている仲が良い友だちがいて、いっしょに仕事をするようになったんです。その頃のぼくは全然パソコンが使えないのに、そういう依頼がいきなり来た。で、いざいやってみたら、映像と音楽のグリッドって全然違うんですよね。たとえば『顔が横を向くから音楽はこう変わってほしい』とかは、小節単位で起きることじゃないので、それが面白かった。音楽的な判断じゃなくて、映像的な判断が自分に加わると、どんな変化をしても整合性を保てるし、これはこれで面白いというのが、今回のアルバムには反映されています」
「彼(=石田悠介)が去年自主制作で映画(=Holy Disaster)を作ったんですけど、そのサントラを自分とボー・ニンゲンのギターのコーヘイ君といっしょにやったんですけど」
ちなみに、高校の先輩にはボー・ニンゲンのヴォーカリスト、そしてネオ・トーキョー・ベースのメンバーもいたという。
「ボー・ニンゲンのギターのコーヘイ君といっしょに『なんかやろうぜ』と世間話をしていたら、たまたま僕が(スティーヴ・)アルビニ・サウンドを言い間違えてアルビノ・サウンドと言ったら、それはなかなか面白い名前だと。それで去年レッドブルに応募するときのための名義を考えていたら、これでいいだろうと。どういう音楽か想像つきづらいのも面白いなと思いました」
「子供の頃はテレビで流れるJポップぐらいしか聴いていなかったんですよ。で、初めて〈ワープ〉系のような音楽を聴いたときに、『嘘をつかれていたんだ』と思ったんです。自分がいままで聴いていたものは嘘だったと」
こういう感動は、ぼくもよくわかる。中学生のとき、初めてクラフトワークを聴いたとき、この世界にはこんな音楽があるのかと心の底から驚き、興奮した。これだけ音数が少なく、すべてが反復なのに、これほどまでに聴いていて気持ちがいい。そして、その回路が開けた自分自身にも嬉しかった。いったいこれは何なのか? そう思うたびにワクワクした。意味もなく。
「だから自分が音楽を聴いて、想像力だったりとか、感情の喚起と言ったら変かもしれないですが、いまの音楽も昔の音楽も自分にとってはそういうものだったので、それをリスナーに感じて欲しい。音楽を聴くことで、音楽以上の何かを感じてもらえれば嬉しいんです」
そんなわけで、確実にいま、新しいエレクトロニック・ミュージックが混ざりながら、ぼんやりとだが新しいシーンが形成されつつある。アルビノ・サウンドもその一員だ。




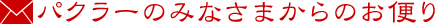

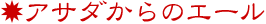


 Valentino Canzani aka French Fries のストーリーは、1975年に彼の両親が当時の独裁的な政治から逃れるためウルグアイよりアルゼンチンに亡命し、パリへ行き着いた場面から始まる。彼の父親である Pajaro Canzani はウルグアイのマルチ演奏者として、そして自身のグループ “Los Jaivas” のプロデューサーとしてスーパースター的な地位を築いていた。パリに辿り着くと、ドラムや様々な種類のパーカッションを備えたスタジオを再建したが、これがのちに Valentino や彼の妹のリズムセンス、レコーディング技術を幼い頃から習熟させるきっかけとなった。
Valentino Canzani aka French Fries のストーリーは、1975年に彼の両親が当時の独裁的な政治から逃れるためウルグアイよりアルゼンチンに亡命し、パリへ行き着いた場面から始まる。彼の父親である Pajaro Canzani はウルグアイのマルチ演奏者として、そして自身のグループ “Los Jaivas” のプロデューサーとしてスーパースター的な地位を築いていた。パリに辿り着くと、ドラムや様々な種類のパーカッションを備えたスタジオを再建したが、これがのちに Valentino や彼の妹のリズムセンス、レコーディング技術を幼い頃から習熟させるきっかけとなった。