UKガラージのコンテンポラリーな王道を再定義したディスクロージャーのブレイクをピークに、一連のUKベース・シーンのメインストリーム進出もそろそろ幕を引きそうな気配となっていますが、さて、文化系かつ進歩的ポップ・ミュージック愛好家のみなさま、果たして次はどこを拠り所にお過ごしでしょう。全世界のDQNを巻き込んで猛威を奮いつづけるEDMの圧倒的パワーを目の当たりにして、もはや行き場を失って呆然とする……なんて方がいらっしゃらないかと、余計な心配も募るわけです。ナードかつギークではあるけれど、根本的に苦悩のない僕みたいなタイプは、正直なところジェイムス・ブレイクが歌いはじめたあたりから脱線気味で、後のポスト・ダブステップ〜IDM再興にしても、脇道のインダストリアル、アンビエント、グライムにしても、どうにもシリアスな成分が多すぎて馴染めないと思ってきたわけです。
そんな折、個人的にもえらくハマったのが、2014年から話題となっている〈PCミュージック〉というネット・レーベルを中心に盛り上がる、90’sレトロ・フューチャリスティックなエレクトロ・ポップ・ミュージック、俗称“バブルガム・ベース”です。その名の通り、風船ガムのようにカラフルで甘く刹那的(つまり俗っぽくキャッチーで安っぽい)ユーロ・ポップと、10年代のベース・ミュージックのマナーが意図された音楽ということで、かなり絶妙なタグ付けではないかと思います。
A.G.クックの主宰するこの〈PCミュージック〉については過去に日本語のテキストもいくつか出ているので省略させてもらいますが、そのA.G.クックの盟友であり、シーンの象徴的アーティストであるソフィーが、ついにデビュー・アルバム『プロダクト』をリリースしました。
2013年にグラスゴーのUKベース・ミュージック名門〈ナンバーズ〉からリリースしたセカンド・シングル『ビップ/エル(BIPP/ ELLE)』のヒットで注目を集めたソフィーは、サミュエル・ロングによるソロ・プロジェクト。当初は素性がよくわからず、アーティスト名と女性ヴォーカルを起用したサウンド、モデルと思われる女の子をつかったビジュアル・イメージを使用するために、女性アーティストと思っていた人が多かったよう(もちろん意図的な仕掛け)ですが、20代の男性アーティストです。
古いWindows内蔵のFM音源(もしくはエミュレータなのかな?)を使用して制作されたと思われる、不協和で歪んだエレクトロ・サウンドと、異常にピッチを上げられ女性ヴォーカルの組み合わせで展開される彼のポップ・ミュージックは、とにかく記名性が高くキャッチー。つづく2014年のグリッチ・ヒップホップなシングル「レモネード」(※今年になって米マクドナルドのCMにも採用)も話題となり、前述のA.G.クックとのユニットQTで〈XL〉からリリースした「ヘイ・QT」のヒットを受けて、メインストリームのミュージック・シーンでも注目を集めました。ここからのスピード感は流石に10年代という展開。ディプロのフックアップを受けて、なんとマドンナのシングル曲“ビッチ・アイム・マドンナ(Feat. ニッキー・ミナージュ)”を共同プロデュース。さらにチャーリーXCXの次回作にもプロデューサーとして参加が決定しており、相当な変化球ながら、一躍売れっ子プロデューサーの仲間入りを果たしそうな勢いとなっています。また日本では、安室奈美恵の最新アルバム『_genic』に収録の“B Who I Want 2 B feat. HATSUNE MIKU”の楽曲プロデュースを手がけているというトピックも面白いですね。
余談になってしまいますが、〈PCミュージック〉界隈のアーティストの嗜好性とサウンドの親和性から期待するに、久しぶりに日本と英米のポップ・カルチャーがリンクした盛り上がりの芽があるかもしれないですね。ソフィーやA.G.クックは、じつは〈マルチネ〉からリリースしているボーエン(bo en)やケロケロボニトのメンバーとは同じ芸術大学の友人同士だったようで、相当にコアなJポップ(とくに中田ヤスタカ周辺)マニアが集まっていたご様子。QTのコンセプトには明らかにPerfumeの影響があるだろうし、先日は〈PCミュージック〉のダックス・コンテンツがSekai No Owariをリミックスするなど、アーティスト同士の交流が急速に具体化してきている。ライアン・ヘムズワースやポーター・ロビンソン、スカイラー・スペンスあたりのポスト・インターネット世代のアーティストによる、Jポップ・カルチャーに対するポジティヴな評価というのは、日本側の視点からするとファンタジーではあるのだけれども、たしかにEDMのような圧倒的なマッチョイズムへの抵抗手段として、中田ヤスタカの方法論はパーフェクトに映るのかもしれない。「カワイイ」みたいなのがキーワードになるのは、HCFDM(ハッピーチャームフールダンスミュージック)のときといっしょだし、結局、日本人が得意なのはそこだよねと思います。
さて、話を戻して、ソフィーのアルバム『プロダクト』。これまでにリリースされたシングルに収録された“レモネード”“ビップ”“ハード”“エル”に、新曲4曲を収録したシングル・コンピ的内容の作品ということで、正直なところ何か新味があるわけではないのだけれども、媚もない、これまでのサウンドとヴィジュアル・コンセプトが貫徹された内容。つまりエッジは充分すぎるほど効いている。ポップ・ナンバーとしては新曲“ジャスト・ライク・ウィ・ネヴァー・セッド・グッバイ”が彼の関連作の中でもトップクラスの好曲だけど、〈ナンバーズ〉からのリリースにふさわしい、ベース・ミュージックらしいグルーヴを成立させたヒップ・ハウス・チューン“Vyzee”も人気を呼びそうですね。
ヴェイパーウェイヴの醸造したポスト・インターネット以降のシーンを震源地にしたアーティストが、現実のメインストリームのポップ・チャートまで侵食していく、いよいよそんなタームに入ってきたことを象徴する1枚として、2015年の重要作に推しておきたいと思います。























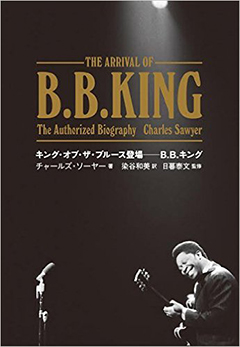 チャールズ・ ソーヤー
チャールズ・ ソーヤー