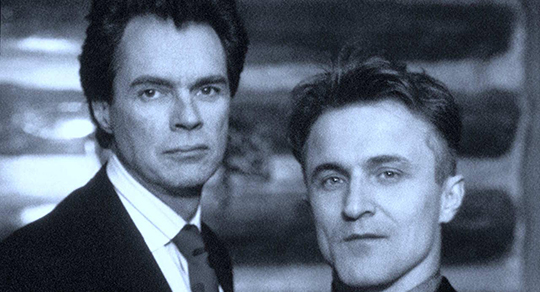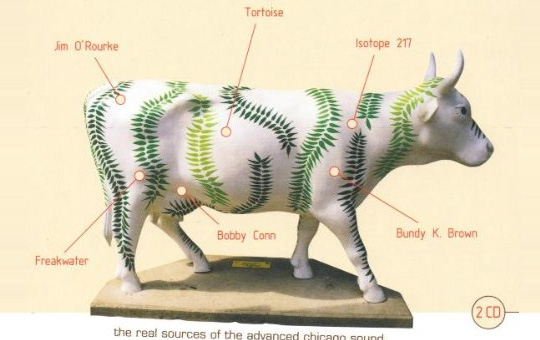Mystery Jets Curve Of The Earth Caroline / ホステス |
ミステリー・ジェッツというこのロンドンのバンドのことは、「テムズ・ビート」という呼称とセットで記憶している方が多いにちがいない。彼らの最初のアルバム『メイキング・デンス(Making Dens)』がリリースされてからもう10年にもなろうとしているが、テムズ・ビートこそは、人々が「ヨウガクの国内盤」を普通に買っていた最後の時代を華やがせたバズ・ワードのひとつであり、彼らのアルバムはそこに象徴的な彩りを与えるものでもあった。そういった呼び名はメディア主導のカテゴライズに過ぎず、本人たちにそれを牽引するというようなつもりもなかったと言われるかもしれないけれど、そこに前後してモッズのやんちゃにアイリッシュ・フォークの牧歌性、UKトラッドを何度めかの新鮮さで甦らせたバンドがいくつも矢継ぎ早に見つけだされたことはたしかで、少しエキセントリックな佇まいの中にサイケの系譜ものぞかせたミステリー・ジェッツもまた、ロックをリヴァイヴァルとしてしか知らない2000年代の耳に共感と興奮を与えてくれた。ほかにもその頃は「ニューレイヴ」とか「ニュー・エキセントリック」とか、UKのロックは元気だったし、そうした言葉を泡沫のように生み出し伝えるメディアも元気だったことが、ひとかたまりで思い出される。
そこで、つづいてリリースされたエロール・アルカンのプロデュースになるセカンド『トゥエンティ・ワン』(2008)までは聴いて、あとはどうなったか知らない、という方も正直なところいらっしゃるのではないだろうか。あのときはただ時代の息吹を聴き、祭を楽しんでいたのであって、とくにミステリー・ジェッツそのものを聴いていたのではなかった、というような──ポップ・ミュージックのそれもまたダイナミックでおもしろいところだから、その酷薄な享受のしかたを責めないでいただきたいと思うが、しかしそうであればこそ、ほとんどが一時で姿を消していったそれらバンド群において、後々もリリースをつづけて10年にもなろうというミステリー・ジェッツには、「何かがあった」ということになる。時が移り、状況が変わり、騒がしい情報に影響されることもなく聴いた『カーヴ・オブ・ジ・アース』は、優しく懐かしかった。当時が懐かしいというのではなくて、もっと普遍的な、親しく温かみのある感覚。地球のモチーフにしたジャケットにスケール感のある冒頭曲“テロメア”からは気宇壮大なテーマを、また『ホール・アース・カタログ』をコンセプトに据えスチュアート・ブランドとの対話が下敷きにあったというエピソードからはサブ・カルチャーと未来についてのヴィジョンの提示があるのかと先走って想像してしまうが、“ボンベイ・ブルー”から先こそがこのアルバムだと言いたい。それはここで語られているように、むしろ若き日の父、若き先人たちのイノセンスへの共感というべきパーソナルでかつ普遍的な感覚に端を発し、そのために多くのひとの感情に優しく響く音になっているように思われる。
この「普遍」というところへと、彼らは一枚ごとにバンドとして全力を傾けるべきテーマを掲げながら、こつこつと進んできたのではないか。ウィリアム・リースの言葉からさらに推量れば、それは時代から自由になって、内側から出てくる自分たちの記憶やルーツが自然と溶けだしたようなものなのかもしれない。リヴァイヴァルやリファレンスという「わざわざ」の意図なくそれはUKのポップスであり、穏やかで優美な、薄曇りのサイケデリック・ロックだ。“サタナイン”が美しい。
昨年11月の〈ホステス・クラブ・ウィークエンダー〉明け、質問に答えてくれたのはウィリアム・リースとカピル・トレヴェディだ。
ミステリー・ジェッツ / Mystery Jets
2004年にブレイン・ハリソン、ウィリアム・リース、カイ・フィッシュ、カピル・トレヴェディが結成した4人編成バンド。2006年にファースト・アルバム『メイキング・デンス』をリリースし、「テムズ・ビート」の象徴として世界的な評価を浴びる。セカンド『トゥエンティ・ワン』につづき、2010年には名門〈ラフ・トレード〉移籍後初となるサード『セロトニン』を発表。2012年にオリジナル・メンバーであるカイが脱退するも通算4作めとなる『ラッドランズ』を作り上げ、2015年には新メンバー、ジャック・フラナガンを迎え入れ5枚めのニュー・アルバム『カーヴ・オブ・ジ・アース』を完成させた。
過去を研究することがいちばん大きかったと思う。それにはロンドンに戻らなければならなかったんだよ。(ウィリアム・リース)
■今作の背景にはアメリカーナの研究があるということですが、どんなものを聴いていらっしゃいました? あるいは、それは音楽にかぎらない探求だったのでしょうか?
ウィリアム・リース(以下ウィリアム):今回のアルバムにはあまりそういうところはないかもしれないな。
■そうなのですか? それはごめんなさい。では、前作のお話をうかがっても?
ウィリアム:あのときはすごく新鮮な体験だった。テキサスに行って、スタジオをつくって、音楽を生んで、レコーディングする──それは僕たちがずっとやりたかったことなんだ。夢でもあった。とくにアメリカ大陸から生まれてきた音楽を愛してきた身としては、すごくやりたかったことなんだよ。でも、この作品にはその痕跡はあるかもしれないけど、具体的にどんな影響があるかというと、明確には言えないな。音楽的な影響というよりは、もっと本質的な意味で、その体験を経たことによって今作では過去を振り返らなければならないということに気づいたんだ。それで、若い頃に聴いていた音楽をたくさん聴き返して、ロンドンに戻って、かつてそれを聴いていた場所でもういちど音楽をつくってみた。……そうだね、過去を研究することがいちばん大きかったと思う。それにはロンドンに戻らなければならなかったんだよ。
■なるほど。アメリカというものにぶつかって、あらためて見えてきた英国について教えてください。
ウィリアム:そういうふうに自分で考えたことはなかったけど、たしかに感じられるものはあったような気がする。おもしろいもので、アメリカ文化という、自分とはぜんぜんちがうものに触れて──「これじゃない」というものに触れて、はじめて人は自分を意識できるのかもしれないね。そういうところはあったかもしれない。ただ、作品について言えば、“『ラッドランズ(Radlands)』パート2”をつくることはできなかった。それに自分たち自身をそのまま表す作品にしなきゃいけないということはわかっていた。『ラッドランズ』は架空のキャラクターを設定して生まれた作品だったけど、今回はもっとパーソナルな作品だ。それがイギリス的かどうかということになると自分にはわからないし、そこはもう自分にとっては重要なことではないんだ。
むしろ、それはファースト(『メイキング・デンズ(Making Dens)』)でやったことかもしれない。あれは、曲名からしてもものすごくイギリスっぽいものだったと思うよ。シド・バレットだったりキンクスだったり、自分たちの好きなアーティストたちを意識していたし、自分たちもその系譜に並びたいと思っていたんだ。でもいまは「国」というレベルではないところで自分たちのアイデンティティを持ちたいと考えているかな。もちろん、聴いてくれた人がこの作品をイギリス的だと思ってくれたとするなら、それはどんなとこなんだろう? って興味深いよ。
いまは「国」というレベルではないところで自分たちのアイデンティティを持ちたいと考えているかな。(ウィリアム)
カピル・トレヴェディ(以下カピル):どこでレコーディングをしてどういうことをやるかというのは、ひとつ前の作品の反動も大きいよね。3作めのときは、とても大きくて洗練されたスタジオで録ったから、次はアメリカの田舎の家をスタジオにしてみようと思ったし、そうするとその次(今作)はもういちどロンドン──自分たちが育ったところでやってみようということになる。それが自分たちにとっての新しいチャレンジってことだよね。
■なるほど、よくわかりました。「テムズ川のほとりの小屋で録音された」と聞くと、どうしてもつい原点や精神的な拠り所を求めての録音だったのかなと想像してしまって。必ずしもそういうわけではないんですね。
ウィリアム:ロンドンという意味でのルーツではなくて、もっとパーソナルなルーツに戻るべきだと思った、ということかな。この10年間、自分たちがバンドでやってきたこと、それから人間として変化してきたこと──恋愛だったり人との関係だったりね──を振り返らなければならない時期だったのかもしれない。実際にバンドもひとつのチャプターが終わって次の分かれ道に突き当たったようなところがあって、そういう意味でもいったんホームに戻るということが重要だったんだ。
もっと現実的なことを言えば、家族や友だち、ロンドンに戻っていっしょにいなきゃいけない人たちもいた。そんな事情もありながら、そういうことも全部が曲に反映されていったのは不思議なものだよね。パーソナルだというのはそういうことかな。
『ホール・アース・カタログ』っていうのは、あの時代にはたしかに生きていたイノセンスや楽観性を表現しようとしたものだと思うんだ
■ええ、なるほど。一方で資料などを拝見すると今回はスチュアート・ブランドとの対話やコミュニケーションが今作の大きなインスピレーションになっているという紹介もあります。そのあたりはどんなことがきっかけで、どのようなやりとりになったのでしょうか?
ウィリアム:今日はいくつものメディアから『ホール・アース・カタログ』についての質問を受けたんだ。そのたびに新しく答えを発見するような気がする。いま思ったのは、やっぱり『ホール・アース・カタログ』っていうのは、あの時代にはたしかに生きていたイノセンスや楽観性を表現しようとしたものだと思うんだ──60年代という時代の持っていた、ね? 僕たちのパーソナルな視点から言えば、かつてブレイン(・ハリソン)のお父さんのヘンリーもバンドのメンバーだったんだけど、彼は『ホール・アース・カタログ』をリアルタイムで知って感じていた人間なんだよ。だから僕たちにとっては過去といまがつながるような感動があったかな。当時の若い男の人たちはそのオプティミズムやイノセンスを表現していたわけだけど、それはかたちは異なれど僕たちも表現していることなんだ。本質は同じなんだよ。それに『ホール・アース・カタログ』はインターネットの先駆けみたいなものでもある。インターネットにおいてもっともポジティヴな部分は人をつなごうとするところ、点と点をつないでコミュニケーションを生むところだよね。それは過去といまがつながるということでもあるし、ヘンリーと僕らがつながるというパーソナルなことでもある。
■その「イノセンス」や「楽観性」というのは、本来、音楽がもっともたやすく体現しうるものでもあると思うんですね。でも世の中が複雑きわまりなくなっていくものだから、いまの音楽はますます多大な情報量を含みこんで表現しなければいけなくなっているようにも思われます。そういう、一種息苦しい状況の中で、音楽が提案できるものが何かという、その答えが今作にあると考えていいですか?
カピル:まず、オプティミスティックなものがいちばん強く聴こえるのは、それがちゃんと意識されたものである場合だと思う。実際に絶好調なときにオプティミスティックな曲を書くよりも、たとえばすごく苦しい状況にあったりしても──自分の楽観的な部分が脅かされるような状況であってもなお楽観的であろうとするときに、その表現は強いものになるんだ。
まず、オプティミスティックなものがいちばん強く聴こえるのは、それがちゃんと意識されたものである場合だと思う。(カピル・トレヴェディ)
ウィリアム:たとえばいまパリはテロを受けて大変な状況を迎えているよね(取材は2015年11月に行われた)。そんなときに、ただバカみたいに楽観性を振りかざして曲を生むことなんてできないと思う。だからこの作品もオプティミスティックに聴こえたとしても現実的なことを表現しているつもりなんだ。曲というのはひとつのプロセスであって、そこで提示してあるものは自分たちの苦しかったり不安だったりする経験でもあるんだけど、それにただ打ちひしがれてしまうのではないという部分を表現したいというか──どうやってそれを赦すか、とか、どうやってそれと折り合いをつけるか、それでも前に進むにはどうしたらいいか、とかね。
ビートルズとかキンクスの曲を聴くと、いまの時代にはないナイーヴさみたいなものを感じる。僕はその時代を生きたわけじゃないからわからないけれども、そういうことにはちゃんと理由があったはずだし、何かいまとはちがう明るさみたいなものもあったんだと思うんだ。ただ、いまという時代はいろんなところであまりにいろんなことが起きているけれども、そこにちゃんとした原因や理由みたいなものが見出しにくいというか。なんでそうなったのか? そうしたことがごちゃごちゃになってグレーに見える。いまの音楽にはそのエッジが表れていると思うし、自分たちの作品にもそれは表れているんじゃないかと思うよ。ある意味で、明るいだけではなくてビタースウィートなものにね。今作はそういう意味でのオプティミズムを持っていたかもしれない。
ビートルズとかキンクスの曲を聴くと、いまの時代にはないナイーヴさみたいなものを感じる。(ウィリアム)
■60年代という時代が抱いていた理想と、いまの時代が抱けるものとの差のなかで、楽観性ということのポジティヴな意味を考えているわけですよね。……すごく思索的なバンドなんだなあとあらためて驚いているのですが、でもあえてお訊ねすると、そういうことへの回答を音楽で行う必要はないじゃないですか? きっとキャリアを重ねていくなかで取り組むテーマや音楽観も大きくなっているのではないかと思うのですが、そのなかでいま自分たちの目指すべき音楽のかたちをどんなふうに考えていますか?
ウィリアム:それはなかなか答えにくいな。音楽はある明確な何かを表現しようと思ってつくるものじゃないからね。それは自分が生きてきたことの結果として生まれるもので、たしかにタイトルなりコンセプトなりがついてひとつの製品として作品ができあがっているように見えるかもしれないけど、音楽そのものはそれそのものだけを表現している──極端に言えば、曲のほうからやってくるものなんだ。だからこそ、生まれてきたときはぜんぜん複雑なものではないし、実際に複雑にも聴こえないと思う。つくるのにものすごく努力したり考えたりはするけどね。それをインスピレーションと呼ぶ人もいるけれど、曲をこれだというかたちにするのはコンセプトじゃないんだよ。