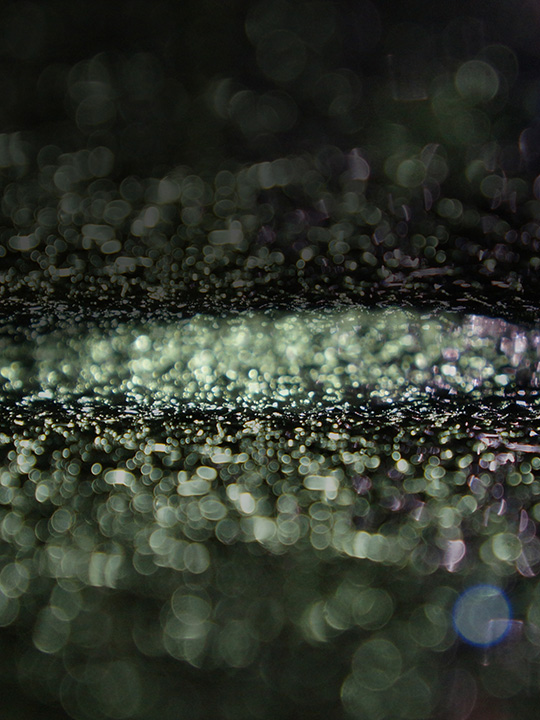きたる6月4日(土)~5(日)、長野県木曽郡木祖村「こだまの森」にておこなわれるTAICOCLUB'16の出演者としてArcaが発表された。これが二度目の来日になるが、もちろんビョークの作品への参加を経て、問題作『ミュータント』リリース後の初めての来日になるので、注目される方も多いだろう。また、エレクトロニック・ミュージックのアクトとしては、すでにOPNの出演もアナウンスされている。
TAICOCLUB'16
2016年6月4日(土)- 6月5日(日)
at 長野県木曽郡木祖村「こだまの森」
出演アーティスト
*- Arca -DJ set (VE)
*- あふりらんぽ (JP)
*- KiNK (BG)
*- LORD ECHO (NZ)
*- LUCKY TAPES (JP)
*- Nozinja (ZA)
*- Oneohtrix Point Never (US)
*- サカナクション (JP)
*- シンリズム (JP)
*- SPECIAL OTHERS (JP)
and more…
MORE INFO: https://taicoclub.com/16/2nd/
チケット販売に関して: https://taicoclub.shop-pro.jp/