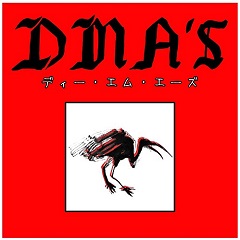 DMA's DMA's Infectious / ホステス |
DMA'sを本当にオアシスの後継だと考えるひとはいるだろうか? もちろんひとつの売り文句にすぎないが、そうした喧伝が彼らに翼をつけるとも思われない。われわれはべつに次のオアシスを求めているわけではなく、ただそこで90年代のUKインディを思わせる音が素朴に素直に鳴っていることを喜び、また、オーストラリアのバンドであるという出自が、洒落っ気と愛嬌を伴った「いなたさ」としてうまく読み替えられていることに大いに反応しているのだ。
素朴さの価値はいまそれほどまでに高い。そして、コートニー・バーネットの存在によってにわかに熱いまなざしを向けられているオーストラリアは、その金脈であるかのように幻想されている。彼女は先日グラミー賞「最優秀新人賞」にノミネートされたが、むしろその事実よりも、ロンドンでのゲリラ・ライヴの様子のほうが、この現象をうまく伝えているといえるだろう。みな、ロックを継ぎ得るヒーローではなくて、ふと聴こえてきた素朴さ、その清新な力に足を止めているのだ。
それに加えて、昨年作『カレンツ』の絶賛ムードで存在感を増したテーム・インパラもオーストラリア熱を支える。系譜としては彼らに近いサイケ・バンド、ガンズにジェザベルズ、あるいはシドニーのインディ・ポッパー、アレックス・ザ・アストロノート、もう少しヴィンテージ感のあるオーシャン・アレイなどなど、ロックはどこに残っているのかと「発掘」が止まらない。
しかしてDMA'sは? 彼らもまた、素直で少し懐かしい音を聴かせてくれる。ただし、アークティック・モンキーズ以降のロックであることがわかる。かつ、90年代のUKインディだけではなく、同時期のUSインディの感覚もうっすらと漂う。「オルタナ」という名のまま古びていった音を、彼らはいまの感性のまま無邪気に楽しんでいる。
また、キウイ・ポップの牙城にして、USインディとかの地のロックとの紐帯である〈フライング・ナン〉とも関わりが深いようだ。一貫してガレージ―で素朴なスタイルによって強固なレーベル・カラーを築き愛されてきた彼らの縁戚に、このようにフレッシュなバンドが生まれていることは、現在のバブル状況に関係なく、そもそものシーンの層の厚さを証明しているといえるだろう。
よって、DMA'sについてはもう、聴くだけだ。彼らが楽しむようにわれわれも楽しめばいい。ただ、ロックというジャンルの可能性について割合にクールな視点を持っているところは現代ふうというべきである。けっしてレイドバック志向なわけではない。コートニー・バーネットがそうであるように、彼らはとても自然にその音を呼吸していて、それがなにより気持ちよいと感じる。もし「大型」新人と呼ぶのなら、そのような点をこそ大型と表現したい。
■DMA's / ディー・エム・エーズ
オーストラリアはシドニー出身の3ピース。トミー・オーデル(Vo)、ジョニー・トゥック(Gt)、マット・メイソン(SW, Gt,Vo)によって2012年に結成。地元の小レーベル〈I Oh You〉からのシングル・リリースなどを経て〈Infectious〉と契約。2015年11月、日本独自EPをリリースし、その直後初来日している。2016年2月、デビュー・アルバム『ヒルズ・エンド(Hills End)』を発表。
シドニーではオーストラリアのヒップホップがとても人気だよ。あとはEDMみたいなエレクトロニック・ミュージックとかね。(ジョニー・トゥック)
■みなさんは何歳なんですか?
マット・メイソン:平均26ってとこかな。俺は25歳、ジョニーが26歳で、ここにはいないトミー(・オーデル)が27歳だから。
■楽器やバンドをはじめるきっかけになったアルバムやアーティストを教えてください。
マット:俺は13歳のときにソニック・ユースを聴いたのがきっかけでギターを弾きはじめた。友だちのバンドに巻き込まれて、みんなと同じ音楽を聴くようになった。
ジョニー・トゥック:若いころはそこまで音楽が好きじゃなかったんだけど、学校で楽器ひとつをクラリネットとベースの二択からを強制的に選ばせられて、自分はベースを弾くようになった。クラリネットでもよかったかもね(笑)。それでベースをやるようになったら、お父さんがジョニー・ミッチェルの曲を教えてくれて、それを聴いてすごくインスパイアされた。
■シドニーではどんな音楽に人気がありますか? またUKとアメリカを比べるとしたらどちらの影響が強いですか?
マット:オーストラリアはイングランドの子どもみたいなものだけど、アメリカの影響のほうが最近は強いと思う。
ジョニー:シドニーではオーストラリアのヒップホップがとても人気だよ。あとはEDMみたいなエレクトロニック・ミュージックとかね。でもヒップホップのMCがオーストラリアなまりでラップしてると、ちょっと笑っちゃうよね(笑)。アメリカでもイギリスなまりでもなくて、オーストラリアなまりで歌うひとも一部にはいるよ。俺たちが好きなポール・ケリーもそうだし、最近出てきたコートニー・バネットなんかも彼にすごく影響を受けているねと思う。あと、ハードコア・メタルが人気で、他の街のメルボルンにはメルボルンのシーンがあったりする。
オーストラリアのインディ系レーベルで1年以上続いているってすごいことだよ。(マット・メイソン)
■〈アイ・オー・ユー(I Oh You)〉というレーベルについて教えてください。とくにロック専門レーベルというわけではないですよね。シドニーでどのような役割を担っているのでしょうか?
マット:最初はレーベルもマネージャーもいない状態でやっていたんだけど、あるときビデオをとってネットにアップしたら、マネージャーやブッキング・エージェントみたいなひとたちから、連絡が舞い込んでくるようになった。その流れでいまのマネージャーが決まって、彼が〈アイ・オー・ユー〉を教えてくれたんだよね。大きなレーベルじゃないし、所属アーティストもそんなにいないんだけど、オーストラリアのインディ系レーベルで1年以上続いているってすごいことだよ。すごくヘヴィーなバンドや、俺たちに似ているバンド、女の子のポップ・シンガーとも最近契約したよ。音楽的には幅広いし、運営の仕方もすごくうまいからオーストラリアですごく大きな存在になると言われているし、俺たちも彼ならそうなれると思っているよ。
■ニュージーランドについても教えてください。〈フライング・ナン(Flyng Nun)〉やサーフ・シティといったバンドがいて、彼らにはオリジナリティがありますが、同時に90年代の音楽を参照することもあります。ニュージーランドのシーンは馴染み深いものですか?
ジョニー:よく行き来はするよ。実際にいまのライヴ・バンドのギタリストはポップ・ストレンジっていう〈フライング・ナン〉と契約しているバンドのメンバーなんだよね。だから好きなバンドも多いけど、いろんな音楽を聴いているから、とくにニュージーランドのシーンから影響を受けているわけではないかな。
■新しい音楽はどのようにして知りますか?
マット:友だちから教えてもらうことは多いよ。〈アイ・オー・ユー〉のヨハン(Johann Ponniah)がいろいろおすすめしてくれるんだ。あとスポティファイはいいよね。それからいまはライヴ・サーキットにもよく出ているんだけど、知らないバンドのライヴが見られるから、新しい音楽を知るきっかけになっている。
自分たちが楽しめる曲を書いていたらそうなっただけ。だから、昔の音楽に似ているものをやろうとは思ったことはないね。(マット・メイソン)
■いまの音楽と比べると、90年代や80年代の方に好きなバンドは多いですか?
マット:たしかに普段聴く音楽は昔のバンドが多いけど、その理由は自分でもよくわからない。でもだからといって、いまの音楽がよくないとは言いたくないし、いいバンドもたくさん出てきているけど、全体的なテイストは時代とともに変わってしまって、自分たちは昔の方が好きなんだと思う。
■よく80年代や90年代のバンドと比較されることが多いと思いますが、あなたたちはそういった音楽を参照している意識がありますか? また〈ファクトリー〉や〈クリエイション〉といったレーベルに興味がありますか?
マット:90年代の音楽はよく聴くんだけど、ものすごく影響を受けたわけでもなくて、自分たちが楽しめる曲を書いていたらそうなっただけ。だから、昔の音楽に似ているものをやろうとは思ったことはないね。それからトミーはイギリスの音楽を聴くんだけど、曲を作る俺たちはそこまで聴くわけでもない。
■エレクトロニック・ミュージック、たとえばダンス・ミュージックといった他のスタイルにも興味がありますか?
マット:バンドをはじめたときは生ドラムじゃなかったから、ドラムマシーンを使っていたんだけど、いまはリアムっていうものすごくいいドラマーがいるから必要ない。でも将来的にはまた使う可能性もあると思う。自分たちが新しいシンセを買えば、セカンドではそれを使うし、個人的にヒップホップのビートを作ったりもしているから、エレクトロニック・ミュージックの要素を取り入れる可能性はいまでも十分にあるよ。トミーはダンス・ミュージックのファンでいろいろ聴いているしね。
■アルバムの構成はどのように考えたのでしょうか?
マット:本当にシンプルに全体のバランスを考えただけだよ。ビリヤードの玉を三角に並べるときって隣に同じ玉がこないように揃えるけど、そんな感じでラウドな曲と静かな曲が続かないように意識した。
ジョニー:あと全体のダイナミズムは考えたよね。
マット:ストーリー・ラインがあるわけでもないし、曲の流れを決めていたくらいで、そこまで考えて構成したわけでもない。でもEPで作った流れをこのアルバムでも続けたいとは思った。
世の中を変えるような可能性があった頃からやっているひとたちにとっては、そんなこと意味がないように見えるかもしれないけど、いまやっていることにだってちゃんと意味があるんじゃないかな。(マット・メイソン)
■「DMA」とはどのような意味を持つ名前なのでしょうか?
マット:初期のバンド名の省略で、とくに意味はないよ(笑)。自分たちの音楽を表すシンボルみたいなものなんだけど、みんなどんな意味があるのか勘ぐるんだよね。オランダのラジオ局へ行ったときは20個くらい意味の候補があって、ここでは言えないような名前の省略形を考えついたひともいた(笑)。そういうのもおもしろいけど、実際には何の意味もないんだよね。
■ロックという音楽はいまでも多くのバンドを生んでいますが、音楽的なポテンシャルやその可能性は出尽くしたと思うことはありませんか?
マット:新しく出てきて一気に世の中を変えてしまうような音楽が生まれるという点に関しては、ロックはポテンシャルを失っていると感じることはあるけれども、もう既にあるジャンルで自分が好きなことをやることはできるし、それを楽しむことも可能だと思うよ。世の中を変えるような可能性があった頃からやっているひとたちにとっては、そんなこと意味がないように見えるかもしれないけど、いまやっていることにだってちゃんと意味があるんじゃないかな。
■みなさんにとってロックバンドがどのような価値を持ったものなのか教えてください。
マット:ロックバンドをやるってことは、やっていることを楽しむってことだよ。自分たちにとってはね。
