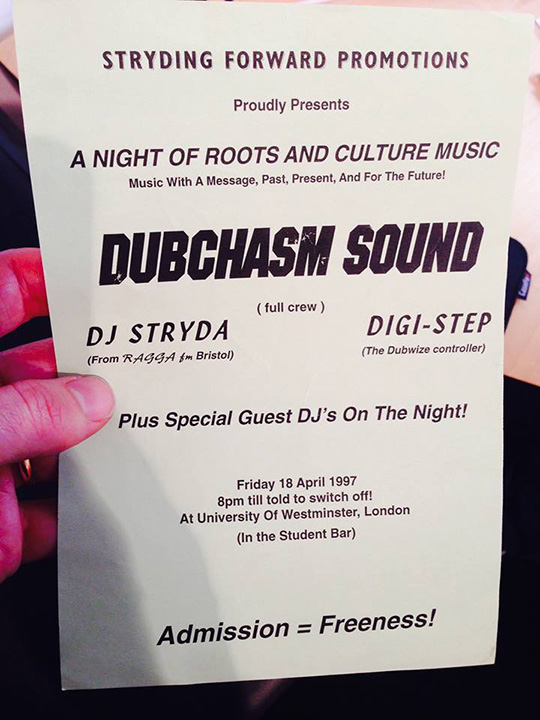彼女の名はクララ・ルイス。1993年生まれ。あのワイヤーのグラハム・ルイスを父とする若きサウンドアーティストである。2014年に〈エディションズ・メゴ〉からファースト・アルバム『Ett』をリリースし、同年、ペダー・マナーフェルトの自主レーベルからEP『Msuic』も発表した。2作とも融解した映画のサウンドトラックのような雰囲気を漂わし、いわば強烈な物語性というより、あらゆる記憶が溶け合った音響空間がじつに魅惑的な作品であった。明晰なグリッドから感覚的な曖昧へ。
そう、彼女の音には、魅力的な「曖昧さ」があるのだ。感覚的な何か、といってもいい。グリッド状の支配から揺らぐ音へ。彼女のドローンは、リズムは、ノイズは、われわれの時間軸を揺らす。アンビエントにしてはビートがあるが、かといってリズムに支配されているわけでもない。環境音と環境音が編集され、それらは明確なリズムを作るまえに、変化を遂げていく。そう、いくつもの音の輪郭線が重なり、どんどん曖昧になるように。しかし、だからこそ音楽の存在感はいっそう強まるのだ。静寂のなか、遠くに聴こえる鼓動のように。もしくは闇夜の響く、微かな物音のように。そのサウンドを一聴し、父であるグラハム・ルイスとブルース・ギルバートによるドームのようだという方もいるだろう。たしかに。だが、ここには新世代ならではの音響感覚が横溢している。それは何か。ひとことでいえば音の「細やかさ」である。デジタル以降の微細なエディット感覚とでもいうべきか。幽玄にして微細。グリッドの格子状の時間支配から自由に逃れていくような繊細な感覚。いや、逃げ去っていく自由、とでもいうべきか。
そのクララ・ルイス、2年ぶりの新作が〈エディションズ・メゴ〉からリリースされた。アルバム名は『トゥ』。あの傑作EP『Msuic』を経由したこの新作において、彼女は彼女の独創的なサウンドをより突き詰めている。断言しよう。これはかなりの傑作だ。〈エディションズ・メゴ〉傘下の〈スペクトラム・スプールス〉からリリースされたセカンド・ウーマン『セカンド・ウーマン』(こちらもポスト・マーク・フェルな超傑作!)、イヴ・ドゥ・メイの新譜、そして本体〈エディションズ・メゴ〉かクリスチャン・フェネスとジム・オルークのデュオ盤、ピタ『ゲット・イン』、コー『ミュージック・ヴォル』などなど本年大充実の〈エディションズ・メゴ〉界隈にあって、現在、もっとも注目すべき新世代のアルバムではないかと思う。ダークな不穏な物語性で補完されていったテン年代初頭的なインダストリアル/テクノも、快楽的なアンビエント/ドローンも、同時代的なポスト・インターネットも、クララ・ルイスの「明るくはないが暗くもない」浮遊する音響/時間感覚によって、(いったん)乗り越えられたのではないか、という大袈裟な断言も思わずしたくなるほどだ。じっさい、本作のサウンドテンマテリアルの選別は、これまで以上に厳選されている。環境音や音響のエディットにはまったく迷いがない。彼女が捕まえた音たちの存在感は、前作を軽く超えている。同時にすべてが曖昧になっていく感覚もやはり健在である。環境音、ノイズ、リズムのなどのサウンド・マテリアルは、反復と非反復の中で、暗闇の中の蝋燭の光のようにユラユラと揺らいでいくのだ。
時間を逆行するような持続音とガソゴソとしたサウンドが、やがて霧の中の叫びのようなノイズに行きつく1曲め“ビュウ”から作品世界に惹きこまれてしまう。続く2曲め“ツウィスト”の乾いた鉄のような音の響き。そこに重なるドローンとリズムの細やかさ。タイトル曲である3曲め“トゥ”のインダストリーでありながら、過剰なダークさに行き着く手前で浮遊するようなコンポジションの見事さ。深海の中で聴く鼓動のようなリズムが響く4曲め“エルス”と5曲め“ウォント”の柔らかさ。霧のようなダーク・アンビエントが折り重なり、そこにシネマティックなヴォイスたちがレイヤーされ、かつて観た映画の記憶と溶け合うような6曲め“ビーミング”の幽玄さ。7曲め“ワンス”の朝霧のような清冽さ。鼓動のような4つ打ちのビートと淡い持続音が鳴り響く8曲め“トライ”と、さらに明確なビートが鳴り響くラスト9曲め“アス”の乾いた明るさ(とくに、アス”には一瞬、事故のような演出が仕組まれているので注目してほしい)。全9曲、全編にわたって融解した映画の音響に身を浸すような感覚がジワジワと展開していくのだ。曖昧で、幽玄で、細やかで、唐突で、慎ましく、しかし大胆に浮遊する淡い音空間。
これだけ充実のアルバムながら、総収録時間は40分に満たない。昨今のアルバムにしては短い収録時間である。しかし聴いている間も、聴き終わった後も、時間感覚が揺らぎ、40分弱というクロノス時間が無化するような感覚が持続していくのだ。環境音とソフトなノイズが誘発する睡眠と覚醒のあいだ? われわれはこのアルバムを聴きはじめると、クララ・ルイスの作り出す時間の中を連れて行かれるのだ。まるでルイス・キャロルの小説のように、である……。そう、奇妙な夢の中へ……。