デトロイト市内を中心から北北西に向かって真っ直ぐ延びているメインストリート、通称ウッドワードアヴェニュー(別称、M-1)、19世紀初頭に建設されたこの主要道路を進んで、歩けば20分ぐらいだったろうか、ウェイン州立大学を越えてさらに進むと、グランドブルーバードが交差する。その左手、つまり西に歩けばモータウン・ミュージアムに到着する。そしてウッドワードからその右手、つまり東側に進めば、サブマージがある。
そのT字を、こんどは大型の書物が綺麗に結びつけている。
昨年、河出から刊行された『コンプリート・モータウン』は、ウッドワードアヴェニューを左に歩かせる。序文は、ウッドワードアヴェニューを歩けば見渡せる(もちろんオススメはしない)。60年代の暴動の傷跡である。この世代の人たちと話すと、「スティーヴィー・ワンダー」とは言わない。眼を細めながら「リル・スティーヴィー・ワンダー」という。リルはリトルの発音。
1998年の時点で、モータウン・ミュージアムの売店ではCDよりもヴァイナル、そしてカセットテープのほうが多かった。いまのようなファッションとしてのカセットテープではない。当時驚いたことのひとつに、日本人が当たり前に思っていたCDプレイヤーなる再生装置は、デトロイトでは当たり前のように所有していないということがあった。PCなんて庶民は持っていないのが当たり前、CDのようなすぐに壊れてしまうような……というか、そもそもCDはリアルではなかった。壊れづらい頑丈なレコードプレイヤー、車にはカセット、だからレコード店にヴァイナル、それが1998年の時点のデトロイトの庶民のスタイルだった。
話が逸れてしまったが、デトロイト(より正確に発語すれば、ディトロイト)においてモータウンは、日々生きるための最高のポップスだった。また60年代を生きた世代にとっては栄光であり、誇りだろう。マイク・バンクスは彼の世代ではおそらく少数かもしれないが、ご存じのようにモータウンを誇りにしている。タイガース・スタジアム移転の際に初代サブマージが市から立ち退きを命ぜられているが、だから彼は新しくサブマージをはじめる場所を、ヒッツヴィルUSAとの対になる住所を選んだのだ。
また、デトロイト・テクノ/ハウスを育てたラジオDJ、ジョージ・クリントンの友人にしてプリンスの友人、エレクトリファイン・モジョの1995年の著作『Mental Machine』は、フレデリック・ダグラス、マルコムX、キング牧師、マーカス・ガーヴェイ、そしてページをめくってマーヴィン・ゲイの言葉ではじまる。(そして同書の最初のページには11歳の黒人の子供が撃たれた事件の新聞の切り貼りがある)


『コンプリート・モータウン』が60年代の栄光の日々であるなら、同書とまったく同じサイズの、洋書で販売されている写真集『313ONELOVE』は、いま現在のデトロイトである。サブタイトルは、「A LOVE AFFAIR WITH ELECTRONIC MUSIC FROM DETROIT」で、すべてマリー・スタッガート(Marie Staggat)という女性写真家が撮影してきたものだ。90年代のele-king読者には、中田久美子さんという写真家が撮影した数々のデトロイトの写真(ジェフ・ミルズのミックスCDのジャケにも使用されているし、ドレクシアの写真は、ネットではいまだ彼女が撮影したものしかない)をよくご存じだろうが、マリー・スタッガートが撮影したデトロイトは、ここ最近のデトロイト。ベルリン在住の彼女がデトロイトに初めて来たのは2010年のことだと序文に書いている。この、ぶ厚く重たい大型写真集のなかにはぼくも知っている顔も何人かいるが、知らない人のほうが多い。みんないい歳になっているけれど(いや、ジェイのような若者もいますよ)、写真はセクシーで、そして静かで、美しい。だいたいいまだこれだけたくさんのDJ、ミュージシャンが活動していることはすごい。170以上のポートレート、街の風景が印刷されているがあまりにも豪華で、貴重な記録だ。
なかには、現在のクラフトワークとホアン・アトキンスとケヴィン・サンダーソンなんていうキラーな1枚もあるし、何枚かの風景写真は、それがたとえデトロイトの写真でなくても、1枚の写真としての力がある。ちなみに、ドイツは、写真印刷に関して世界最高の水準をほこると言われている。『313ONELOVE』はもちろん、ドイツ印刷だ。(また本書はデトロイトの子供たちのサポートを目的としたチャリティー・プロジェクトでもある)
『コンプリート・モータウン』も『313ONELOVE』も奇しくもともに重量ある大型本で、前者は400ページ、後者は320ページ。時代は違えど、2冊ともにデトロイト・ファンには悩ましい本だ。
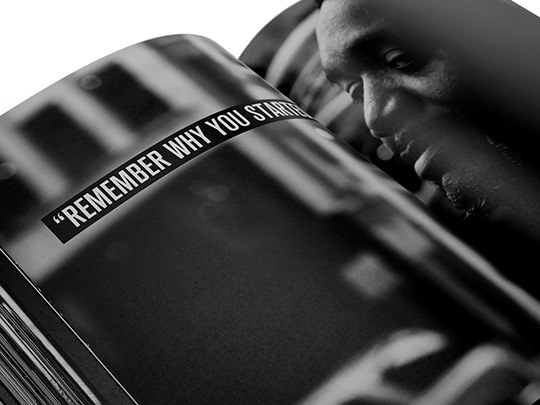
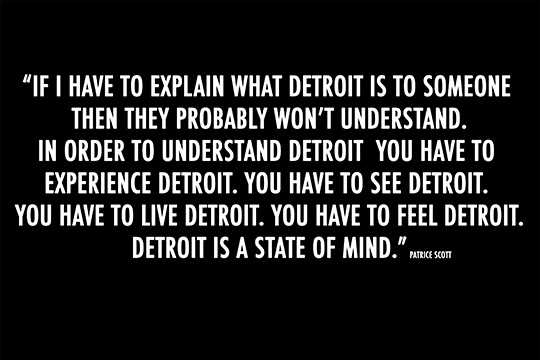
※先日マイク・バンクスが、「90年代はアンダーグラウンドのレーベルがプレス工場に音源を持って行けば、数週間でお金を得られたものだった。しかしヴァイナルが流行の現在は、メジャーのアーティストのプレスを工場が優先するため、アンダーグラウンドのレーベルは半年も待たなければならない。これでアンダーグラウンド・ミュージックはやっていけない。レッド・プラネットはすでに工場に出しているがいまだにプレスはあがってこない。Bandcampを使うかも知れない」(要約)ということを書いたらミスリードされ、「URはこれからBandcampで音源を発表する」という情報が氾濫した。ネット時代のこれは本当に恐い……。それはそうとレッド・プラネット、早く聴きたい。






