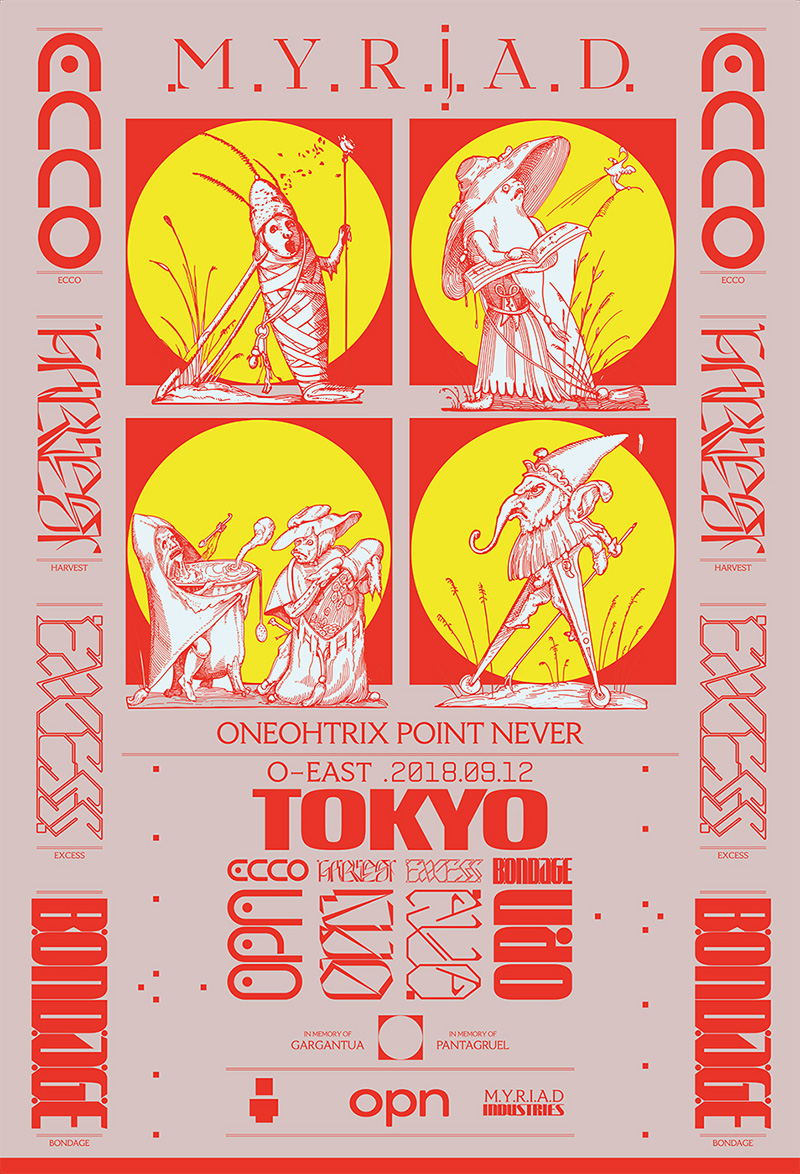アンノウン・モータル・オーケストラを初めてみたのは、2014年のアイスランド・エアウェイズ。たまたま入った小さな映画館で彼らはプレイしていた。100人ぐらいの人がいて、優しいアイスランドの人たちは小さいアジア人に場所をあけてくれ、「椅子に登るとよいよ」とアドバイスまでくれた。そこで見たのは、グレイのスウェットに黒のベースボール・キャップを被ったギター・ヴォーカルと、黒一色のベーシストと、ジンジャー・ベイカーのようなプレイをする、一番目立っていたドラマーの3ピースのサイケデリック・バンドだった。ヒップホップかハードコアにもなり得るリズム・セクションに、カジュアルだが、ファンキーなギター・ラインに圧倒され、すぐに次に行く予定が立ち去れなかった。無理してないのに、なぜか良い。イギリスのバンドだと思っていたが、ニュージーランド出身、ポートランドを拠点とするルーバン・ニルソンを中心とするバンドだった。その後彼らのアルバムを聴き漁っていると、いつの間にか曲をハミングし、歌詞も覚えてしまった。
2015年、ルーバンと妻、そしてガールフレンドの関係をテーマにした新譜『マルチ・ラヴ』をリリースした後は、いたる所で名前を目にするようになった。有名なセントラル・パークのサマー・ステージでもプレイし、”So Good At Being In Trouble”, “Swim and Sleep”, “Ffunny Ffriend” などのシンガロング系のヒット曲から、新曲 “Can’t Keep Checking My Phone” などをミックスしたセットでは、広々としたセントラルパークというロケーションもあり、リラックスしたレイドバックな雰囲気で、誰もが思い思いに楽しんでいた。この、少し奇妙なバンドは、いつのまにか幅広い知名度を獲得していた。

2018年4月、「自分たちが消費するもの、それがどのように影響するか」をテーマにした新譜『セックス・アンド・フード』をリリースした。それと同時に地下鉄のホームから道の看板まで、アルバムの広告で溢れかえり、イヤでも目につくようになった。数週間後にブルックリンの工業地域にある大会場、ブルックリン・スティールで2日間のショーを行った(ソールド・アウト)。ブルックリン・スティールは、2017年にLCDサウンドシステムが再結成&こけら落としをした新しい会場で、インディのトップクラス・バンドがプレイしている。

ステージ・ライトは『マルチ・ラヴ』のカヴァーのようなピンク。楽器以外にレコード・プレイヤーと白いスピーカーが載った長テーブルがあり、白いふわふわのじゅうたんがひいてある。フルワイン・ボトル2本、ウィスキー、テキーラ・ボトルが一本ずつ、キーボード・スタンドの下に準備されていて、まるで誰かの部屋のようである。
バンド・メンバーは、ルーベン、ベースプレイヤー。キーボード・プレイヤー、ドラマーの4人で、ドラマーはルーベンの兄。
ベースボール・キャップ、Tシャツ、ショート・パンツにレギンスのルーベンは全体を通してリラックス・ムード。ガムを噛んでいて、大体歌の出だしをミスる(笑)のだが、その後のクレッシェンド感は流石。高い音も決して外さないし、R&B、ソウルっぽい強弱のある歌い方とメロウなギターの爪弾きにキューンとさせられる。ショルダーバックがけのギターの持ち方もチャーミングだし、「ブルックリン、まだ大丈夫?」と観客を気遣うことも忘れない。

今回は新曲中心に4枚のアルバムから曲を選び、グルーヴィでエフェクトをかけたルーベンのヴォーカルが現実的で病んだテーマをディスコ・ボールのなかでダンスしているように軽やかに響かせていた。メロウになったり、ハードコアになったり、基本はR&Bグルーヴを様々な表情に変えていた。
彼らの曲はインターネットの世のなかに生きていれば起こりえる日常生活を歌っている。いまの時代みんな狂っているし、だからそれをテーマに歌うUMOに共感するのだろう。オーディエンスは20~30代ゲイの男が中心で全部歌詞を覚えている! ぐらいの熱烈さだった。私たちが持つ現代病問題をサラリと気づかせるメロウな友たちがUMO。それを伝染させるのは簡単なことなのだろう。



 現代プロレス入門 注目の選手から初めての観戦まで
現代プロレス入門 注目の選手から初めての観戦まで