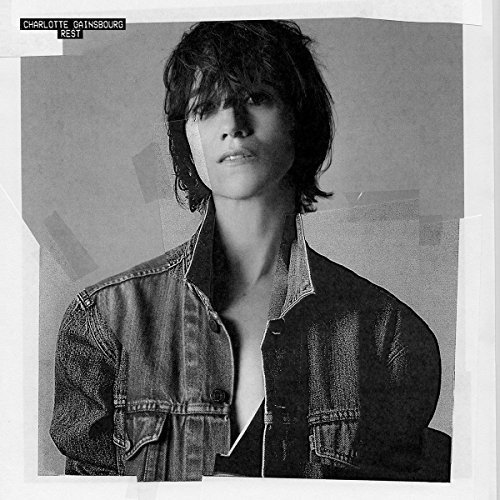 Charlotte Gainsbourg Rest Because Music/ワーナーミュージック・ジャパン |
ラース・フォン・トリアーの映画はさておき歌手としてのシャルロット・ゲンズブールは、共演する男性によってその輪郭は作られてきている。1986年の最初のアルバムは、言わずもがなセルジュ・ゲンズブールが手を貸しているわけだが、音楽家としての活動を再開した『5:55』(2006年)はジャーヴィス・コッカーが、『IRM』(2009年)ではベックが全面協力している。昨年11月にリリースされた4枚目のアルバム『レスト』では、〈エド・バンガー〉の看板、セバスチャンがその立場について、ダフト・パンクのギ・マニュエルとポール・マッカトニーも少しばかり手を貸している。この流れで言えばいままでの彼女のやり方を踏襲しているのだが、しかし『レスト』においては彼女のアイデンティティ(ないしはエゴ)が強烈に露わになっている点で過去作とは異なる。このアルバムの輪郭はセバスチャンではなく彼女である。というのもシャルロット・ゲンズブールは、アルバムのほとんどの曲の作詞を自ら手掛けているのだ。まずはこれが、いままでの彼女のアルバムではなかった。父の書いた言葉を歌い、コッカーやベックの書いた歌を歌ってきた彼女は、『レスト』においてなかば暴露的に個人(とその心情)を歌い上げている。具体的に言えば、2013年の姉であるケイト・バリーの死が引き金になっているのだが、酒瓶と4つ打ちの猥雑なクラブ・カルチャーの片隅で、人生の深い悲しみについて語る内気な女性のことを想像してみてほしい。(ぜひ日本盤の訳詞を読んで欲しい)
それはある意味、エレクトロニック・ミュージックではあるものの、苦しみを公開するという観点では、フレンチ・ポップのお決まりの快楽主義的な回路を切断しているのかもしれない。『5:55』のようなセクシーな作品はたしかに魅力だが、『レスト』での彼女は、しかし悲しみのために新しい声を見つけ、死と向き合い続けた朝方にほのかに立ち上がる力強さのようなものを吹き込んでいる。去る4月に彼女を取材できたので、ここにお届けしよう。

質問:あなたにとって人生とは快楽でありメランコリックであると?
答え:ノン。私は哲学的な座右の銘みたいなものを持たないの。
■うちの雑誌で、およそ18年前、いちどだけ50代半ばのときのあなたのお母さんに取材したことがあります(といってその誌面を見せると嬉しそうに写真に撮る)。セルジュが亡くなって10年近く経った2000年のことでしたが、ジェーン・バーキンは元夫との死別について、まるで物語を読むように話してくれました。ウェールズでオートバイに乗って木っ端微塵になろうとしたけど失敗してくるぶしを痛めただけだったとか、セルジュが死んだあとの留守番電話のメッセージが「生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ。用件をどうぞ」という言葉だったとか。こういうエピソードをたくさん話してくれましたが、奇しくも、『レスト』というアルバムの主題には“死別”があります。
CB:暗いアルバムを作りだかったわけではないけど、死者への想いに取り憑かれているところがあるの。誰でもそうだと思うけど、生きていると近しい人を失うわよね。私の場合は13際のときの祖母の死をはじめ、19歳のときの父、そして最近のいちばん大きなトラウマである姉まで。このアルバムでは父と姉の死を歌っているけれど、生きることについても歌っているわ。でも死というものにこれまでも取り憑かれてきたし、きっとこれからもそうなんだと思う。
■このような重たい主題を扱うことに躊躇はなかったでしょうか?
CB:ひとつ前のアルバム『IRM』でも死について歌ていたわ。もちろんあのアルバムは私が詞を書いたわけではないけれど、死を意識するような事故にあったこともあって自分自身の死について歌っていたの。だからそういう意味では死というのは私のなかにいつでもあるテーマなのかも。
■たとえばエールの音楽を聴いていても、あなたの『5:55』を聴いていても、ジェーン・バーキン&セルジュ・ゲンズブールが創造したなかば快楽的でありながらメランコリーという独特の感覚を覚えます。『レスト』ではそのバランスを崩し、もっとメランコリーのほうに振れているようにも思うのですが、いかがでしょう?
CB:今回のアルバムの音楽的な影響としてあげられるのが、これまでの私の人生で影響を受けてきたホラー映画『ジョーズ』や『シャイニング』、ヒッチコック映画、ジョルジオ・モロダーの映画音楽など。そういったサウンドをセバスチャンのなかに感じたの。その彼の強いエネルギーを持ったサウンドがあったからこそ、メランコリックで痛みを伴う歌詞を乗せられた部分もある。例えば“Les Oxalis”はサウンドと歌詞の内容が結びつかないと思う。そういうサウンドと歌詞が相反するようなものを作りたかったの。
作っているときには自分では分析できないけれど、いまになって思うのは音楽とヴォーカル、つまり歌詞を繋ぐような役目をストリングスが負っているのかも。これまでのアルバム『5:55』から今回の『レスト』までストリングスはとても重要なの。レコーディングではいつも最後に入れていたんだけど、まるでひとりの登場人物のような役割を負っていて、それがメランコリックな要素を強めたかもしれないわね。
■つまり、あなたにとって人生とは快楽でありメランコリックであると?
CB:ノン。私は哲学的な座右の銘みたいなものを持つことや、確信を持って何かをいうのが好きではないのよ。私は人生をあまり俯瞰的に見ないで生きることが好きなの。
■フランス人はみんな哲学的なのかと思ってました(笑)。
CB:そういう意味ではフランス人じゃないかもね(笑)。
■すでに“Les Oxalis”のAlan Braxe(ダフト・パンク一派のプロデューサー)によるリミックスがヒットしてますが、“Deadly Valentine”もソウルワックスがリミックスを手掛けてますし、クラブ・ミュージックとの繋がりを感じます、あなた個人にはクラブ・ミュージックへの想いはあるのでしょうか?
CB:クラブ・ミュージックは好きじゃないの。エレクトロニック・ミュージックには興味はあるけど、まずその定義がわからないの。私にとってはベックだってときにはエレクトロニック・ミュージックを使うときがあるし、逆にセバスチャンはコンピュータで作っていないストリングスも使うし。エールのときもそうだった。まあ、エールはエレクトロニック・ミュージックというよりエレクトロニックなヴァイブを持った音楽という感じね。エレクトロニック・ミュージックという要素に惹かれるものはあるけれど、ダンス・ミュージックを自分から聴くことはないわ。
■では、音楽面ではレーベル、〈ビコーズ〉のアドヴァイスはあったんですか?
CB:方向的にエレクトロニック・ミュージックをアルバムに取り入れたかったのは私の意向で、〈ビコーズ〉はいろいろなアーティストの音を聞かせてくれたの。
私はトランスの要素のある音楽がずっと好きだった。エマヌエーレ・クリアレーゼ監督のイタリア映画の『Nuovomondo』という映画に出演したとき、シチリアでのお話なんだけど、とてもトライバルな音楽が使われているの。それがとても気に入った理由はきっとトランス感のあったからだと思う。
■クラブに行きますか?
CB:ノン(笑)。フランスで出かけるのはちょっと難しかったのよね。クラブに行くのは楽しむためだと思うんけど、顔がバレてしまうと楽しめないでしょ。いまNYでならできるけど、もうこの歳じゃね(笑)。
(※取材時46歳)
■NYで暮らしていてパリが懐かしくなるのはどんなときでしょう?
CB:パリにいる親しい人たちね。イヴァンはNYによく来てくれるけど、パリに住んでるし。イヴァンのお母さんも恋しいし、友だちや家族ね。あとはちょっと恥ずかしいけど食べ物(笑)。パリの生活自体はまだ恋しいと思わないの。パリの生活を忘れたいわけじゃないのよ。でももう少しNYにいて、パリを新たに発見できる気持ちになったら帰るわ。
■最後に、お父さんから言われた言葉でいま覚えているのを教えてください。
CB:ふー(フランス的ため息)、たくさんありすぎて……。いまの会話から思い出したこと、パリの生活や人に顔を知られてしまっていることとかについて言うわ。思春期の頃、人からしょっちゅうサインを頼まれることにうんざりしていた時期があって、そのときに父から言われたのが「ある日もう誰もお前にサインを求めなくなったら後悔するんだから、いまの状況をありがたく思いなさい」と言われたの(笑)。
しかしながら、クラブ的なサウンドトラックは、傷心のアルバムに生命についての主張をうながしているようだ。近しい人の死を商売にする人はこの世界にいる。シャルロット・ゲンズブールは、そんなせこい真似をしなかった。悲しみを公開することで、錯乱でも追憶でもない、彼女はそれ以上の強いものを作った。『レスト』は世界中で賞賛されている。(了)
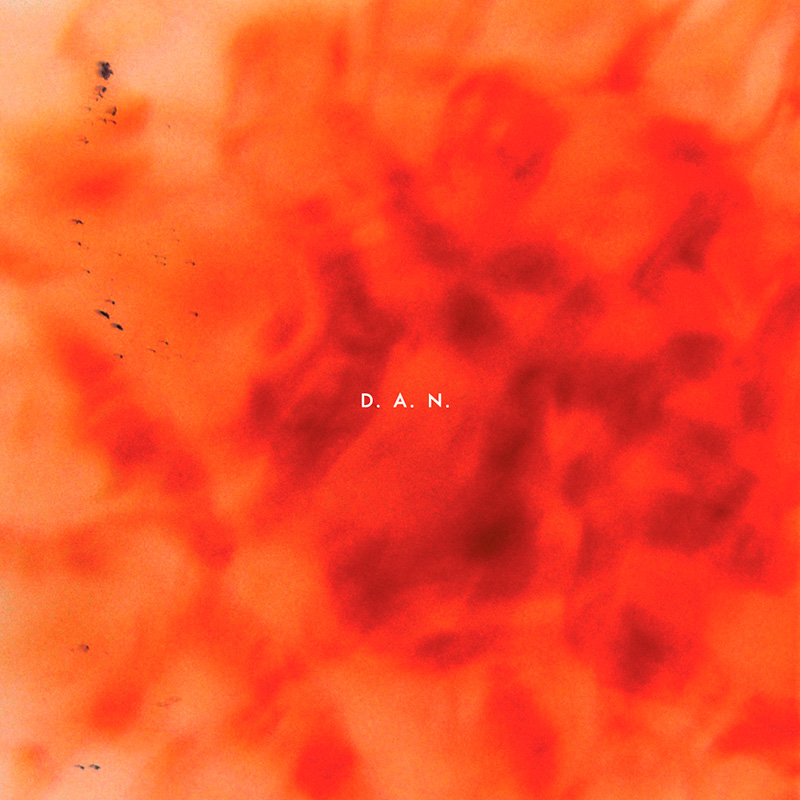
 リスボンで開催されている音楽見本市、MIL(
リスボンで開催されている音楽見本市、MIL(






