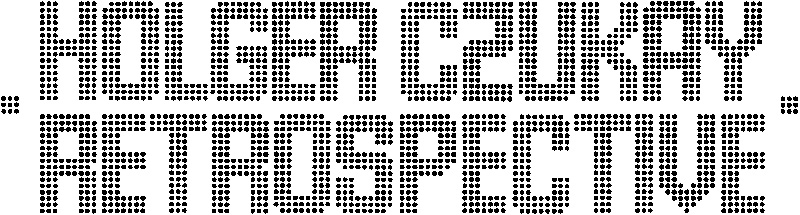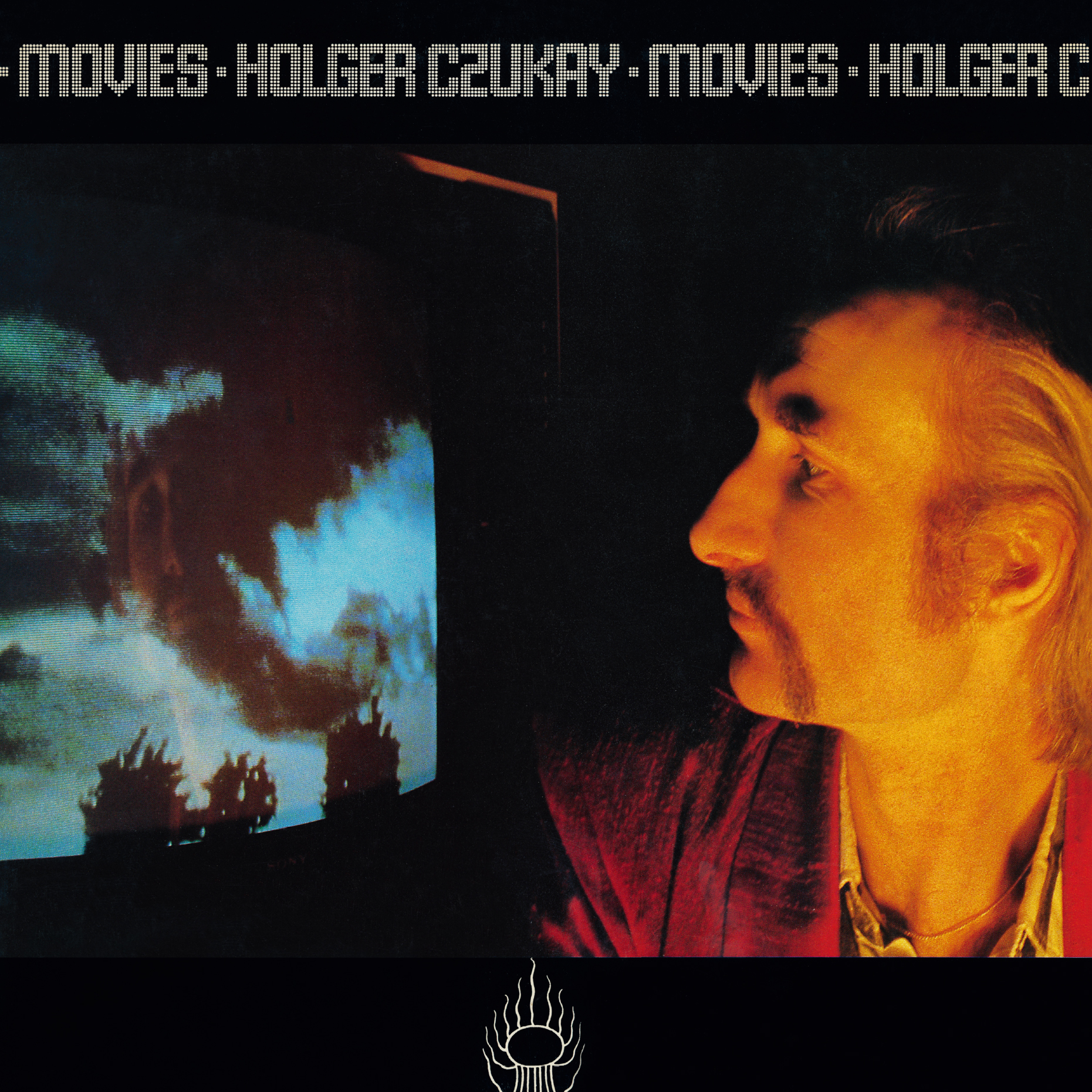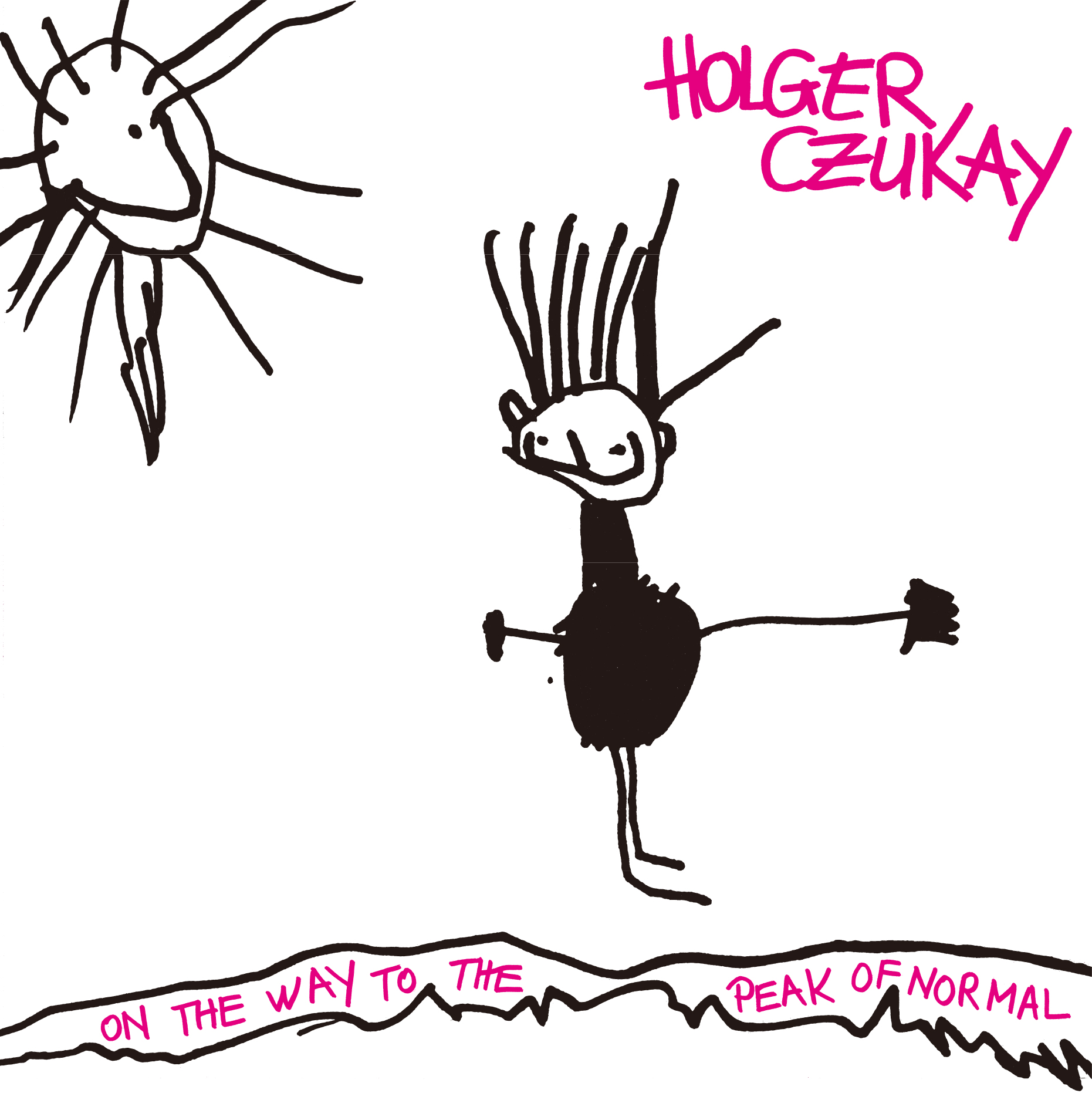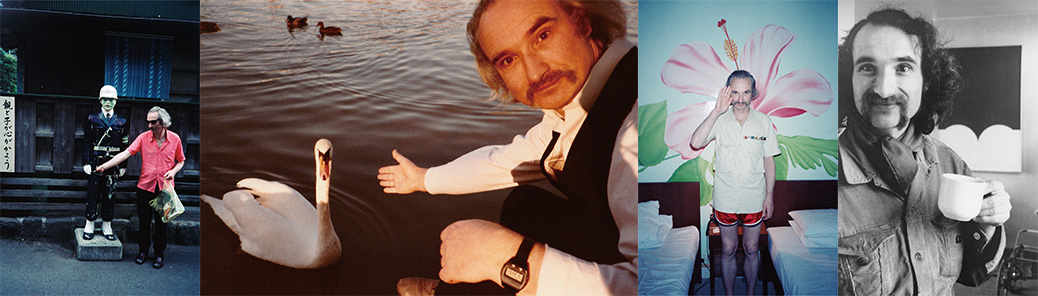パソコン音楽クラブ、情報デスクVIRTUALではないしMacintosh Plusでもない。新手のヴェイパーウェイヴではない。前期YMOや80年代エレ・ポップの現代解釈版。ダフト・パンクからの影響もあるんじゃないのかな。しかし、不思議と懐古主義的には聴こえない。トーフビーツから教えてもらった関西の若手有力株。ようやくCD買ったでぇ~。
はじまりはベッドルーム。ストリートにありがちな人間関係の面倒くさいしがらみはない。オンライン文化の暗闇(アイロニー、シニシズム、憎しみ、悪意)だってスイッチをオフにすればいいだけ。お、可愛い犬もいるんだね。
パソコン音楽クラブはトーフビーツのフォロワーではない。水曜日のカンパネラの強力なライヴァルというわけでもない。そもそもこの音楽は力んでいない。気取ってはいるが、まわりを意識しているようには思えない。“OLDNEWTOWN”は、トーフビーツの“NEWTOWN”へのアンサーではないのだろう。同じメランコリーでも出し方がまったく違う。前者は、軽い。後者が重たいわけではないのだけれど、パソコン音楽クラブのメランコリーはさっと通り過ぎていく、跡形も残さずに。あ、いま通った? という感じで、ちょっと清々しい。
ジャケットのアートワークは、「水星」へのオマージュにも受け取れるし、ジェントリフィケーション時代の申し子である自らを表しているのかもしれない。記憶だけがカラフルな、この殺伐としながらも恍惚な風景。好むと好まざるとに関わらず、ぼくたちが暮らしているお馴染みの世界。ザ・スリッツの“NEWTOWN”から39年、NEWTOWNというNEWではない街。
ぼくもRX17持ってました。リアルタイムで。ダサい音なんだよね、これが。とはいえ、パソコン音楽クラブは「昨日」の音ではない。だからといって「明日」の音でもない。いくぶん感傷的だが、これは「現在」の音なのだ。“Inner Blue”で歌われるようにそれは「終わらない夜」、つまり、ただただ陶酔したいという願い。“Beyond”という最後の曲は夢の時間のはじまりだ。そう、チルウェイヴであれチル&Bであれ、ミニマルであれアンビエントであれ、アンダーグラウンドであれオーヴァーグラウンドであれ、これこそ今日のポップの奔流に通底するもの。パソコン音楽クラブ、今後の活躍が楽しみ。