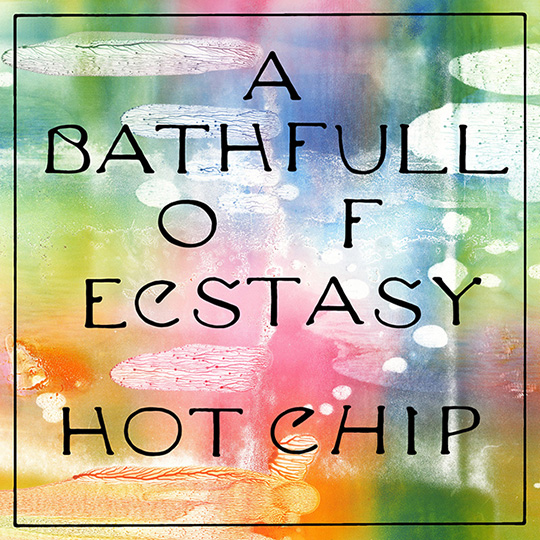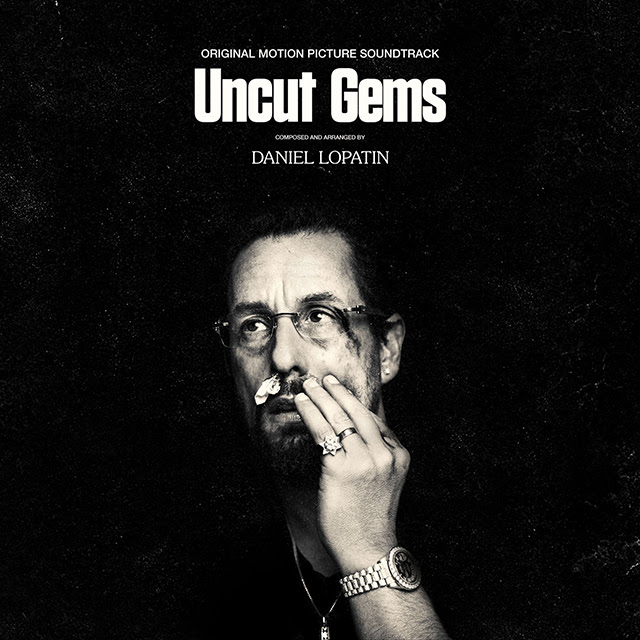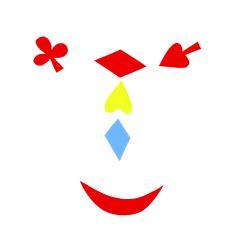いま日本で50周年といえば細野晴臣である。だが、もうひとつ重要な50周年が今年はある。アート・アンサンブル・オブ・シカゴ(AEC)だ。こちらは1965年に“シカゴのゲットーから生まれた”AACM(Association for the Advancement of Creative Musicians)なる非営利の音楽団体が元になっている。ポップスを作るつもりなどはなっからなかった連中だから、労苦をともなう50年だっただろう。AECは自らの音楽をジャズとも括らず、このように定義した。「古代から未来への偉大なるブラック・ミュージック」
AACMの創設メンバーのひとりマラカイ・フェイヴァース(b)、ジョセフ・ジャーマン(as)、ロスコー・ミッチェル(as, d)、そしてレスター・ボウイ(tp)が加わりAECの骨格は出来上がった。スティーヴ・レイシーのドラマーだったドン・モイエ(d)が参加し、その強力なクィンテットが形成されるのは70年代に入ってからだが、AECは結成された1969年から1971年までのフランス滞在の3年間において、じつに10枚以上のアルバムを制作している。『People In Sorrow(悲しみの人びと)』や『Message To Our Folks』、『Great Black Music』などは初期の傑作に数えられているが、そのなかの1枚には、日本でAECといえばこれと言わんばかりのブリジット・フォンテーヌの『ラジオのように』がある。間章がライナーを書いたことでも知られる名盤で、ぼくもご多分に漏れずにこのアルバムによってAECと出会ったひとりだったりする。
間章はそのライナーで、AECの開放的な音楽性の本質に迫ろうとはしているが、むしろフォンテーヌの歌う「世界は寒い」というフレーズに強く惹きつけられている。こうした言葉には、たしかに間章が愛したヴェルヴェット・アンダーグラウンドとの親和性がある。
しかしながらAECは寒くはなかった。彼らはワールド・ミュージック(いまで言うならグローバル・ビート)の先駆的存在のひとつだったという評価があるように、同時代の何人かのフリー・ジャズ・ミュージシャンもそうだったが、片っ端から西洋文明以外の領域を調査した。70年代後半のアルバムではどレゲエを演っているほどに、柔軟な姿勢をもって極めてディアスポリックな「未来へのブラック・ミュージック」を志向してきたと言える。
レスター・ボウイは1999年に他界し、マラカイ・フェイヴァースは2004年に、ジョセフ・ジャーマンは今年の1月に亡くなっている。ロスコー・ミッチェルとドン・モイエはまだ生きている。そして3人の死者に捧げられた、彼らの50周年を祝うアルバム・タイトルは『We Are on the Edge』、私たちは切羽詰まっている、私たちはギリギリである、いずれにせよネガティヴな状況にいるというニュアンスの言葉だが、ここではあえてこう訳そう、私たちはどん底だ。
この最新作における「未来へのブラック・ミュージック」はしかし、クラシカルな響きではじまる。場面によっては、まるでオペラである。静かな、ある意味もったいぶったはじまりであり、じょじょにAECが姿を露わにしていく。それはそして、アルバムのゲスト、ムーア・マザーの登場によって場面を急変させる。
過去の白人アーティストの名を現在の黒人アーティストへの賞賛として使うのは、文章書きとしてあまりに芸がないと後ろめたいが、人に伝える手段としてあえて使わせていただけるなら、これはまるで黒いパティ・スミス、黒い“ピス・ファクトリー”だ。彼女の声それ自体だけで、ひとつの世界が生まれる。
2枚組のうちの1枚はスタジオ・セッションで、もう1枚がライヴ盤となる。後者ではベースと管楽器が絡み合う“Tutankhamun(ツタンカーメン)”がひとつのクライマックスとして演奏されている。また,ライヴの最後には“リアルな暴動のようだ”とも評された1973年の『Bap-Tizum』から“Odwalla”に乗せてメンバーが紹介される。
AECのカオスは、アーケストラのようなぐわっと高揚に向かうそれではない。よりパーカッシヴで、豊かなポリリズムをもって、それぞれが柔らかく揉みほぐされるように型にはまらず拡張する。サックスの神妙な響きから打楽器の陽気で快活なセッションへと、カリンバやフルートの音色を活かした美しく平穏な展開、あるいは目の覚めるようなカオスへと、『We Are on the Edge』は集大成的にさまざまなな表情を見せている。老練な演奏と若々しい実験が素晴らしいバランスを保っており、じっくり音楽を聴く上での魅力が充分につまった力作だ。
もっともぼくは日本の〈DIW〉からリリースされている数多くの作品まで押さえているほど熱心なAECリスナーではないので、ロスコー・ミッチェルとドン・モイエによるこの新しいAECと伝説的なクインテットとの詳細な比較はできない。今年の春先にリリースされたこの2枚組を夏前にゲットした理由も(Spotifyでは聴けない、悪いけど)、ぶっちゃけたところ、ムーア・マザーが参加しているからである。AECの演奏に彼女のリーディングがどのように絡むのか、その興味がぼくの耳をAECに向かわせたと言っていい。
まっとうなAECファンからしたら邪道だろうが、その判断は間違ってはいなかった。このアルバムの表題曲、作中もっとも燃えたぎる曲“We Are on the Edge”において、ムーア・マザーの炎のような声はこんな言葉を繰り返す。
We are on the edge(私たちはどん底だ)
for victory(勝利のために)
これはラップでもリーディングでもない。アジテーションである。ネガティヴをわずか一瞬にしてポジティヴに変換してしまう。ぼくにとって彼女のこの言葉は「世界は寒い」よりも100倍強く、気持ちを熱くさせる。そして、決して平易ではない道を歩んできたAECの50周年に、これほど相応しい言葉もないだろう。