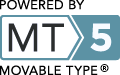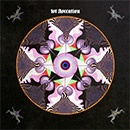 VARIOUS ARTISTS 1ST ASCENSION GURUZ |
こんにちは。
レーベルGURUZ主宰のDJ Doppelgengerです。
僕がDUBSTEPのDJをやりはじめたのが約5年前。それからいまを比べれば、随分と認知は広がったように思えます。当初はBack To ChillとDrum&Bass sessionsぐらいしかDUBSTEPのパーティがなかったですし、DJの数もまだ少なかったのを思い出します。僕は幸いなことにそのなかでプレイをすることができ、多くの国内、そして海外アーティストとも共演することができました。
そのなかで記憶に新しいのがDJ PINCH。Techtonicといういまや有名なUK DUBSTEPレーベルを主宰する彼との交流は、すごく貴重な時間でしたね。彼は僕と同じ境遇、クリエイターでもありDJでもありレーベルマネージメントもおこなっており、れでいて、あれだけ多くの作品を輩出し世界で認知させてきた経緯など、いろいろ聞かせてもらいました。
一緒に居て思い浮かんだ言葉は「情熱」。
例えば、1枚のレコードやCDを出すことにも、実に多くの労力と時間、そして覚悟が必要です。ひとつひとつ、その思いが詰まったレコードたち。PINCHのレコードバッグはすべてDubplate(テストプレスの白盤。なかにはアンリリースも多々!)だったのが衝撃でした。
それと針がSHUREの44Gを使ってたんですよね。何でこんな針圧も弱く、ハウリングしやすい針を使うのか? Dubplateは通常のレコードよりも溝が浅いので、ortofon等の針圧の強いものだと溝がえぐれてすぐに盤がダメになってしまうからなんです。なもんで、リハも相当入念に行ってましたね。これだけ自分の曲からリリース、そしてDJセットまで、すべて究極を追求し、それをスピーカーを通じて聞き手に届けている......本場のDUBSTEP、そのひとりの姿勢を魅せて貰いました。
これは例として、海外DUBSTEPアーティスト全般、皆オリジナル思考がすごく強くあって。それって音楽云々以前のとても大切な部分であり、人と違う自分だけのものを追求するっていう大切な行為だと思います。
DUBSTEPが海外でこれだけ大きくなった背景には、このオリジナル思考を随所に感じます。まだそれほど歴史は短いにしても、この枝分かれ具合にしろ、スタイルにしろ、細分化の早さがそう物語ってますね。
聞いたことあるかもしれませんが、Digital Mystiksが主宰するパーティDMZはあまりに尋常じゃないBASSを出すので、入口で耳栓を配るそうです。イカレてますよね(笑)。けど、そこでのサウンドは相当やばいらしく、平気で数千人のクラウドが集まるとか。やっぱヨーロッパのクラブシーンの個性、そしてレヴェルの高さは凄いですね。
やってる人は解ると思いますが、オリジナル志向って度胸や覚悟も必要なんですよね。自分や仲間の、それも未マスタリングのアンリリースの曲って音質もバラバラだし、鳴りも同じくマチマチですし。スタイルも何処にも属さない、誰も知っちゃいないような曲ですし。けど、それをプレイすることってすごく大事なんですよね。

たとえ未完なものでもいいんです。いまを全力で追及した結果を1曲に封入し、それを現場でかけるって行為が大切なんじゃないかと。
最初の頃は、なかなか良い結果は出ないでしょう。それだけ、自分の曲でフロアを納得させる事って簡単じゃないですから。けど、作り続け、かけては直し入れてを繰り返し、そしてプレイし続ければやがて「この曲好きです!」っていうのが出てきます。そこでようやく長年かけ続けてきた意味が出てくるわけであって。そして、「自分の音」ってものが確立され、DJとしても一脱出来るんじゃないかと。全体がそうなっていけば、それぞれの個性がもっと出て、パーティの盛り上がり方も変わってくると思うんです。自分らの曲でアンセムが出来たりして、やがて独自の文化が生まれると思うんですよね。
日本のDUBSTEPは、徐々にそれが浸透していっているように感じられます。今年僕は1st Album『Paradigm Shift』をリリースして、国内ツアーで全19カ所を回ってきたんですが、随所でそういったアーティストと会うことが出来て。人数は少ないながらも、オリジナル曲で勝負してるDJもいました。
そして、そんな仲間に声をかけて集まった曲をすべてリリースしようと思い、年末の12/22にコンピレーションアルバム『1st Ascension』をリリースすることになりました。
今回最年少だと17歳と20歳の兄弟デュオSeimei&Taimei。僕が知り合った頃、兄のSeimei君は19歳だったんで、クラブに入れないっていう話で(笑)。そして弟のTaimei君はまだクラブ行けないそうです......。
しかし、曲聴いてびっくりですよ。若い柔軟な脳みそってここまで吸収しちゃうんだなーと。DUBSTEPが好きだという気持ちが全面に出ていて、それが随所で感じられて、見ててこっちも刺激になりますね。深夜クラブには行けないけど、彼らなりにやれる場を探して、早い時間帯のU20のパーティに出演したり、自分でUstream配信したり。この情熱は見習うべきですね。是非彼らの曲、聴いてみると良いですよ。そして彼らを例に、若いクラブミュージック好きな人、いますぐ曲作りにチャレンジしてみるといいでしょう。着手は早いに越したことが無いし、若い方が覚えるもの速いです。時間も余裕あるだろうし。
話戻しますね。
あと、栃木にB Lines DelightというDUBSTEPクルーがいます。
彼らも凄いですね。何が凄いって、メンバーほぼ全員が曲作ってて、それを現場でしっかりかけてるんですよね。東京以外でここまで成熟したクルーは彼らぐらいしか現状居ないと思います。それぞれやばい曲作りますし、なかには海外ラジオや有名DJがかけている曲も保有してます。
コンピにも彼らのなかからSivariderとRyoichi Ueno、Negatinが参加してます。とくにRyoichi Uenoの曲「Brain」はラッパーの志人君の声がサンプリングされてて彼の諭すような声と重厚なビートが合わさって、いままでに無いDUBSTEPサウンドが出来たと思います。志人君に聞かせたところ、快くOKしてくれて。嬉しかったです。この場を借りてお礼申し上げます。ありがとう!
それに加え、今回は沖縄出身のアーティストが3組います。DUBGYMNER、Helktram、CITY1。それぞれ別々に知り合ったんですけどね。昔から何故か、沖縄の人とは縁が深いです。それってやっぱ土地柄というか、沖縄って全般的に個性が強い場所だと思うんですよね。
それが音楽にもやはり反映されてて、3人とも全然違った個性ながらも、かっこいい曲作ってきますよ。DUBGYMNERのMONDOってやつはDJもやってて、BUD RYUKYUっていうDUBSTEPパーティも主宰してます。僕もツアーで足を運ばせて貰ったんですが、凄く良いパーティでしたよ。沖縄DUBSTEPシーンの先駆け的なパーティでしたね。
あと、これはBack To Chillを通じて知り合った100mado、DEAPA、DUBTRO。とくに100mado「Indian Zombie」はかれこれ2年前ぐらいからプレイしており、それを自分のレーベルからリリース出来て、すごくうれしいですね。僕のDJを何回か聴いた事のある人は、絶対に耳にされてる曲だと思います。DUBTROもじわじわと頭角を現してきてますしね。
これは制作秘話? ってほどでも無いんですが、マスタリングはこれまたBack To ChillクルーのENA君にやってもらいました。やはり同じジャンルに精通しているだけあって、実に理想的な音に仕上げてくれました。
彼と作業した1日も、いろんな意味で面白かったですね。エンジニアワーク見てるって面白いですよ。制作とはまた違う視点で。使ってるケーブルやら機材、電源やら、スピーカーとか吸音材とかの話もして。かなりマニアックな話でした。ついでにですが、ENA君のアルバムが来年7even Recordingsからリリースされます。これもかなり凄い内容で、国内外で話題になる事でしょう。
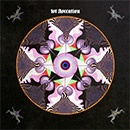 VARIOUS ARTISTS 1ST ASCENSION GURUZ |
こんな感じで、自分を取り巻くDUBSTEPアーティストの皆さんと協力して、今回こういったリリースが出来る訳でありまして、なんとも感慨深い気持ちですね。しかも「国内初の日本人DUBSTEPコンピレーション」という名目まで! ありそうで無かったんですよね。これが。そして12月22日。マヤ暦が終焉を迎えるこの日を敢えてリリース日とさせて頂きました。タイトルも『1st Ascension』。これは、JAPANESE DUBSTEP新時代の幕開けという裏テーマが隠されています。
これを皮切りにレーベルGURUZからどんどん日本人DUBSTEPをリリースしていく予定です。何故か? DUBSTEPが好きだからですよ。
これ、PINCHにも同じ質問してこう返ってきたんですよね。シンプルかつ響いた言葉、僕も使わせてもらいます。

もっといろいろなスタイルがあって良いと思うし、さまざまな解釈があってこそ、DUBSTEPだと思います。それこそ、いま大きく言えば二極化してるブロステップとディープ系ダブステップ、それぞれが盛り上がるって大事なことですよ。
いまのシーンを見てると、ブロステップの流行が目に入りますね。こないだのスクリレックス公演なんか3000人SOLD OUTらしいですね。僕は正直、ブロステップに関しては好きではないです。聴く努力はしましたけど、サウンド然り、どうも馴染めないです。けど、それはそれでそういったシーンが出来たという現実は受け止めてますし、彼らの功績もまた凄いですね。ただ、いまそれがアメリカで流行ってる、だから正しい、というわけではないと思います。日本人はとくにメディア操作に操られ過ぎです。
シーンが虚空の肥大をして過度のビジネス傾向に陥り、魂の無い音楽が蔓延して、結果、何も残らないっていうね。それではならんのです。
僕はDUBSTEPを大事にしたいんですよね。だからこそ、そこに魂、そしてメッセージが宿っているかどうか? ってことにはサウンドクオリティと同等に気持ちの比重を置いてますね。
これは自分に対する課題でもあると思ってます。いまの僕視点でのDUBSTEPが果たして正しい道なのかどうか、これは時間が経たないと解らないじゃないですか。それだし、僕が提唱しているDUBSTEPでもきちんとビジネス出来る環境を作らなきゃいけないって思うんです。
これはUK DUBSTEPシーンを見ていてもそう。例えば先に言ったPINCHやMALAみたいなアーティストが、 いまの日本のシーンで成功出来るとは到底思えない。しかし、彼らは向こうじゃトップアーティストであって、音楽で生活を賄っているわけで。
これを日本でやろうって「無理だ」って言葉が大多数ですけど、そう言って動かないでいては何も変わらない。畑は耕さないと、芽はいつまでも出てきませんから。僕はDUBSTEPとこれからも長く付き合っていきたいです。そのためには少しずつ、ひとりずつ納得、共感してもらって土壌を作って行く事が今の自分がすべき事だと思ってます。サウンドクオリティの向上は当然ながら、それとともにリスナーの聴くレヴェルも向上させていく必要性は感じてますね。
だから、僕はレーベルを立ち上げたというのもありますし。GURUZからもっといろいろな日本で暮らしているDUBSTEPのクリエイターを世に知らせていきたいなと。そして、もっとこの国で起こっているドープなDUBSTEPのシーンの実情を国内外共に伝えていきたいんですよね。これだけ世界で大きな波となってるDUBSTEP、だけどそれって日本の場合、大衆には僕らがやってるDUBSTEPというのが現状あまり見えてないと思うんですよ。先に言ったブロステップ然り、表面的なものでストップしちゃってる。
これを広めるって容易では無いですよ。一人対全国ですから。しかし、不毛だからこそチャレンジしたいっていうね。あきらめたらそれまで。前進すれば道は拓ける。これは音楽云々以前の、人としての生きる姿勢の選択であって。地道に時間かけてでも、道を拓く覚悟ですよ。
パーティにおいては、東京だとDrum&Bass sessionsやBack To Chillなんか、音響も素晴らしいですし、日本最高峰のDUBSTEPが聴ける現場と言えるでしょう。最新の国内外のDubplateもガンガンかかってるし、DUBSTEPのいまを知るにはうってつけのパーティと言えますね。まだ行ったことの無い方、そして若いDUBSTEP好きな方は是非、足を運んでみるといいでしょう。大箱でしか体感出来ない極太BASSを体全身で感じれば、DUBSTEP本来の素晴らしさを知ることでしょう。
最後に、12月22日のリリース日に、僕の地元大宮でリリースパーティも開催します。僕がいま思う新鋭アーティストを揃えた奇跡の一晩となることでしょう。サポートは地元のDUBSTEPクルーMAMMOTH DUBがしてくれてて。彼らとは共に3年、地元でパーティを開催してきて。大宮は年々DUBSTEPが育っていってる感をビシビシ感じますね。オリジナル曲もどんどん増えてるし、この日はかなりの数のオリジナル曲がスピンされるでしょう。都内からも近いですし、是非皆さん遊びに来て下さい。
JAPANESE DUBSTEPの新たな一面をここで垣間見ることでしょう。
東京でのリリパは2月を予定。詳細をお楽しみに! ほか、地方公演もいろいろ入ってきてます。スケジュールは以下の通り。各地の皆さん、またお会いしましょう!
それでは、DUBSTEP FOR LIFEでした。
PEACE.
DJ Doppelgenger -
DJ SCHEDULE
12/1 Version @ CACTUS (乃木坂)
12/8 Drum&Bass Sessions @ UNIT (代官山)
12/22 [ 1st Ascension ] Release Party @ 444quad (大宮)
12/31 Countdown Party @ 444quad (大宮)
1/13 TBA @ Circus (大阪)
1/20 Dubstep Area @ The Dark Room (福岡)
1/25 TBA @ TBA (長野)
2/1 TBA @ TBA (東京)
2/23 TBA @ Bangkok (タイ)
3/2 TBA @ Rajishan (静岡)
 |
MALA / MALA in Cuba (Album)
今年一番好きなアルバム。 |
|---|---|
 |
GOTH TRAD / NEW EPOCH (Album)
言わずもがな、GOTH TRADのニューアルバム。 |
 |
Swindle / Do The Jazz (12inch)
DEEP MEDIからの新たな刺客Swindle。 |
 |
ENA / Analysis Code (12inch)
これまた、何処にも属さない全くオリジナルスタイルを提唱した問題作。 |
 |
Shackleton / Fablic 55 (MIX)
ミックスながらも全曲オリジナルでの編成。 |
 |
KRYPTIC MINDS / THE DIVIDE (12inch)
ミニマルテクノ+ダブステップ。 |
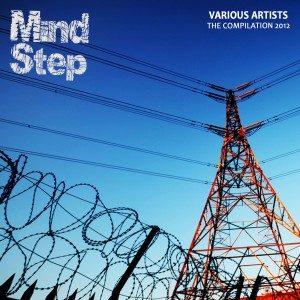 |
DUBTRO / MIND HUMAN (Compilation)
Back To ChillクルーDUBTROのニューチューン。
|
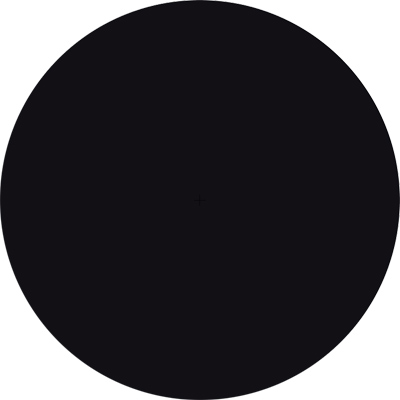 |
KILLAWATT & THELEM / kaba (12inch)
KILLAWATT好きですね。他もだいたい好きです。 |
 |
V.A / 1st Ascension (Compilation)
僕が見てきた日本のダブステップが此処に。 |
 |
DJ Doppelgenger / Paradigm Shift (Album)
今年リリースした僕の1stアルバム。 |
DJ Doppelgenger ( GURUZ )

15歳からDJキャリアをスタート、そして2008年よりDJ Doppelgenger名義でDubstep DJとしての活動を開始する。世界各国を放浪した経験を基に、ワールド感漂う独自の音楽観をDubstepというフィールドで表現している。東京を代表するBass Music Party『Drum&Bass Sessions』@代官山UNITのレジデンツとして出演。そして、2009年より地元埼玉でMAMMOTH DUBを開催し、多くのアーティストを招聘している。これまでにrudiments、subenoana等のレーベルよりmix、trackをリリース。