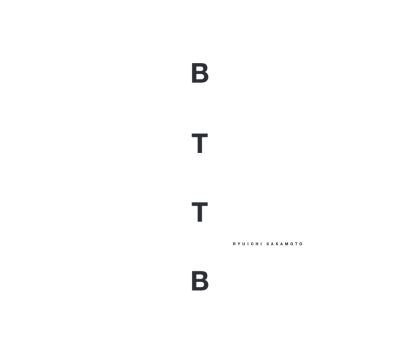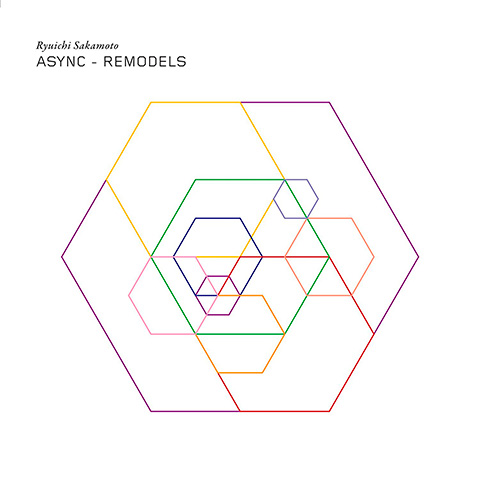MOST READ
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- 橋元優歩
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- Jlin - Akoma | ジェイリン
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- 『成功したオタク』 -
- interview with agraph その“グラフ”は、ミニマル・ミュージックをひらいていく | アグラフ、牛尾憲輔、電気グルーヴ
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- ソルトバーン -
Home > Reviews > Album Reviews > 坂本龍一- 12

三田格
どうしてそうなったのか覚えていないのだけれど、大学生だった僕と小山登美夫は、その日、新宿アルタのステージにいた。映画『戦場のメリークリスマス』のプロモーション・イヴェントで、僕たちは「戦メリ」に夢中な若者たちという設定でステージ上の椅子に座っていた。2人ともまだ映画は観ていなくて、要するにサクラだった。ステージには30人ぐらいが3列に分けて座らされ、僕らから5席ほど右に坂本さんがいた。前口上のようなものが長くて、僕らは多少、緊張していたけれど、坂本さんはとっくに飽きてしまったらしく、やたらと目でこちらに合図を送ってくる。最初はなんだかわからなかった。坂本さんは視線をこっちに向けながらひっきりなしに眉毛を上下させている。もちろん面識はない。初対面というか、ただ近くにいるだけである。『戦場のメリークリスマス』という映画の意義が語られ続けているなか、坂本さんの眉毛は上下し続ける。僕も小山も吹き出すのを我慢して下を向いてこらえていた。しばらくしてからまた坂本さんの方をちらっと見ると、まだやっている。あのしつこさには参った。ようやくイヴェントが本題に入って坂本さんが若者たちの質問に答える時間が始まり、僕らは解放された(イヴェントの後で僕は坂本さんに “君に胸キュン。” を勝手にリミックスしたテープを渡し、それが坂本さんの番組でオン・エアされたのに、その時の放送を聞き逃してしまい、そのテープが放送されたことを教えてくれたのは砂原良徳だった。さすが「カルトQ」)。10年ぐらい前に坂本さんがドミューンに出演した際、打ち上げでたまたま隣の席になった僕はアルタのイヴェントのことを訊いてみた。なぜ僕らを笑わせようとしたのかと。坂本さんは爆笑して、「覚えていない! あの頃のことはなんにも覚えてない!」と実に楽しそうだった。「忙しすぎてなんにも覚えてないんだよ!」。そして、日本酒の中瓶を取り出すと「これは貴重なお酒で、美味しいから飲んでみて」という。僕はお酒が飲めないというか、お酒を飲むと偏頭痛が大爆発してしまうので、「いや、飲めないんです」と言うと、「いいから飲んで」と引き下がらない。「いやいやいや」と僕がいうと「いいから、いいから」とお酒を注ぎ始める。あのしつこさは変わっていなかった。僕は手塚治虫の酒や赤塚不二夫の酒を飲み、赤瀬川原平やビートたけしのお酒も飲んだ。忌野清志郎のビールもちょくちょく口にしている。ここで坂本龍一の酒だけ飲まないのもなんだよなと思い、頭痛のことは忘れてちょっと飲んでみた。基本的に飲まないので味のことはわからないけれど、それはとても美味しく、なんというか滑らか~で不思議な世界に出会ったような気がした。「お、美味しいですね」。「そうだろー」。坂本さんの眉毛がまた上がった。
かつてスタジオボイスで坂本さんにインタヴューした際、坂本さんに「アンビエント・ミュージックはつくったことがない」と断言されてしまった。それもかなりきっぱりと。そんな無茶なと思ったけれど、それ以上追求しても眉毛が動くだけだと思って僕はあっさりと引き下がった。なので、『12』を前にして1曲目からアンビエント……と書き出すわけにもいかず、昨年から延々と悩み続け、晦日も正月も雑煮も初荷も通り過ぎ、そうか、この滑らかで不思議な感触はアンビエントではなく、お酒を飲んで気持ちよくなった状態、そう、酩酊音楽と呼べばいいのではないかと思いついた。日本酒の中瓶を持ち歩く坂本龍一の音楽を説明するのにぴったりのカテゴライズではないだろうか。『Gohatto』も『Elephantism』も『Comica』も『Alexei and the Spring』も『Love Is The Devil』もみな酩酊音楽の系譜に属している。坂本音楽の謎がこれでひとつ整理できた。ふー。それでは『12』を紐解いていこう。ここで安心して筆を置くと原稿料がもらえなくなる。『12』は何か遠くのことに想いを馳せているような酩酊音楽で幕を開ける。ブライアン・イーノ “An Ending (Ascent)” を思わせる悲しいドローン。いきなりエモーショナルで、生と死の境界を見つめるかのように透き通った諦観が冒頭から胸を撃つ。喜怒哀楽のどこにも寄せなかった『Comica』とはまったく違う。続く “20211130” からはアルヴァ・ノトとのコラボ・シリーズと同趣向で、少しばかり希望が増大し、ハロルド・バッド『The Room』がニューエイジぎりぎりと評されたように曲の表面を弱々しさが覆いつつ、背後に隠されたテンションが印象派の尊厳を仰ぎ見る。初ソロが『宇宙~人類の夢と希望~』だし、『Esperanto』や『The Fantasy Of Light & Life』の一部を聴くと坂本龍一は気質的にはニューエイジで、それは手塚治虫の影響であり、生まれ変わったら人類学者になりたいと言っていたことからもわかる通り人類全体に対する慈愛や興味が音楽から滲み出している。かといって一時期の知識人たちのようにオウム真理教や統一教会といった個別のニューエイジに引きずられなかったのはやはり知性や教養といった歯止めが効いていたからだろう。ひっきりなしに聞こえるのは坂本の息遣いだろうか。肩の上にジョン・ケージが乗っかっている。酩酊音楽というより、だんだんと瞑想音楽になってきたかと思いきや、息遣いがフィジカルな場面を想像させることで、完全にはスピってしまわない効果を上げている。続く “20211201” もアルヴァ・ノトとのコラボ・シリーズをさらにゆっくりと展開する感じか。余韻が主役。そして、病気をすると肺が弱り、呼吸が短くなるはずなのに、同じように息遣いを混ぜながら8分を超える長い曲に挑んだ “20220123” 。『Comica』にはなかった微妙な透明感が宿り、それがまた儚さを無限に醸し出している。教授、やっぱりこれはアンビエント・ミュージッ……いえ、なんでもありません。
5曲目で『12』は一転する。重苦しく波打つシンセサイザーは “Carrying Glass(『The Revenant』)” から深刻さを割引いて、ムルコフや伊福部昭よりも92年のレイヴ・ヒット、ユーフォリア “Mercurial” に途中から被さるシンセサイザーをそのまま取り出した感もあり、当然のことながらブリープのループやトライバル・パーカッションは入ってこない。延々とシンセサイザーがとぐろを巻き、アシッドな汗が滲み出る。このグラマラスな厚み。ゴシックを気取った酩酊モードにもほどがある。 “20220207” で再び前半のタッチに戻り、不完全に反復されるミニマルの断片に18番ともいえるピアノの高音でアクセントをつけたイーノ “1/1” のオマージュか。 “戦場のメリークリスマス” で果たした西洋と東洋のクラッシュは継続され、とんでもなく想像力を広げさせてもらうと、上海華夏民族楽団が “ウルトラQのメイン・テーマ” をチョップしてスクリュードさせた大衆音楽の供養にも聞こえる。ジャズ系のダン・ニコルズがスマホだけで録音したという『Mattering And Meaning』にも一脈で通じるものがあり、とくに “Yeh Yeh” は近しい発想に思える。 “20220214” はただ静かにしていたいという気分が反映されているのか、前述の “An Ending (Ascent)” から歓びを差し引き、PIL “Radio 4” をスローダウンさせたようなシンセ・ドローン。喜びや楽しさにもエネルギーは必要だから、その手前で立ち止まり、ただここに「ある」というだけで恩寵があるという価値観がここには刻印されている。酩酊音楽はここまでとなり、以後はピアノ曲に移り、唯一、ヘンデルのカバーらしき副題がつけられた “20220302 - sarabande” は輪郭のはっきりとしたピアノが前景化している(音響のせいなのか、知識のない僕にはラフマニノフ “嬰ハ短調” に聞こえてしまう)。演奏はかなりゆっくりで、アンチ・ドラッグ系の人力スクリュード・プレイというか。続く3曲も短いピアノ・ソロで、『BTTB』でいえば “intermezzo” の系統。坂本龍一のピアノは( “aqua” みたいなものでなければ)どこを切ってもラヴェル(やサティ)が出てくるような気がする(知識が乏しいのでよくわからない)。悲しいともそれを押し殺しているとも、あるいは、メランコリーというのとも違って、前頭葉のどこかにある感情なんだろうけど、ひとまずは言語化できない楽しみができたと強がっておこう。80年代は坂本龍一のつくった音楽が時代の音になったけれど、90年代はハウスやブレイクビーツなど他人がつくったフォーマットを自分流に聞かせるだけで別に坂本龍一じゃなくてもいいんじゃないかと思う曲が多かった。それが『御法度』や『BTTB』で自分の音を取り戻し、坂本龍一でなければならないピアノ曲に昇華させ、それがここにも4曲並んでいる。クロージング・トラックは静かな鐘の音。これまでも時々鳴らされていた音だけれど、こうも続くとドビュッシーがパリ万博で聞いたガムランの音がそのまま坂本龍一のオブセッションとなっていまだに響き続けているかのようである。
昨年は『Thriller』の40周年記念盤で初めてマイケル・ジャクソン版 “Behind the Mask” を聴いた。想像以上にこれがよかった。アレンジも原曲に忠実で、ポップスとしての完成度は高かった。原盤権を手放すことがカヴァーの条件だったそうで、坂本龍一がそれに応じなかったために『Thriller』への収録は見送られたという。もしも収録されていたらポップ・ミュージックの全体像はいまと少しは異なるものになっていたのだろうか。そうでもないのだろうか。坂本さん本人が “Behind the Mask” のリフはキンクス “You Really Got Me” と同じだったことに後で気がついたと話していて、当時、 “You Really Got Me” のカヴァーで売れまくりだったエディ・ヴァン・ヘイレンが『Thriller』でギターを弾いていたということはなかなかの符合だったとも思う。いずれにしろ坂本龍一はその翌年、 “戦場のメリークリスマス” がベルトルッチの耳にとまって世界に躍り出ることになり、日本では「世界の坂本」として奇妙な立ち位置を占めるようになる。80年代は北野武や村上春樹、川久保玲や安藤忠雄など「世界」に実力を認めさせた日本の文化人を多く輩出していて、なぜか「世界の川久保」とか「世界の村上」とは言われず、その後も「世界の宮崎」とか「世界の草間」もなく、ただ1人坂本龍一だけが「世界」呼ばわりされていた。日本で評価されるということは評価してくれた人の奴隷になると同義で、やがてはその権力を禅譲されるという習慣(家父長制度)がどこまでも染み渡り、若い才能が自由に活動する土壌が整っているとはとても言えないのだけれど、「世界の坂本」がそうした制度の外側で自由に動けたことは大いなる利点であると同時にいったん村の外に出てしまうと日本の村社会には戻りにくいという難点もあった。坂本龍一はそのまま藤田嗣治やオノ・ヨーコのように海外の才能になりきることもありだったという気がするけれど、坂本は日本を愛していると何度も発言し、00年代以降は政治的発言を有効にするために、無意識かもしれないけれど、ダウンタウンとの芸者ガールズだったり、労務者のコスプレをしてTVに出るなど、いわば「足立区のたけし 世界の北野」というパロディと同じ要領で日本の村社会に底辺から出入りする方法を見つけていく(日本人はスゴい才能にひれ伏す気持ちが薄く、どういうわけか素人芸を好むので、圧倒的な才能を実のところは煙たがっていて、自分たちよりも下に見える振る舞いをすれば「親しみやすい」といって受け入れるところが多分にある)。日本の村社会にはそのような抜け道があることを坂本龍一は教えてくれ、そして、そうまでして坂本が日本の才能であり続けてくれたことに感謝すべきではないかと思う。『12』というアルバムを僕は「日本の坂本」として聴きたい。(1月7日記)
ALBUM REVIEWS
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain
- Lost Souls Of Saturn - Reality


 DOMMUNE
DOMMUNE