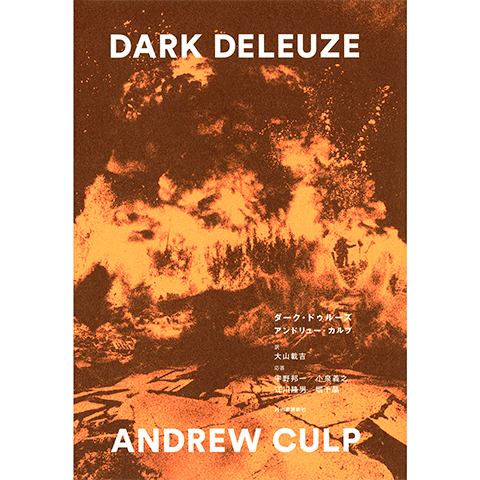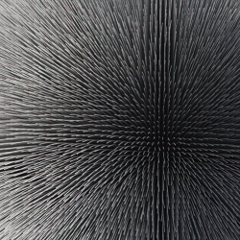MOST READ
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- interview with Toru Hashimoto 選曲家人生30年、山あり谷ありの来し方を振り返る | ──橋本徹、インタヴュー
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- Jlin - Akoma | ジェイリン
- 『成功したオタク』 -
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 | 対談:ジェフ・ミルズ × 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- みんなのきもち ――アンビエントに特化したデイタイム・レイヴ〈Sommer Edition Vol.3〉が年始に開催
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- Beyoncé - Renaissance
Home > Reviews > Album Reviews > Demdike Stare- Passion
2014年に野田努に同行して、代官山ユニットの楽屋でデムダイク・ステアのマイルズ・ウィテカーとショーン・キャンティ、それからアンディ・ストットにインタヴューをしたことがある。ウィテカーとストットによるユニット、ミリー・アンド・アンドレアがアルバム『Drop The Vowel』を〈Modern Love〉から出した直後のことだ。地元のマンチェスター近郊に住む寡黙なストットと日本の文系青年に似た雰囲気のキャンティ(同世代の近郷出身者にはジェイムズ・リーランド・カービーとサム・シャックルトンがいる。若手世代にはシンクロ、インディゴ、エイカーなど)、当時ベルリンに居を構えていた快活なウィテカーと過ごしたあの時間をいまもたまに思い出す(このインタヴューは「ele-king vol.14 」に収録)。ウィテカーはあの頃、ニーチェ『善悪の彼岸』に頭を悩ませていて、インタヴュー後(ファンだというDJノブがデムダイクのふたりに会いに来ていた)、ステージ脇ではイタリアの現代音楽家エギスト・マッチ(1928-1992)について熱く語ってくれた。
あれから四年過ぎ、デムダイクのふたりは実に多くのことに挑戦してきた。2013年から2015年までに続けていた12インチの「Testpressing」シリーズでは、ジャングルからUKガラージ、さらにはグライムにいたるUKダンス史を俯瞰し、これまでのデムダイク・ステアのイメージを覆すような楽曲フォームを発表してきた。
ここには機材における大きな変化もある。それまでハードウェア+エイブルトン+ロジックで進めていた作業環境から、エレクトロン社製のサンプラー、オクタトラックをメインに据えたセットに切り替えたのだ。2014年のライヴでも「これ、使うの難しいんだよね」と言いながら(この発言は謙遜ではなく、オクタトラックは操作を覚えるのが本当に難しい機材である。サンプラーというよりも、オシレーター(音を発生させる機能)が搭載されていないエイブルトンのようなDAWのハードウェア版、くらいに捉えてもらってよい。マニュアルも難しい!)、ウィテカーはステージ上でオクタトラックを手に、キャンティがセレクトするレコードをサンプリングし、華麗にさばいていた。
これは非常に重要な転回である。シーケンサーを動かしながら(つまり、楽曲を止めることなく)リアルタイムでサンプリング/加工ができるこの機材から実に多くのフレーズが生まれている。ジャングルはリピートを極小細分化し(“Null Results”)、ソウルⅡソウルは裁断機にかけられガラージになり(“Rathe”)、象の嘶きがグライム空間から突発してくる(“Procrastination”)。
もちろん彼らは以前にも『Voices of Dust』(2010)で“Hashshashin Chant”という最高のトライバル・チューンを生み出している。しかしオクタトラック導入後の「Testpressing」以前以後では律動的直感性の強度は異なるものになっている。彼らが愛すジャズ・ミュージシャンたちが、猛練習と苦楽を重ねて新たな音を獲得していくように、デムダイク・ステアのマシン・ミュージックは自身のOSを書き換えていったのだ。
この変化への欲求が結実したのが2016年の大傑作『Wonderland』である。この年の9月、僕はロンドンへ渡った。その翌月の7日、ショーディッチのクラブ、ヴィレッジ・アンダーグラウンドで、彼らの〈DDS〉レーベルのパーティが開かれ、迷わず現場に向かった(DJのリル・モフォも来ていた)。ジョン・K、ステファン・オマリー、ミカチュー、イキイノックス、そしてデムダイク・ステア。そうそうたるメンツである。この年、同レーベルからは、2018年に『Devotion』を生み出したティルザがフィーチャーされたミカチューのEP「Taz And May Vids」が、そしてなんといっても10年代の名盤であるイキイノックスのアルバム『Bird Sound Power』がリリースされている。
「最近はジャズ、とくにマル・ウォルドロン、それからイキイノックスの影響でダンスホールを聴いてるよ」、とフロアにいたウィテカーは教えてくれた。この時点で彼は長年拠点にしていたベルリンを離れ、故郷のマンチェスターに戻っていた(この時のウィテカーの読書リストはドゥルーズ『スピノザ:実践の哲学』と、アントニオ・ダマシオ『感じる脳:情動と感情の脳科学 よみがえるスピノザ(原題:Looking for Spinoza)』である)。
『Wonderland』の主軸にもキャンティとの2台のオクタトラックのセッションがあり、それがイキイノックスを経由したダンスホールの影響下で、なんとも形容しがたい奇妙なビートを醸成した。昨年、英国のNTSラジオに出演した坂本龍一が同アルバムからセレクトした“Animal Style”が好例である(坂本はストットの“Tell Me Anything”もかけていた)。揺らぎつつ、芯のあるポリリズム。怯えながらもトラップをすり抜ける小鹿のように、どこまでも逃げていく華麗なシンセ。どこか笑える、頭をかち割るリムショット。
筒井康隆はかつて山下洋輔のボレロを「脱臼したボレロ」と形容したが、その言葉がここにもしっくりくる。正常ではなく、不良な異常さを。停滞ではなくダイナミックな恒常性を。そして、シリアスさもいいけど、常に一握りのユーモアを。『Wonderland』のマシン・ミュージックは、多くのしがらみにまみれたジャンルの道徳をフォローするのではなく、それを脱臼し、前例のない自らの倫理の構築を呼びかけてくる(これは先のドゥルーズのスピノザ理解と重なる点でもある)。
2017年にはフランスの音楽研究グループであるIna Grmの要請によって実現した、同団体が所有するアーカイヴ音源と音響システム、アクースモニウムを用いたライヴ・レコーディング盤『Cosmogony』を、さらに2018年に入ってからはローマの伝説的即興音楽集団「Gruppo di Imorivvisazione Nuova Cosonanza」(同グループにはかつて前述のエギスト・マッチが参加していた。伏線はあのステージ脇にもあった!)とのコラボレーション作『The Feed-Back Loop』をカセットで発表。「Testpressing」/『Wonderland』のセットアップで、即興/ミュージック・コンクレートを追求していく力作だ。
そして2018年10月25日に〈Modern Love〉から届いたのが、9曲入りの新作『Passion』である(紹介媒体によってアルバムかEPで分類が異なっているが、ここではアルバムとして扱う)。この段階で僕が最後にデムダイクのふたりに会ったのは、2018年6月15日、イースト・ロンドンにあるクラブ、オヴァル・スペースで行われた、デムダイク・ステア、アイコニカ、リー・ギャンブル、アンディ・ストットらがブッキングされたイベント時である。この日、〈DDS〉からシンイチ・アトべの新作『Heat』が出ることをウィテカーからチラッと教えてもらっていたのだが、デムダイクのリリースについては何も言っていなかったので、今回のリリースは驚きだった(この時、ウィテカーはマーク・フィッシャー『資本主義リアリズム』、ダン・ハンコックス『インナー・シティ・プレッシャー:グライムの物語』を読んでいた。最近興味が社会学系にシフトした、そうである)。
このライヴは『Passion』の布石だった。ライヴのヴィジュアルを担当したデザイナー/ヴィジュアル・アーティストのマイケル・イングランドが今作のジャケットのデザインを担当している(彼のクライアントはBBCからソニー、ミュージシャンにはオーテカやボーラなどがいる)。濃い紅色に塗られた女性がこちらを睨んでいる。現代におけるソフトウェアの使用方法を探求し問い直すという手法から、今回のヴィジュアルは生まれたという。
現実にポッカリ空いた非現実の落とし穴を拡大することを、イングランドは得意とする。あの日のライヴのヴィジュアルに現れたイメージたち:カナダのナイアガラの滝で自撮りをするレズビアンのカップル、蝋人形館、ニューヨークのヴォーグ・ダンス、ジャパニーズ・ホラーな白衣を纏った女性の暗黒舞踏的身体移動etc。これまでは、映画好きであるキャンティが選んだホラー映画などからの抜粋がライヴで使われていたが、今回、彼らの視覚を司るのはフィクションとノン・フィクションの境界を揺らぐ何かであり、異様な人間性たちである。それがこのジャケットや、リリース時に公開された以下の本作のトレーラーにも表れている(この映像はライヴでも使われていたと思う)。
Demdike Stare - Passion / Trailer by Michael England
ここでアルバムを再生する。鋭く青光りするシンセが鈍いディストーションの渦巻きへと降下する “New Fakes”から、さらに粒の細かい歪みが覆ったメランコリアが徐々に出現し、強いトレモロ・エフェクトを経由しビートが緩やかにはじまる“At It Again”へと流れる冒頭。極小のキックの上に、制御不能気味に響くジャングルのビートが、速度の低下と上昇を経て次第に開花する。複雑性と単純性の両方が相互を包摂していき、その両方がノイズの海へと沈む。
“Spitting Brass”では、時にウォブルする緩やかな周波数グラフを描くシンセが、幽霊のごとき声と重なり低速ガラージを奏でる。続く“Caps Have Gone”でビート・パターンはよりプリミティヴになり、FMシンセの流星が降り注ぎつつもダンスホールのビートが前進を続ける。
ここでレコードが2枚目へと移行する。1曲目、“Know Where to Start”はBPM142、グライムである。「どこからはじめるか知っている」とタイトルが語るこの3分33秒から、初期のワイリーとディジー・ラスカルが想起され、タワーブロックから送信される海賊ラジオのトランスミッションのようにパーカッションは断片的に連打される。「Testpressing」でのUKダンス・ミュージックの地図を書き換える旅は、ここでも新たな作図方を展開していく(タイトルを「Nowhere to Start/スタート地点などない」と言葉遊び的に読みかえれば、何かの起源/パイオニアを特権化しない姿勢も読み取れる?)。
C面2曲目、「お前ら人間はファックだ」(“You People Are Fucked”)という挑発のもと、人間は何か別の存在に中指を立てられる。ふたつの冷徹なヴォイスが右と左のチャンネルで相互に会話のやり取りをし、異様なポジティヴさを放つウォンキーなベースラインが、BPM120代中頃の相対的低速感でユーモラスに響く。続く“Pile Up”は同様のタイム・スピードながらも、「間」を強調し、2017年のミュージック・コンクレート修行で養ったサウンド・マテリア構築センスが惜しみなく披露されている。
レコードは裏面へ。タイトルは“Cracked”(「ひび割れた」の意)。針が飛んだかと思わせるオープン・ハットの機能不全ビートに、深いリヴァーヴ(おそらくクナスのエクダール・モイスチャライザー〔Ekdahl Moisturizer〕を使用。バネを使ったナチュナルにエグい効果を生む。ウィテカーが長年愛用)が優雅にマシン・ヴォイスを包む。そして入り込む低音。このベースラインは間違いなく、ガラージの暗黒面におけるクラシック、ダブル99 の“Rip Groove”(04年)に由来するものである。書道のようにフォームを崩されたそれが、一服の絵画のようにトラックを貫き、モノクロームを基本色に、ドットのようなシンセの突出が細部から全体を書き換える。ビートが消えると、広大な花畑のごときドローン・ビートがこれまでの展開がジョークだったかのように広がり(曲名“Dilation”は「拡張」の意)、今作は幕を閉じる。
ここで見てきたように、そしてプレス・リリースが語るように、『Passion』はUKダンス・スタイルをなぞった「アヴァンギャルドと、重低音のためにデザインされ洗練された、機能的なクラブ兵器の奇妙な構成物」である。たしかに前作『Wonderland』でイキイノックスのダンスホールを経由し到着した不思議の国から、上記のカセットのリリースで研ぎ澄まされた前衛センスを武器に、「Testpressing」シリーズで試みたUKダンス史へと再潜入していくのが今作である(だからこのレヴューは、ここ数年の出来事を詳述しなければならなかった)。
だが、同時にそれ以上の何かがここにあるような気がしてならない———。去る3月、僕はマンチェスターのクラブ、スープ・キッチンで毎年開かれている、デムダイク・ステアのオールナイトDJセットを聞きに行った。そこで流れていたのは、ミュータント・ダンスホールであり、レヴォン・ヴィンセントの“Double Jointed Sex Freak”(09年)だった。彼らは新旧ジャンル問わずにしっかりと丁寧にレコードを聴き、映画を見て、本を読む勉強家&リスナー・タイプの作り手であり続けていた。
いわゆる「型にはまらない系」の人々は、自身のスタイルを「オンリー・ワン」の名の下に特権化しがちだが、デムダイク・ステアにはそれがなく、偉そうに見えない。彼らは謙虚なリスナーであることと、過激な作り手であることを自由に行き来する。そこには主体性を保ちながら、対象と並列に寄り添う姿勢がある(DJセットでは影響元である対象をセレクトし、フロアから聴かれることによって、自身も対象と同化している)。自身の曲中でありながら、“Rip Groove”が見え隠れするように、デムダイク・ステアの奇妙なリアリズムは、常に何か別のものに開らきつつ生成する……(この感覚は、清水高志が『実在への殺到』(水声社、2017年)で論じているミシェル・セールの概念「準-客体」に近いものがあるかもしれない)。
かつて阿木譲は放射性物質がバラまかれた「3.11以後の我々の生きる時代意識が最もリアルに反映されたもの」としてデムダイク・ステアのホラーに満ちた音楽を論じた。同意である。今回、僕は違った角度からそこに新たな意味を加えたい。政治的にも、文化的にも、あるいは環境的にも何かを特権化してしまいがちなダークエイジの価値観に、デムダイク・ステアの音楽はノーを突きつける。だから僕は彼らに吸い寄せられてしまう。スピノザもニーチェもフィッシャーも、似たようなことを書いてきた。
『Passion』は作品単体として聴いても素晴らしいが、上記で述べたように、前作たちとの関連でも面白みを増す。なので、単体でベスト・ランキングの上位に入る大傑作、というわけではないかもしれない。だが、UKダンス系にフォーカスをした初のアルバムという意味では初の挑戦であるし、何よりビートと音質が文句なしにかっこいい(今回から彼らは24ビット・リリース、つまりハイレゾにも挑戦している)。そして、ここに表出している奇妙な姿勢は、絶妙な彼ら「らしさ」である。ダークな内容に対して、少し皮肉っぽく響く「情熱」というタイトルも面白い。
次にウィテカーは何を読んでいるのか考えながら(ミシェル・セールだったら面白い)、僕はしばらくこの「情熱」に耳を傾けようと思う。きっと今作は年末のフロアでも最高に鳴る1枚になるだろう。
髙橋勇人
ALBUM REVIEWS
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain
- Lost Souls Of Saturn - Reality


 DOMMUNE
DOMMUNE