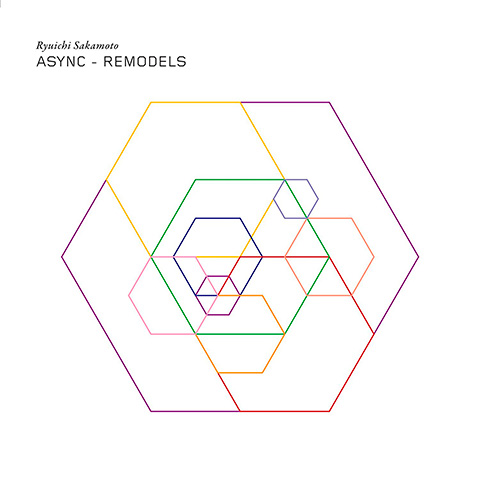MOST READ
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- Jlin - Akoma | ジェイリン
- Jeff Mills ——ジェフ・ミルズと戸川純が共演、コズミック・オペラ『THE TRIP』公演決定
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- Jeff Mills × Jun Togawa ──ジェフ・ミルズと戸川純によるコラボ曲がリリース
- R.I.P. Amp Fiddler 追悼:アンプ・フィドラー
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Rafael Toral - Spectral Evolution | ラファエル・トラル
Home > Reviews > Album Reviews > 坂本龍一- async
この『async』は、2009年の『アウト・オブ・ノイズ』以来、8年ぶりのソロ・アルバムというだけでなく、坂本龍一という、ひとりの音楽家が40数年の年月をかけて行き着いた未踏の音楽に思えた。(個々人、さまざまな意見があるかもしれないが客観的にみても)最高傑作といってもいいかもしれない。“戦メリ”に代表されるリリカルな旋律を生み出す作曲家としてではなく、未知の音を追求する「ノイズ音楽家、坂本龍一」の集大成である。
ノイズといっても轟音ではない。静謐で、空間的で、澄み切ったマテリアル=音の連鎖である。沈黙をも取り込んだ響きとリズム。微かな和声と旋律。それらの「音」たちのズレを孕んだ、しかし自由で豊穣な配置=コンポジション。まさに坂本の自伝の書名『音楽は自由にする』ということの実践に思えてならない。そもそも「async=アシンク」とは「非同期」、つまり同調しないという意味である。同調しない自由。美しく、豊かで、しかし微かな音の美を生み出すための強い意志。音への飽くなき好奇心。未知の音楽への探求心。そして世間という抑圧への抵抗と闘争心。いまの日本で、このような静謐で美しいアルバムをリリースすることじたい、「パンク」な行為ではないか。
その「自由」のために、『async』にはまったく妥協がない。コマーシャリズムもタイアップの要素も希薄だ。メロディやビートなどポップ・ミュージックの基本フォームすら手放している(正確には形式的に「同調」するだけのポップ・ミュージックのフォームから遠く離れているだけで、耳を拓いて無心に音を追い続ければ、『async』はある意味でとても聴きやすいアルバムでもある)。
同時に「妥協しない」という堅苦しい不自由さからも自由であり、その自由さによって本作は聴き手の耳に向かって、無限に開かれてもいる。すべては聴き手次第。聴くこと次第、とでもいうように。ゆえに本作はリスナーをとても信頼している作品のようにも思える。われわれに問いかけている音楽のようにも聴こえる。
とはいえ、『async』は唐突に生まれたわけではない。この20年ほどの電子音響の潮流を背景に、カールステン・ニコライやフェネス、テイラー・デュプリーなどとのコラボレーション/創作活動の結果、生まれた作品でもある。その意味で、90年代の音響派、90年代後半以降のグリッチ、00年代的なアンビエント/ドローン、10年代的なエクスペリメンタル・ミュージックやフィールド・レコーディング作品以降の音楽作品として、全世界・各国で高い評価を獲得することも予想できる。たとえば、〈ラスター・ノートン〉、〈タッチ〉、〈12k〉を愛聴するリスナーたちに。もしくは〈ECM〉を求めるような繊細な耳を持ったリスナーたちに。
この静謐で美的な音楽を生み出すマテリアル=音の数々を、坂本龍一はまるで縄文時代の狩猟民族のように「捕って」きているように思える。雨、足音、ざわめき、アルセニー・タルコフスキーの詩を朗読するデヴィッド・シルヴィアンのヴォイス、『シェルタリング・スカイ』のポール・ボウルズによる朗読、電子音、弦、東北大震災の洪水に溺れたピアノの音などなど……。坂本はいまだ音の狩人なのだ。それこそが受動的に「聴くこと」を推奨するエレクトロニカ系のサウンド・アーテイストとは違う点ではないか。この世界に横溢する音の蠢きを、坂本は繊細な音響彫刻、もしくは静謐な映画のように織り上げてみせる。狩猟/織り上げ。野蛮と繊細の共存。
私見だが、本作のコンポジションの過程において「時間」の感覚が、これまで以上に研ぎ澄まされているように思えた。本作のアルバムの収録曲は、どれも比較的短い。この種のエクスペリメンタルなアンビエント曲は長尺になる傾向があるが本作は違う。同時に「短い」とも感じない。むしろ聴いているあいだは、豊穣な時間の只中にいる。ここが本作の肝ではないかと思う。聴き手を音響や音楽の時間に招き入れる力があるのだ。
21世紀に復活したバッハのコラールのような1曲め“andata”から、持続音のなかに溶けたマーラーのアダージョのようなアンビエントである最終曲“garden”まで、止めることなく一気に聴けてしまう。曲の構造、アルバムの構成など、シーケンスとシーケンスが厳密に、しかし感覚的に、記憶に作用するように編集されているような感覚を抱いた。
まるでアルバム1枚で、90年代以降のゴダール作品や、タルコフスキーの作品などの映画作品を観たかのような充実感がある。となれば、本作の坂本龍一は音だけの、「音による映画」を生み出したのだろうか。じっさい本作には「タルコフスキーの架空のサントラ」というコンセプトもあるようだが、それは表面上の問題ではなく、音響=映画によって、生の記憶と受難を表現しようとする意志を感じた。
この『async』に漂っている悲痛なムードは、まるで環境音、アンビエントによる受難曲のようである。それは悲観とは違う。長い冬を抜けて、春の芽のようにある命が生まれ、その命がこれから辿る生の、受難の響き/音楽だ。冬から春へ。そして夏から秋へ。四季という生の循環。
そう、ライフ=生の感覚が、確かに、この音の蠢きの中に息づいている。もしかすると、坂本龍一にとってノイズ=サウンドとは、生=ライフのことなのかもしれない。
デンシノオト
ALBUM REVIEWS
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain
- Lost Souls Of Saturn - Reality


 DOMMUNE
DOMMUNE