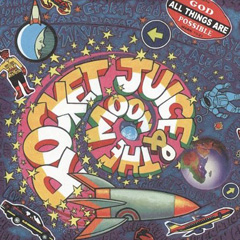MOST READ
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- interview with Toru Hashimoto 選曲家人生30年、山あり谷ありの来し方を振り返る | ──橋本徹、インタヴュー
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- Jlin - Akoma | ジェイリン
- 『成功したオタク』 -
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 | 対談:ジェフ・ミルズ × 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- みんなのきもち ――アンビエントに特化したデイタイム・レイヴ〈Sommer Edition Vol.3〉が年始に開催
- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- Beyoncé - Renaissance
Home > Reviews > Album Reviews > Gorillaz- Plastic Beach
デイモン・アルバーンはとんでもない情熱家だ。向学心があって、ポップ・ミュージックの時計を20年前に戻すことを許さない。ブラーとしてセカンド・アルバムを出したばかりの頃に取材で話したときの彼は、60年代の音楽とカーナービー・ストリートの服屋の話を喜んでするようなご機嫌な青年だったけれど、ブリット・ポップ騒動のなかで相当に揉まれたのだろう。トニー・ブレアにオアシスとともに持ち上げられ、そしてまあ、アイドル系のルックスだったがゆえに、労働者階級の英雄であるオアシスの、結局はなかば引き立て役のような、どこか損な役回りを強いられ、が、しかし労働党に裏切られたという政治的な経験をバネにするかのように、アルバーンはつねに向上心を捨てることなく、その後驚くほど貪欲な活動を見せている。アフロ・ミュージック(トニー・アレン)にアプローチしたかと思えば、イスラム文化にも接近してみたり(『シンク・タンク』)、あるいは漫画家のジェイミー・ヒューレットと一緒にゴリラズとして『西遊記』をモチーフとしながら音楽と文化をシャッフルさせる。イギリスの音楽らしく、そこに社会風刺と政治的主張も含まれる。
ゼロ年代にはじまったゴリラズは、デビュー・シングル「クリント・イーストウッド」において西海岸のヒップホップの魔術師オートメイターの力を借りながら、90年代初頭にコンシャス・ラップのひとつとして注目されたオークランドのデル・ザ・ファンキー・ホモサピエンスにラップさせている。2005年のセカンド・アルバム『ディーモン・デイズ』では、その時期玄人筋からもっとも受けていたUSとUKのふたりのラッパー、MFドゥームとルーツ・マヌーヴァを誘い、チャレンジ好きのヒップホップ・プロデューサーとして知られるデンジャー・マウス、それからデ・ラ・ソウルとショーン・ライダーを招き入れている。こうした前2作のスジで考えても今回のアルバムのゲスト陣は尋常ではない。
物欲の塊のような西海岸の大物ラッパー=スヌープ・ドッグ、ガラの悪いUKグライムのスター=ケイノ、正義感の強いラッパー=モス・デフ、ウェールズのヒッピー左翼のロッカー=グリフ・リース、毒舌と批評精神のシンガー=マーク・E・スミス、それからルー・リード......ボビー・ウーマック、それから元ザ・クラッシュのミック・ジョーンズとポール・シムノン、前作に続いてデ・ラ・ソウルも......、洒落たクラブ・ジャズからはユキミ・ナガノまで......、あるいはシカゴからは元サン・ラ・アーケストラのヒプノティック・ブラス・アンサンブル......。まとめると、ルー・リードとケイノとマーク・E・スミスが1枚のアルバムに収まっていること自体が奇跡的で、まずはこのオーガナイズ力だけでも賞賛に値する。
もちろん背番号10を11人揃えれば強いチームが作れるわけではない。問題は明確な方向性だ。ゴリラズは、エレガントなエレクトロ・ヒップホップやディスコやポップスを回転させながら、世界が滅亡した後に太平洋に残された島を舞台として、新自由主義の犠牲としての環境破壊を物語る。
「世界は絶望的だ」――西海岸のG・ラップのスーパースター(スヌープ)はラップする。「革命はTV放映される」――先頃カムバックしたギル・スコット・ヘロンの言葉を引用する。レバノンのナショナル・オーケストラの演奏に混じってグライムのビートが飛び出し、バッシーとケイノのラップがたたみかける"ホワイト・フラッグ"はアルバムの白眉のひとつだ。この曲から素晴らしい生気が放たれたかと思えば、モス・デフとボビー・ウーマックが共演するダーク・エレクトロの"スタイロ"のメランコリーからはディストピアが浮かび上がる。マーク・E・スミスのぼやき節のみならず、曲調までザ・フォールじゃないかと思わせる"グリッターズ・フリーズ"は文句なく格好いいし、モス・デフとヒプノティック・ブラス・アンサンブルによる"スウィープステイクス"の楽天性は多くの人に愛されるだろう。ルー・リードがエコロジーについてソウルフルに歌う"サム・カインド・オブ・ネイチャー"やグリフ・リースが未来の食生活を憂う"スーパーファスト・ジェリーフィッシュ"も面白いし、ユキミ・ナガノがコズミック・ディスコをバックに歌う"エンパイア・アンツ"も捨てがたい。
多くの個性派を集めたが故に、アルバムの中心がどこにあるのかわかりづらいという評もあったが、たしかに1曲だけを選ぶことは困難かもしれない。まあ、しかし逆に言えば全曲気を抜けずに聴けるということでもある。そして何よりも重要なのは、元ブリットポップのスターが情熱を傾けてこのコンセプト・アルバムを完成させたということだ。「オレは自分が環境問題について考えていたとは言わないよ。あの曲もそんなものではないんだ」、ケイノは『ガーディアン』の取材でアルバーンが最初にアルバムのコンセプトについて説明してくれたことを明かし、そしてこう語っている。「"ホワイト・フラッグ"は警告なんだ。世界は滅び、そしてふたたびはじめるための警告だ。それは平和を暗示するのさ」
野田 努
ALBUM REVIEWS
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes
- Beyoncé - Cowboy Carter
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow
- Jlin - Akoma
- Ben Frost - Scope Neglect
- Savan - Antes del Amanecer
- Rafael Toral - Spectral Evolution
- Kelela - RAVE:N, The Remixes
- Kim Gordon - The Collective
- serpentwithfeet - GRIP
- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks
- Philip Glass - Philip Glass Solo
- Royel Otis - Pratts & Pain
- Lost Souls Of Saturn - Reality


 DOMMUNE
DOMMUNE