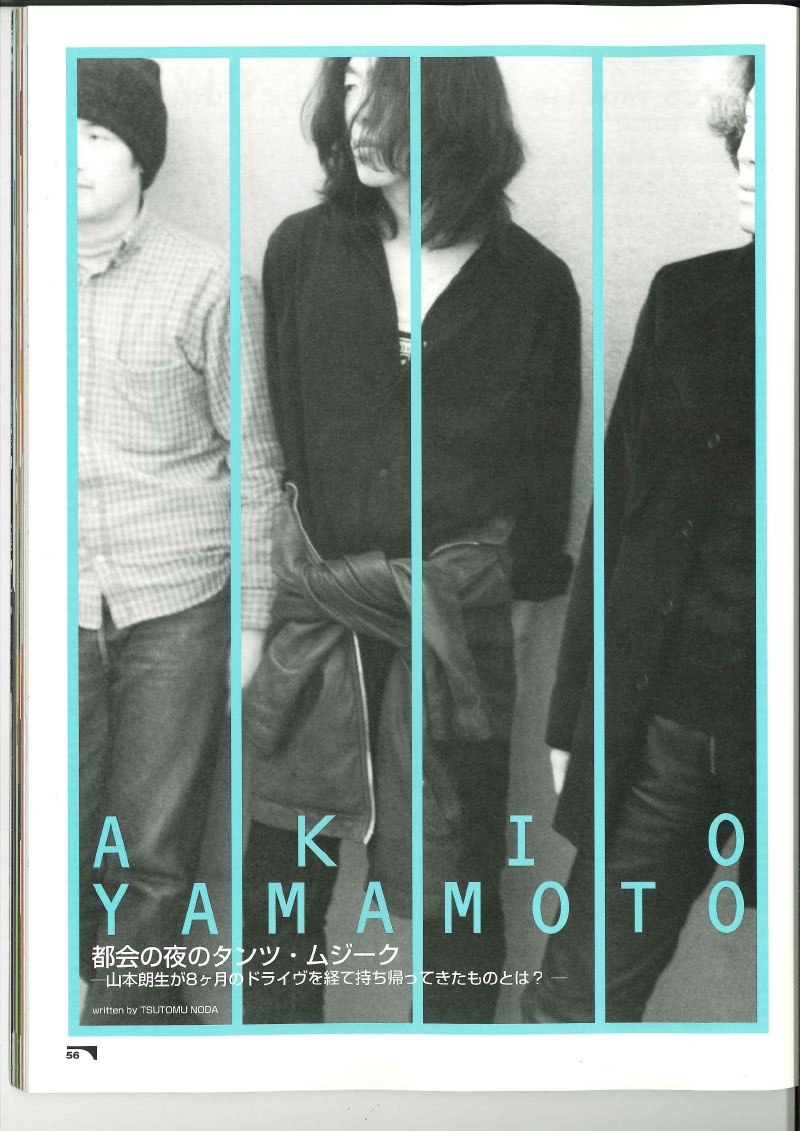MOST READ
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- Rafael Toral - Spectral Evolution | ラファエル・トラル
- 『成功したオタク』 -
- Bobby Gillespie on CAN ──ボビー・ギレスピー、CANについて語る
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- ソルトバーン -
- Claire Rousay - a softer focus | クレア・ラウジー
Home > Interviews > interview with Akio Yamamoto - 都会の夜のタンツムジーク
およそ8ヶ月ものあいだ、山本朗生と佐脇興英のふたりを乗せた車は夜の高速道路を走っていた。タンツムジークのプライヴェイト・ロード・フィルムの撮影のためである。車のなかから、映像を担当した朝比奈学の8ミリ・カメラが外の世界を覗く。撮影は震災後の神戸にはじまって、新宿の新大久保、福生、横須賀、そして大阪の西成へと足を伸ばす。ときにはヤバい場所にも侵入して、フィルムを没収されそうになったこともあったそうだ。それでも彼らを乗せた車は、止まることを知らなかった。
いつの間にか、フィルムは膨大な量に増えていた。そのフィルムには、都会の隅っこに転がっている異様な熱気の多くが収められている。ネオン街、雑踏、米兵、夜の熱気、青い空、雲のような街灯。フィルムからもわかるように、タンツムジークのニュー・アルバム『ヴァージョン・シティ・ハイライツ』はもはやハードコアなテクノ・ファンだけのものではない。
1996年末、フードラムから離れた山本朗生の頭には、映像を撮ることがまずあったという。それはなかば強迫観念のように彼を支配したが、しかしその映像が久しぶりに再開するタンツムジークの重要な下地になることを彼はわかっていた。とはいえ、それを完成させるには長い時間と多くの労力が必要で、資金的にも相当きつい。客観的にみれば暴挙と言えるだろう。が、山本朗生は、とにかく完成させることしか頭になかった。フィルムを発表するあてもないばかりか、タンツムジークの新作のリリース元もまだ決まっていなかった。それでも、まるで何かにとり憑かれたように、彼らはドライヴを続けたのだった。
車が目指したのは、日本の都会の片隅で暮らす移民たちの表情だった。あるいは、果てしなく続く道路そのものだった。新大久保に潜む南米から来たストリート・ガール。福生の街をうろつく米兵と少女たち、西成のホームレス、そしてネオンと道、道、道。日本のもうひとつのリアリズムの追求。こうした作業は、タンツムジークの音楽に新たな息吹を吹き込んでいった。
1994年にリリースされた『シンセカイ』を、僕らはもう忘れてもいいかもしれない(新生タンツ・ムジークは新たにARM名義で活動する久川大志が加入し、3人編成になった)。『ヴァージョン・シティ・ハイライツ』の1曲目を飾る“ウィークエンダー”を聴けばわかるように、最新タンツムジークには強力なビートが備わっている。それはターヒル名義で山本朗生が追求したビートの延長線上にあって、極端なカタチで構成された16ビートの裏リズムが強烈なファンクを打ち鳴らしている。タンツムジークが手に入れたファンクは、2曲目の“ア・ヴァージン・シティ・エピソード”でも鳴っているが、この曲は、近い将来パトリック・パルシンガーとデリック・カンターのリミックスとアキヲ・ミランパーク名義のリミックスを収録してシングル・カットされるという。
6曲目の“モカ・コルバ”もまた、このアルバムのクライマックスのひとつだ。うっとりするような美しい瞬間が、こと細かく展開されるリズムパターンのうえから聴こえてくる。そして、それはたしかに深夜の高速道路の暗闇を飛ばしているような気分にさせてくれる。“C.M.Y.”からは、シンプルな繰り返しでありながらカール・クレイグの“ニューロティック・ビヘイヴィア”を彷彿させる深い叙情性が聴ける。また、“ウェスタン・コス”から最後の“シティ・ライツ”にかけては長いトンネルをくぐり抜けたかのような軽快さが待っている。
久しぶりに会った山本朗生は、まるで生まれ変わったように生き生きとした顔つきをして現れた。前の晩はフィルムの編集で寝ていなかったというのが嘘のようだった。僕は彼に、新作には強く感じるものがあったことを伝えた。その強さは、初期のタンツムジークにはなかった種類のものだ。
「あの頃は、なんも考えてないッスよ。いや、ほんま俺に関しては差異を生もうとか、そういうのは全然なかった。ほら、だいたい当時俺“テクノ知らん”とか、よく言うてたやんか。〈ライジング・ハイ〉だって出すまで名前しか知らんかったしね。オッキーもめっちゃ詳しいかって言うたらDJぐらい詳しいわけやなかったから。そんななかであれが生まれた感じはあるんよ。そんで、僕らはもともとライヴ・ユニットやったし、その前はほんまにヴォーカルが入ってるようなバンド(※シークレット・ゴールドフィッシュ)に入ってたから」
何か伝えたいことが強くあるように感じたんだけど、と言うと彼は以下のように説明する。
「まずは攻撃性ということがあった。これはリズムに関してだけど。極端に精神の攻撃性を高めていったら、絶対動きにフェイントがでてくるんですよ、拳法的な。ムエタイとかでもそうじゃないですか。フェイントの応酬になると思うんですよ。極度まで攻撃性を高めたらそういうふうになると思うから、突き詰めると俺はこういうリズムになるというか」
『ヴァージョン・シティ・ハイライツ』を作るうえで何故フィルム撮影が必要だったのだろうか。その質問に対して山本朗生はシンプルに「タクシー・ドライヴァーの視点で街を見てみたかった」と答え、さらに次のように加えた。
「映像を撮ろうとしたときに、例えば、お金があるからってニューヨークで撮ろうていうのは“違うやろ”っていうのがあった。俺らは日本に住んでいるんやし、ライヴでよく海外に行ったりとはせえへんし。そんなのやったら嘘やないですか。やっぱ日本やないとあかんやろって。で、ほんまのリアリティのある嘘じゃない日本を撮りたかった」
では、リアルな日本を撮るために、何故新大久保や福生といった街を選んだのだろうか。
「おもしろかったから。例えば新大久保は、コロンビア人の女の子とかええ顔してるんですよ。ほんま、日本人やったらあんなキッツい労働できへんでしょ。でも、笑うとるんですよ。 それがね、チャーミングでもあり、 かっこよくもあり、なんか感じるものがあったんですよ。 俺らが車乗ってると声かけてきたりするじゃないですか。 それで、そこらへんを2、3回まわってたら南米あたりの子は話しかけてくるんですよ。 “また会ったね” とかね。 そんでその表情とかがね、 何か感じるところがあったんですよ」
その感じは決して 「ダークではなかった」と彼はつけ加える。 そして、撮り続けているうちに彼女たちから何かエネルギーのようなものさえ感じていたという。
「アウトローっていうかね、ふだん真面目な日本人が避けて通るような場所っていうかね、ほんまやったら虐げられてるそういう人たちのほうが画面で見たときエネルギーとかいろんなもの感じるときがあるし、これはなんなんやろっていうのがあって。でもそういう世界は絶対的な事実やと思うんですよ。もちろん自分らには彼らのいる世界をどうもしようがないし、だからどうしたっていう提示もないんやけど。 自分でもただそれを撮ってみたかったのか、サンプリングしたかったのか、 エディットしたかったのかわからへんけど、とにかく何かを感じた。それにけっこう日本は、臭いモノには蓋をするっていうのがあるじゃないですか。 だからなおさら撮りたいっていうか。撮っているあいだはただ無我夢中だったけど」
つまりタンツムジークは、清潔な日本の都会とは逆の方向に車を走らせたというわけだ。そこで目撃していった数々の場面が、 タンツムジークの音楽にあらたな意味を持たせている。それは僕たちの住む国のサウンドトラックでもある。それだけでも僕は、 タンツムジークのセカンド・アルバムは多くの人に聴かれるべき作品だと思っている。だってそう、ベッドルーム・テクノはいま街に飛び出したのだ。
これは、タンツムジークが頑なな実験派で、限られたテクノ・ファンだけを相手にしているアーティストだと思っている人には予想外のカウンター・パンチかもしれない。こうしたサウンドの変化に関して、山本朗生はジャマイカン・カルチャーからの影響について話す。 ここ2年、ほとんど他の音楽にインスパイアされることがなかったというが、彼にとってレゲエだけは特別だった。
「昔からレゲエは好きやったけど、たまたまレゲエのヴィデオを観てたらそのすごさを再確認したっていうかね。 ほんまパンク以来のショックやったんですよ。 ほんでラスタのことにどうしようもなく興味を持ってジャマイ力に関する本もたくさん読んだし、ヴィデオもたくさん観たしね。 歴史的な背景とかも植民地からはじまって云々とかね。それとごっつい慢性的な不景気でしょ。 そういうなかで生きてる音楽というか、あの音楽のエネルギーがねえ、例えば、70年代のサンスプラッシュのヴィデオとかからすごい感じられてん。だからと言って、ジャマイカに住もうとか、ええとこだとは思わへん。 絶対に住みたくないし、行ってはみたいけどね。 そのへんはき違えたらアホやから」
福生や横須賀(といった米軍基地のある街)での撮影を通して、山本朗生はあらためて日本の歴史について考えたという。だからといって彼は、リスナーに対して「考えろ」ということを言いたいわけではないと強調する。「(リスナーを)スカッとさせたい。 ただそれだけ」
『ヴァージョン・シティ・ハイライツ』 はデヴィッド・ホームズの『レッツゲット・キルド』やバリスティック・ブラザースの『ルード・システム』 なんかと近いところがないわけではない。が、どう考えても新大久保はブルックリンではないしブリクストンでもない。日本人と移民労働者とのあいだには、まだまだ計りしれない壁がある。 撮影のあいだ、台湾人の女性から冷ややかな目で見られたこともあったと彼は付け加える。
山本朗生は、いまの日本にテクノに対する追い風が吹いていないこともわかっている。テクノをやっているというだけでは、もはやそこに新鮮な響きなどない。タンツムジークという名前を、今日の日本の、例えば本誌読者のなかでどれほど気にしている人がいると思うか、という少しばかりキツイ質問をしてみた。 山本朗生は答える。「自分はもともとそんなにメディアに露出してなかったし、期待もなかった」。だからむしろ、これまでいろんな場所で聴いてくれている人と会ってきたことが、いまの自分にとっては励みにもなっていると。
今回の取材での彼の答え方は、始終、実に爽やかなものだった。それに、これからまたはじまるような雰囲気が彼にはあった。 妥協しないで作品を完成させたことが、彼にポジティヴな気持ちをもたらしたのだろう。 実際の話、日本のもうひとつのリアリズムを描くというコンセプトは、タンツムジークの音楽の強度を確実に高めたのだから。
現在、山本朗生が東京に、佐脇興英が京都に、 久川大志が高知に住んでいるため3人が揃うのはなかなか難しい。だからというわけではないが年内はそれぞれのソロ活動をやって、 ひょっとしたら年末にはタンツムジークのサード・アルバムに向けてアクセルを踏むかもしれない。それにしても不思議というか不可解なのは、 タンツムジークがここまで心血を注いで創り上げた30分のロード・ムーヴィーを上映する予定も売りに出す予定も、この取材の時点ではまだないことだ。 限定でもいいから、なんらかのカタチで発表して欲しい。でなければエレナイトで上映するしかない。 だって本当にいいんだから。

■タンツ ムジークの『Version Citie Hi-Lights』はサブライムレコードより5月20日に発売。レコード店に行ったら探す価値あり!
取材:野田努(2022年6月22日)
INTERVIEWS
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー
- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る
- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会
- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから
- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”
- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン
- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー
- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く
- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー
- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る
- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー
- interview with Gazelle Twin - UKを切り裂く、恐怖のエレクトロニカ ——ガゼル・ツイン、本邦初インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE