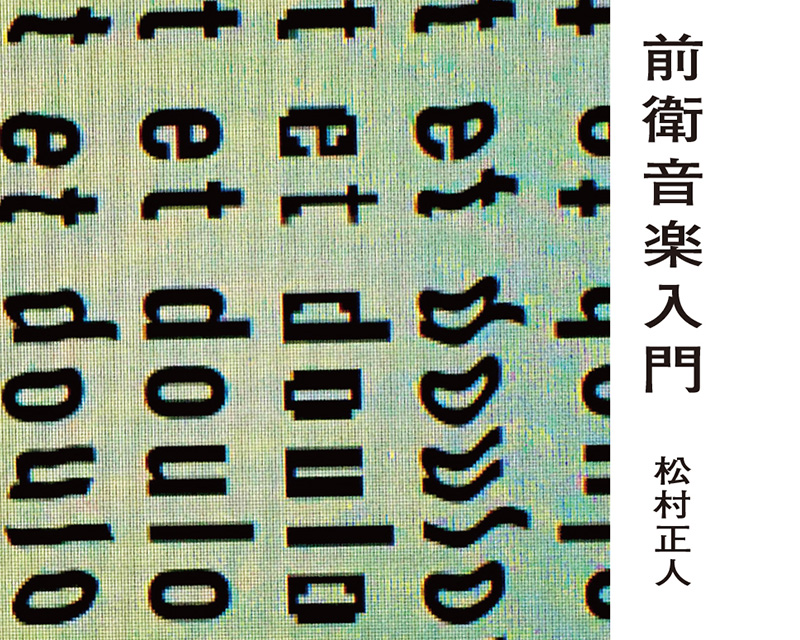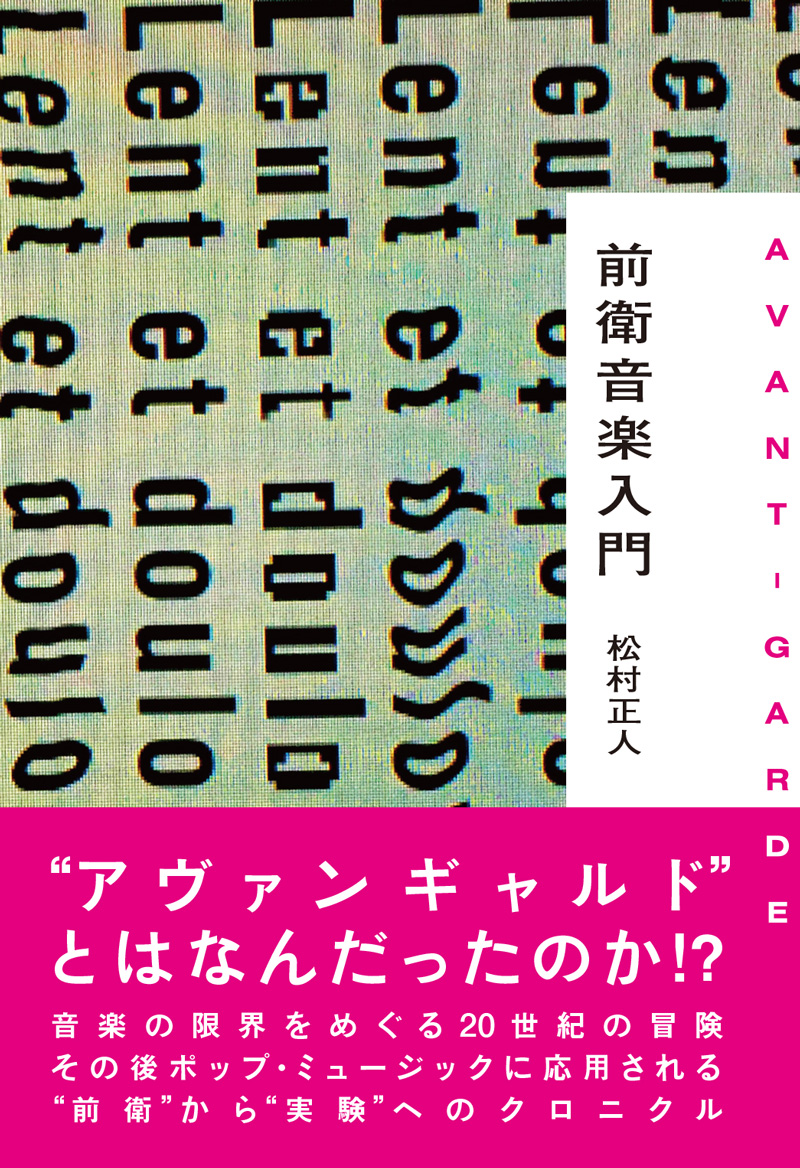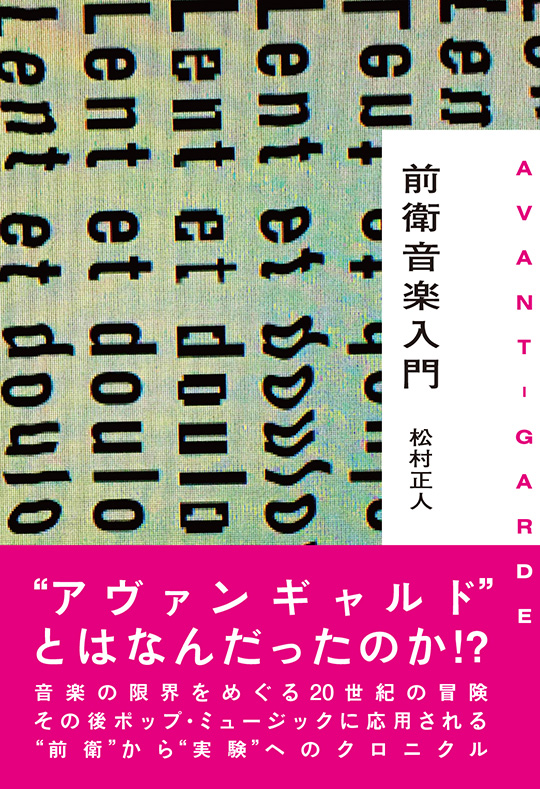MOST READ
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- 『ファルコン・レイク』 -
- レア盤落札・情報
- Jeff Mills × Jun Togawa ──ジェフ・ミルズと戸川純によるコラボ曲がリリース
- 『成功したオタク』 -
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!
- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024
Home > Interviews > interview with Masato Matsumura - これからの前衛音楽のために
録音と自然について
私はやっぱりモダニズムが好きなんですよ。ダダとかシュルレアリズムとかロシア・アヴァンギャルドとかバウハウスとか近代文学とか。YouTubeにアップされている昔の歌謡曲の映像についたコメントによく、この時代に生まれたかったってのがあるじゃない。それをいったら、私だって1920年代の東欧で青春を送りたかったよと思うもんね。
■20世紀のある種の音楽史を描くに当たって、参考にした書物などはありましたか?
松村:それぞれのパートでいろいろな本を参照しましたけど、全体の構想や構造を立てるにあたって参考にした本はあんまりなかったかなあ。それよりもユヴァル・ノア・ハラリの『ホモ・デウス』とか、ジャレド・ダイアモンドの『銃・病原菌・鉄』とか、ビッグ・ヒストリーみたいなものは意識したかもしれない。歴史とかある程度の厚みのある時間を対象にするという意味でね。でも音楽で歴史を溯るのってむずかしいと思うんですよ。ポール・グリフィスの『文化のなかの西洋音楽史』のように、発祥まで溯ると、音楽は壁画にも遺物にもならないわけだから、語るにあたっては空想にちかくなってしまう。その空想は類型的になりがちで、論証も反論もできない。もちろんそうするしかないにしても、私なぞがいうまでもない。だったら、ネウマ譜の時代からはじめればいいともいえるけれども、それを語る言葉を私はもっていない。もちろん記録がないとダメってことでもなくて、西洋音楽に限定する必要もないのだけど、いまの音楽の状況を考えても、いろんな読者と語り合える点でもそっちのほうがいいかなと思った。クラシック音楽みたいな学校で教える音楽には畏怖も抵抗もあったけど、ロックやジャズやそのほかもろもろの勝手のわかった音楽を語るのも自分が成長しない気がした。たしか保坂(和志)さんがいっていたと思うのだけど、なにかを書くのは、書く前と後で書くひとが変化するためでもあると、私もそう思うから、だったら、それまで聴いてきていても、あまり書く機会のなかった「古典的な現代音楽」って言い方も妙だけれども、そのような音楽をちゃんと聴き直して考えてみたいと思った。話はかわるけど、ポピュラー音楽の批評って、どうしてもロックンロールの発生を起点にしがちで、音楽はそれ以前から連綿とつづいてきたはずなのに、その前と途絶しがちだと思うんですよ。日本の近代のはじまりを明治時代に置いたときに、江戸以前が歴史にくりこまれて不動になってしまうように。20世紀の、ことに前半はポピュラー音楽の読者には遠い過去で、逆にクラシック音楽の愛好家には現代音楽の時代なわけで、両方をつなげて、生き生きと描けたらおもしろいんじゃないかという考え方です。話を戻すと、参考にした本については、音楽の書き手にはそれぞれの分野にすごいひとがいて、参考にした文献は無数にあって、きっと誰かが同じことをいっていると思ったけど、現代音楽もジャズもロックもクラブ・ミュージックも同じ目の高さでみるという意味では、特定の書物を参考にしたというよりそれらのあいだを考えていた気がする。
■19世紀と20世紀の大きなちがいの一つに録音というファクターがありますよね。『前衛音楽入門』の序ではミシェル・レリスによる録音装置の描写が引用されています。
松村:そのレリスのくだりはたまたまね、積んでいた本が崩れて付箋がついた箇所を開いて引いただけなのだけど、原稿を書いていると、そういうことがよくあるじゃない。それを読んで、ジョイスの『ユリシーズ』にもたしか蓄音機で音を録音するくだりがあったことを思い出して、20世紀前半に録音再生装置っていうものが記録媒体としてかかわりはじめたときの人々の驚きを再確認したんだけど、それってカセットでもハードディスクでもTikTokでも同じだと思うんですよ。私にとっても録音再生装置の驚きというものはあって。中学生の頃にカセットデッキを親から買ってもらって、ラジオとか喋り声とかを録って遊んだりすると、再生するともとの音とまったくちがう響きになるのがわかる。それは記録すること以上のなにかをもたらすわけです。そうした驚きが音楽そのものにフィードバックしていくのが電子音楽でありミュジーク・コンクレートだと思った。録音の面白さみたいなものは私自身も実感として感じていたから、電子音楽やミュジーク・コンクレートの作曲家の内面を考えてみたらすごく親近感をおぼえた。録音再生装置が紡いできた音楽史というものがあり、近代の芸術ときりはなせないなら、音楽の歴史と録音物の歴史みたいなものをなるべく往還しながら考えていく、というのはごく自然にやってました。
■レリスの描写の面白い点は、録音再生装置の描写であるとともに、録音メディアというものが透明な存在ではないということを捉えた文章でもあるところだと思います。つまり再生に伴うノイズだとか、再生することの得体の知れなさが描写されているんですよね。それは自明なものや前提条件にあるもの、いわば自然と化したものに対する自覚を促してくれるんですが、そうした自然なるものから距離を見出していく運動というのが、前衛音楽の歴史でもあるわけですよね。
松村:おっしゃるとおり。
■これはたまたま私がいまティモシー・モートンの『自然なきエコロジー』について書いていたからかもしれませんが、『前衛音楽入門』では「自然」が一つのキーワードになっていると思いました。それはドビュッシーによる「自然の音楽はわれわれをすっぽりと包み込んでいます」という言葉から始まり、アドルノの「第二の自然」というルカーチを借用した音楽の捉え方や、あるいは「不自然な即興」という章題にもつながっています。
松村:自然という言葉はふたつの捉え方があると思うんですよね。ひとつは自然=環境というようなものの見方。あらかじめ備わっている、疑うべくもないもの、そういう自然なものに対して懐疑的になるのがやっぱり前衛音楽の勘所だと思った。あらかじめ与えられたものごとに対して「本当にそうかな?」って考える行為。アドルノの「第二の自然」っていう言い方はすごく上手いもんだなと思っていて。音楽って人工物じゃないですか。でも人工物なのに、たとえば調性のようなものは神の摂理みたいに考えられている部分がある。平均律も機能和声もきわめて人工的なものだけど、誰もが当たり前のように思っていて、21世紀のいま、そのことは19世紀より支配的になっている。Jポップをもちだすのはどうかとも思うけど、流行りの音楽を聴くと、メロディの洪水につかれるんですよ。ティモシー・モートンのその本は私は読んでないけど、音楽をひとつの環境とすると、前衛的な人工性より無垢な原初主義に軍配をあげるのは旧来のエコロジー観といえるかもね。問題はそこでいう自然に道徳的なニュアンスがあることで、同時にそれは音楽のルールというものにもつながるのだけど、その外に踏み出したのが前衛音楽であり、即興も既存のルールをのりこえようとする点では不自然だったと思うんですよ。で、自然のふたつ目の意味は言葉そのままの自然、ジョン・ケージ的な非音楽の世界。音楽的には不自然な音そのものの広がりみたいなもの。そういう、何重かの意味が重なっている「自然」っていう言葉は、たしかにすごく象徴的だなとは思います。
音楽批評の先達たち
それをたんに進歩史観でとらえるとエリーティズムやアカデミズムに陥ってしまうけど、20世紀前半の音楽家たちの試みが、実験音楽の時代を経て、最終的にポピュラー音楽やクラブ・ミュージック、おそらくは私たちがいま聴いている音楽にも流れ込んでいる、その運動もふくめて、私は前衛的だと思う。
■『前衛音楽入門』のもう一つの特徴として、教科書的な体裁をしているんですが、事実説明的な文章ではまったくないんですよね。パフォーマティヴで物語的というか。文体の強さとも言い換えられるかもしれませんが。
松村:野田さんには難読漢字ばかりで、おまえは小林秀雄かって注意されたんだけど(笑)、私、小林秀雄に入れ込んだことないんだよなあ。まあでも、自分の文章はよくわかりません。文体が強くても弱くても、精一杯書いているとしかいえないのだけど、表現にかまけるのは止めようと思ってきたかもしれない。ひとつには、雑誌編集者をやっていたある日、ポエティックな文章は書き飽きたと思ったから。音楽でそんなことをやると夜郎自大な感想文になっちゃうじゃん。この夜郎自大という四字熟語も注意されてしまうかもしれないけれども、習い性としてお許しいただくとして、表現よりも文の構造と展開が散文の勘所だとは思っているところはあるかも。そのほうが読んでいて、いろいろ考えられると思うんですよ。
■そうした点が本書を教科書から音楽批評へと押し上げていると思うのですが、松村さんにとって重要な音楽批評家の先達というのはいらっしゃいますか?
松村:そりゃもうみんなすごいなあって思ってますよ(笑)。90年代末から2000年代初頭にかけては、仕事の関係もあって、三田さんや野田さんの原稿からはいろんなことを学んだし、湯浅(学)さんや佐々木(敦)さんは学生のころから読んでいたし、竹田賢一さんや岸野さんから原稿が届いたときはうれしかったし、松山(晋也)さんは編集者としてもみならっていました。ひとまわり上の世代の書いてきたことを受けて、私は原稿を書きはじめたし、彼らの音楽の聴き方や考え方からは多大な影響を受けてきました。その一方で、文章を書くという点では、私はele-kingでこんな古めかしい音楽と関係のないことをいうのはどうかと思うけど、第二次世界大戦に強迫観念的な執着があって、その手の文献を読み漁ってきたのね。それを入り口に、小島信夫とか島尾敏雄とか庄野潤三とか、第三の新人の本はだいたい読んだけど、あの世代でいちばん好きなのは古山高麗雄かも。編集者だし。
■若い頃に読んで価値観を揺さぶられた音楽書とかはないんですか?
松村:あ、そうだ、秋田昌美さんの文章は好きだった。『前衛音楽入門』を書くにあたっても、『ノイズ・ウォー』を読み直しました。あれ絶版なんだよね。もったない。秋山邦晴さんの『エリック・サティ覚え書』が再版になったのはよかった。高橋悠治さんの本はどれをとっても閃きがある。武満徹の本もふくめて、私は音楽をやることと書くことが結びついているひとの文章に惹かれるのかもしれない。でも私の若いころは、音楽の文章というと本にまとまっているのより雑誌に載っているのを読むのがずっと多かったと思いますよ。
■『前衛音楽入門』では間章の引用もありますが。
松村:間章の本は私が学生のころは手に入りにくかったからね。妄想が広がって、じっさいの文章はその妄想をも上回るものだったんだけど、私にはちょっと濃密すぎたかな。彼が言及するレコードや、たまに引用するモーリス・ブランショなんかは私も好きなんだけど。
■間章と犬猿の仲とも言える平岡正明はどうですか?
松村:平岡正明は、そうだね、私は先に湯浅さんの文章を読んでたんですよね。ふたりはまったくべつの書き方だけど、言い切ることでひとつの世界をたちあげるところに通じるものがあるんじゃないかな。おふたりとも、対象にたいする濃度というか熱量のようなものをもっていて、平岡さんはそこに向かう向かい方が直線的だけど、湯浅さんは面的な気がする。抽象的な印象論ですけどね。直線的な語り方は説話的だけど、面的だと散文的になると私は思っていて、自分には後者のほうがしっくりくる……というか、細田くんはなんでそんな答えにくいことばっか訊くの。
これからの前衛音楽のために
だって嫌いなものを好きになることってあるじゃないですか。そういうふうに考えたら、音楽の聴き方って生理的体験だけではない、ということがわかったのが20世紀だなとも思った。前提にあるものや後に続くものを含めて聴き比べてみたら何か発見もあるだろうし、前衛音楽に対するバイアスも緩むにちがいない。そもそも私、『前衛音楽入門』でとりあげた音楽はどれもキャッチーだと思ってるんだけどね(笑)。
■面的で散文的な向かい方というのは重要だと思います。それは開放感と言い換えられるかもしれません。たとえば前衛音楽に開放感をもたらすにはどうすればいいと思いますか。裾野を広げていくというか。この前タワーレコード新宿店の10階に行ったら、ニューエイジコーナーがすべて星野源コーナーになっていたんですよ。時代もジャンルも多種多様な音楽で埋め尽くされていたニューエイジコーナーが、星野源というたった一人のアーティストに駆逐されてしまったように感じて、たいへん寂しい思いをしました。
松村:それは……!? そうなったんだ。あそこよかったんですけどね。現代音楽系の新譜もけっこうとりそろえていて、しかも人がいなくてゆったりみられるからよく行ってたんですけどね。
■人がいないんじゃないですか(笑)。これは私の意見ですが、閉塞感の一つの原因として、前衛音楽という言葉が記号化して、「ああ、前衛音楽ね、興味ないや」と見向きもしない人と、「おお、前衛音楽か、聞いてみよう」と飛びつく人に二極化してしまっていることがあるような気がするんです。それは実験音楽とかフリー・ジャズといった言葉も同じように扱われていると思いますが、ともあれ、嫌いだろうが好きだろうが彼ら/彼女らにとって内実はどうだってよいわけですよね。この短絡的な思考が閉塞感を呼び込んでいるのではないかと思います。
松村:やれ難解だとか複雑だとか高尚だとか、そういった短絡化は前衛音楽にはこれまでもあったけど、前衛がひとの口の端にのぼらなくなってから、記号そのものが空洞化したきらいはあるよね。情報化の煽りを喰って、細田くんがいったような状況になっているのだとしたら、その状況は閉塞的というよりもっとのっぺりしたものだと思うのね。ポストモダンを云々するのはわかった気になるからイヤなんだけど、細分化をくりかえして記号がどんどん細かく、軽くなっていく一方で、行き着くところまでいって、揺り戻しが来ているのがいまで、いろんなレーベルから過去の音源も含めて、前衛音楽や実験音楽のレコードが再発されているじゃない。刷られている数はたいしたことはなくても、一定の枚数をうけとるリスナーはいるということですよ。そこで本を書くことの意味はなんだろうと考えてみると、たとえばカタログだと記号の数になっちゃうけど、一冊の本を書き上げていくっていうことは、それがなにがしかの時間の幅を持ったものになっていくことではないかなと思ったんですよね。たとえば『前衛音楽入門』を雑誌の特集としてやることはできると思うわけ。でもそうすると風景があんまり変わらないような気がするんですよね。それは自分が雑誌をずっとやってきたからかもしれませんが、そういう歴史や時間の幅を表現するにはある程度の分量を書かないとダメだろうと思った。そこには当然、余白とか余剰とか、語られていないことがあるわけですよ。そういう幅のなかで前衛音楽という言葉を使っているのであれば、記号の伝わり方がまた変わってくるとも思う。ディスクガイドではないわけで、パラパラと眺めてわかるものではない。著者が「これが前衛だ」というものをどう捉えているのかというのは読まないとわからない。読むとそこには「そうじゃないもの」が行間に入っていることもわかる。そうすれば記号化を緩めることもできるんじゃないか。前衛音楽の外側から滲んでくるものがあったら、少し広がるんじゃないか。それは単なる好き嫌いじゃないですよね。レヴィ=ストロースの『神話論理』っていう全四巻の本があるんですが、その第一巻の『生のものと火を通したもの』の序章では音楽について書いているんですよ。そこでレヴィ=ストロースは音楽を生理に根差しているっていうふうに書く。生理的体験、要するに好き嫌いだと。でも私はそうなのかなって疑問に思うところもあった。だって嫌いなものを好きになることってあるじゃないですか。そういうふうに考えたら、音楽の聴き方って生理的体験だけではない、ということがわかったのが20世紀だなとも思った。前提にあるものや後に続くものを含めて聴き比べてみたら何か発見もあるだろうし、前衛音楽に対するバイアスも緩むにちがいない。そもそも私、『前衛音楽入門』でとりあげた音楽はどれもキャッチーだと思ってるんだけどね(笑)。
■それは好き嫌いとは別に、前衛音楽を聴くことの楽しさがあるということでしょうか?
松村:そうです。でも聴くことの楽しさだけじゃなくて、考えることの楽しさもある。そして考えることの楽しさは聴くことの楽しさを損なわないとも私は思うんですよ。聴くことの楽しさと考えて発見することの楽しさって、ちょっとズレがあるじゃないですか。なぜこれがおもしろいんだろう、気に留まるのだろう、っていうことにたいする気づきって、ちょっと遅れてやってくるわけじゃない。それがやっぱりこういう音楽を聴くときのいちばんおもしろいところだと思うんですよね。テキストを読んで作曲家の意図や作品の構造を知ったときの、目から鱗が落ちる感じっていうかね。聴いただけじゃわからなかったとしても、ライナーノーツとかを読んで、意図や構造を知ってからあらためて反復したときに出会う聴くことの楽しさは絶対あると思う。そう考えると前衛音楽は録音物に親和的な音楽だったともいえる。反復聴取に耐え得るから。聴いて、よくわからなくて、それでも聴いて、やっぱりわからなくて、読んで、なんとなく納得して、発見するっていうのかな。そういう意味ではまさしく20世紀的な芸術のあり方ですよね。それってすごくお得じゃないですか(笑)。
■他方で音楽の前衛を原理的に推し進めるならば、ゆくゆくは音楽という概念も崩壊させていくことにもなるように思います。しかし『前衛音楽入門』ではあくまでも音楽が取り扱われていますよね。そこには音楽とあえて言い得るものは何かという問題があると思うんですが、松村さんとしてはどのように考えていますか。
松村:また答えにくい質問を(笑)。前衛音楽も当初は音楽そのものの制度や構造を含めて問うていた。「音楽は果たして音楽なのか」という考えがはっきりと出てくるのはケージ以降ですよね。とりわけケージの主著『サイレンス』が邦訳された90年代になると、ケージ礼賛みたいな雰囲気が蔓延していた。けれどもケージに対する批判も一方からはあるわけですよ。ルイジ・ノーノのように「そこまでいったら音楽じゃないんじゃない?」みたいにいうひとたちも一方にはいた。即興音楽でもそうじゃない。楽器に触れるか触れないかが即興だ、みたいなことにまでいくと、果たしてそれでいいのかっていう考え方が出てくる。そのようなせめぎ合いの歴史はどこまでいっても調停することはないんじゃないかな。ケージに対してノーノが否を突きつけて、ブーレーズも最終的には強烈な批判を加えていったように。それら両陣営がせめぎ合っている状態。私自身は態度としてはどちらに肩入れしたいわけでもないし、実験的なものよりも前衛的なものがよいとはいわないし、その逆もまたしかりですよ。その蠕動する部分に音楽の原理があるのだと思う。その状態はとどまらないだろうし、固定されて不動だと思っていた歴史にその解を求めようとしたって、どこからどのようにふりかえるかによって、答えはちがってくる。それらをもとに、聴いたこともない新しい前衛音楽が現れてくるかもしれない。テクノロジーや人間観みたいなものとも、それは関係してくるかもしれない。その意味で、音楽は終わったわけではないし、終わるわけがないのであって、『前衛音楽入門』に登場する20世紀の音楽家たちの問題提起は21世紀にも届いてきますよ、きっと。
取材:細田成嗣(2019年2月14日)
| 12 |
Profile
 細田成嗣/Narushi Hosoda
細田成嗣/Narushi Hosoda1989年生まれ。ライター/音楽批評。佐々木敦が主宰する批評家養成ギブス修了後、2013年より執筆活動を開始。『ele-king』『JazzTokyo』『Jazz The New Chapter』『ユリイカ』などに寄稿。主な論考に「即興音楽の新しい波 ──触れてみるための、あるいは考えはじめるためのディスク・ガイド」、「来たるべき「非在の音」に向けて──特殊音楽考、アジアン・ミーティング・フェスティバルでの体験から」など。2018年5月より国分寺M’sにて「ポスト・インプロヴィゼーションの地平を探る」と題したイベント・シリーズを企画/開催。
INTERVIEWS
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー
- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る
- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会
- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから
- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”
- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン
- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー
- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く
- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー
- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る
- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー
- interview with Gazelle Twin - UKを切り裂く、恐怖のエレクトロニカ ——ガゼル・ツイン、本邦初インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE