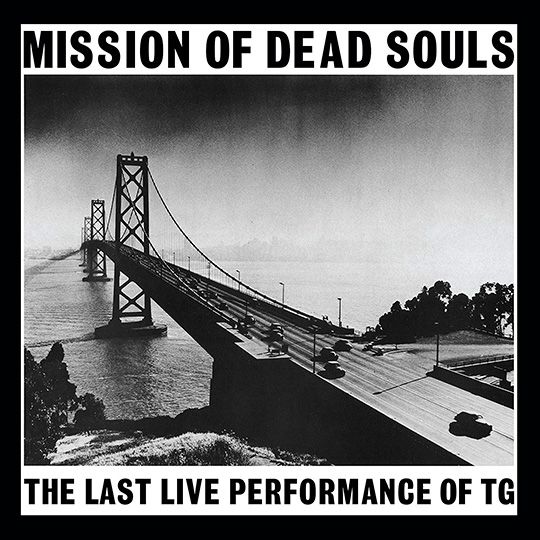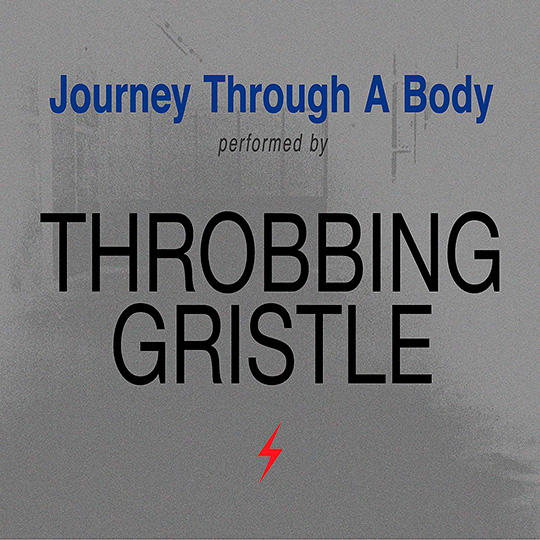MOST READ
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- 橋元優歩
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- Jlin - Akoma | ジェイリン
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- 『成功したオタク』 -
- interview with agraph その“グラフ”は、ミニマル・ミュージックをひらいていく | アグラフ、牛尾憲輔、電気グルーヴ
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- ソルトバーン -
Home > Interviews > interview with Cosey Fanni Tutti - コージー、『アート セックス ミュージック』を語る
まあ、わたしたちはいつだって個人として物事に対処していた、ということね。陳腐な言い回しになるけれども、「個人的な物事は政治的である」と。いまの質問である意味、あなたはわたしたちは政治に繫がっていなかったのではないか、と言ったわけだけど、そんなことはなくて、当然わたしたちも政治には関わっている。
■フェミニズムに限らず、70年代、80年代のUKの音楽シーンはどこかしら政治思想、イデオロギーとリンクしていたと思います。アナキズム、社会主義、コミュニズム、反資本主義等々。
コージー:フム。
■でもスロッビング・グリッスルにせよあなたにせよ、ああいう風におおっぴらに「政治的」だったことはなかった気がします。特定の政治的な「派閥」に同調したことはなかったのではないか? と。あなたは意識的に様々な「〜イズム」とご自分の作品との間に距離を保っていたのですか?
コージー:まあ、わたしたちはいつだって個人として物事に対処していた、ということね。陳腐な言い回しになるけれども、「個人的な物事は政治的である」と。いまの質問である意味、あなたはわたしたちは政治に繫がっていなかったのではないか、と言ったわけだけど、そんなことはなくて、当然わたしたちも政治には関わっている。ただ、個人のレヴェルでそこに関わっているだけ。でも個人的であっても、最終的にはとても政治的になっていくものであって。いまのようになにかひとつ、個人としてのレヴェルで物事がまずくなっている状況があったとして、ではそれを地球規模で考えるとどうだろう? と。イギリス国内に留まらず、アメリカやドイツ、世界各地のことを考えてみると、誰もが政治のせいでパーソナルな面で苦しめられているわけよね。そういう段階こそ、パーソナルが非常にポリティカルになる場面だ、と。
というのも、政治を再び正しい軌道に戻さなくてはいけないわけだし。多数の人びとの声を代弁させなくてはならないし、ただ単にキャリアを求め権力を手にしたがっていて、金儲けをしたいだけ、そういう手合いを代弁しているわけにはいかないだろう、と。政治はそういうものじゃないんだしね。たとえばここイギリスみたいに、わたしたちにいまある政治状況では、それこそ国そのものが崩壊しかねない。人びとは権力に酔い、経済面での利害を追求している。完全に狂っているし、まったく理解できない。だから、わたしとしても民主主義社会に生きているつもりでいるのが本当に難しくて──というのも、人びとはこれを民主主義と呼んでいるけれども、実際はそうじゃないわけで。……どうもわたしも、いまやすっかり政治的になってるみたいだわね(苦笑)?
■いまはそうならざるを得ないですよね。もっとも、どの時代でも困難な状況はあったでしょうが。
コージー:ええ。でも、いまは危機的状況じゃないか、わたしはそう思っているわ。
■すでに『D.o.A.』の頃にはメンバーそれぞれの分担作業になっていたTGですが、それでもグループとしてのパワーを発揮していたというのはすごいことだと思います。再結成のライヴもそうですが、TGにはバンドとしてのマジックがあったんでしょうね。そのことをあなたはいろんな言い方で表現しているように思います。言葉で捉えて表現するのはそれくらい難しいなにか、だったんでしょうか。
コージー:ええ、というか、みんなどう表現すればいいか困るんだろう、と思う。あれは言葉で言い表せないなにかだったし、どうして自分は聴いてああいう感覚を受け取るのか、その理由が見出せないものであって。というのも、ひとつの空間にたくさんの人間を集めて、そこでサウンドとエモーションを同時に相手にして取り組んでいると……だから、その場の全員が一緒にそれに関わっている、という。観客の側からもらうエモーショナルなフィードバック、反応、そしてエネルギーとが、プレイしている音楽に入ってきてエネルギーを与えてくれるんだしね。だから、全員が関与しているわけ。で、あれはとても不思議な感覚で……というのも、ある意味、自分自身から抜け出すようなセンセーションが生まれるから。それぞれと繫がり合うのではなく、むしろあのエネルギーそのものとコネクトしてひとつになっている、というか。あれは集団的なエネルギーだったし、なにもわたしたち4人だけの作り出すエネルギーではなかった。とにかく、口では説明しきれない(苦笑)。
■(笑)でも、本のなかであなたはかなりがんばってあれを描こうとしましたよね。
コージー:ええ、そうよね! だから、音楽やアートをやるときと同じで、とにかくただ、それが「起きる」という感じ。でもそれって本当に、それ以前に起きた様々なことの組み合わせから生じるものなのよね。で、それらを(ライヴの場という)短い瞬間のなかに凝縮させていくと、どういうわけかすべてがまとまって、完璧なものになる。そういうことを意図的に引き起こすのは不可能だったし、とにかくそれが「起こった」。というのも、その場面に至るまでに過去にやってきたいろんなこと、そしてその場での精神状態とが合わさってああいうものが生まれたんだしね。だから自らをオープンにして、様々なことが通過していく「導管」になる、ということ。ある意味、瞑想をやるときに似ているわね。
■TGにライヴ音源が多いのも、それだったんでしょうね。通常の「ロック・コンサート」ではなく、そのときの、その場の、人びとの記録だった、という。
コージー:そうね。
■ちょうどこの9月に再発される『Mission Of Dead Souls』は、あなたが本のなかでもっともお気に入りのライヴのひとつに挙げているサンフランシスコでのライヴを収録したものですよね?
コージー:ええ。
■どうしてあのギグが印象に残っているんでしょう? 第1期TGの終わりを告げた作品だったから、ですか?
コージー:それは、自分がほとんどもう外側から音を発しているような気がした、そういう感覚を抱いた唯一のギグがあれだったから、だわね。わたしは実際あの場にいたけれども、でもあの場にいないような感覚があった、という。ほんと、さっきギグについて話したことと同じだけれども、それまでやってきたことのなにもかもが組み合わさってライヴが生まれるわけよね。で、あれは(第1期)TGが最後にプレイしたギグだったし、そのぶんすごいものにもなった、と。
というのも、あそこですべてが、TGも、なにもかもが最後を迎えていたわけで。それにサンフランシスコ公演の前のロサンジェルスで、わたしたちは言い合いをしたわけよね──例の、あの問題人のせいで。あのときわたしたちは「サンフランシスコではちゃんと元に戻そう、まとまらないといけない」と話し合った。っていうのも、責任は自分たちにあったわけでしょ? あれがTGのラスト・ギグになることになっていたんだし、たとえお互いに対してどれだけ個人的な問題を抱えていたとしても、わたしたち全員が揃えばそれを越えたもっとすごいものになれるんだ、と。で、あのギグはまさにそういうものだったし、素晴らしかった。あのギグ以上にアメイジングだったものと言えば、TGが再結集して初めてやったアストリア公演に……それに、クリス&コージーの音楽を久々にやったとき、でしょうね。あの3本のギグが、わたしにとっては他のなによりも際立って記憶に残っている。
■その『Mission Of〜』ですが、あらためて聴くとTGからクリス&コージーへの架け橋的なサウンドにも思いました。たとえばシングル“ディシプリン”以降のテクスチャーやビートは、その後クリス&コージーに受け継がれていくものじゃないかと。
コージー:その意見は興味深いわ。というのも、あの“ディシプリン”のリズムというのは、これは本当の話だけど……ほぼもう、スロッビング・グリッスルがはじまったのとまさに同じ頃から存在していたのよね。
■ほう!
コージー:クリスの手元にはいろんな実験をやったテープが残っていて、彼は最近それらを聴き返したのね。で、あの“ディシプリン”リズムはそのテープに含まれていたし、あのテープは本当にごく最初期の、まだわたしたち4人がスロッビング・グリッスルとしてライヴを始める前に録ったもので。
■そうだったんですか。
コージー:だからある意味、これも円が一周して閉じた、ということじゃない? クリスがあのリズムをやり始めていて、それと同じ頃にTGもスタートしていたわけよね。ところがあなたにとってあの“ディシプリン”のリズムは、その後のクリス&コージーに至るヒントをもたらすことになった、という。だからほんと、クリスなのよね、物事を繋ぎ止めていた「岩」の存在というのは。
■でも、驚きですね。あのリズム/ビートは、その後のいわゆる「インダストリアル・ミュージック」のテンプレートになって、さんざんコピーされたわけですし。
コージー:ええ。本当に、パワフルなものよね。
■でも、それはTGの始まりから存在していた、と。
コージー:だから、棒立ちで動かない人間のリズムを無視することはできない、ということで(苦笑)。
■(笑)で、今回の3枚の再発で、ほかに『Journey Through A Body』と『Heathen Earth』を選んだのはどんな理由からですか?
コージー:あのすべてになんらかの繫がりがある、そうわたしは思っているから。この3枚のまとまりは、再発企画で同じグループに入れられた他のタイトルほどその理由は明確に映らないかもしれない。タイミングも異なる作品だしね。ただ、あの3枚はスロッビング・グリッスルについてなにかを語っていると思うし、でもそれはノーマルな文脈のそれではない、というか。だから、いつもとは違う……普通よく言われたり書かれてきたスロッビング・グリッスルに関するあれこれからは外れた作品群だ、と。だから、これらを同時に出すのは大切なことだと思ってる。
■「アザー・サイド・オブ・TG」とでもいうか、より即興性の強い、ライヴでルーズな側面を物語る作品、ということですか?
コージー:というか、聴き手にも気づいて欲しいのよね。これらの作品もまた、いわゆる「スロッビング・グリッスルのアイコニックな楽曲」と看做されてきた、そういう曲群と同じ時期に生まれていたものだという点を。だから──スロッビング・グリッスルは「これ」というひとつの存在ではなかったわけ。TGは“ディシプリン”とか“ウィ・ヘイト・ユー”とか、そうした1曲に集約されるものではなかった。『D.o.A.』でやったアンビエント調の楽曲や『20ジャズ・ファンク〜』(のラウンジ〜ディスコ解釈)にしても、わたしたちはハードコアなライヴ・パフォーマンスをこなしながら同時にああいうこともやっていた、その点を考えてもらいたいな、と。だから、スロッビング・グリッスルというのは人びとの考える「インダストリアル・ミュージック」というもの、それ以上のなにかだったのよね。要するに、機械工具だの金属製品を買い込むだとか、そういうことではない、と。
■(笑)ええ。
コージー:それにTGには、さりげないところもあったしね。だから、実験だった、ということ。わたしたちはあらゆる類いの実験をやっていた。たとえば金属塊をぶっ叩き、ハードなリズムを鳴らし、苦痛に喘いでいるようなヴォーカルをそこに乗っけるとか、それって安易過ぎでしょう? TGはそういうものではなかったし、もっとそれ以上のなにかだったから。
■『D.o.A.』そして『20ジャズ・ファンク』のレコーディング過程に関するあなたの本での記述は、TG1作目『セカンド・アニュアル・レポート』のそれに較べると割と簡潔であっさりしている気がしました。あの2枚にあまり文字数を費やさなかったのはどうしてでしょう。
コージー:それはだから、作ったアルバムごとに「我々はいかにしてこの作品を作ったか」みたいに詳述した本を書くつもりは自分にはなかったから。それとか、レコーディングのテクニカル面に関する解説だとか。わたしがあの本で語りたかったのは、わたしがこの世界で経てきた体験についてだった。で、わたしがこの世界で体験した様々なことは、「このアルバムの録音には何インチのテープを使った」とか「どんなタイプのテープを使ったか」といった点に終始するものではない、と。スロッビング・グリッスルの用いた技術だったり使用機材に関する分析は他の人間もやってきたし、これからもその分析は続くでしょうしね。わたしもクリスと一緒になることでそうした面を知ったけれども、詳しいところまではわからない。ただ、あの本はそうした点についてのものではない。あれはわたし自身の人生についての本だ、という。
■最後の質問になります。これまでの人生を振り返って、いろいろなピンチな局面があったと思いますが、やはり病に倒れたことは大きいと思います。そもそも、あなたが体調を悪くされていたこともこの本で知りましたが、最近はいかがでしょうか?
コージー:その日ごとに症状を抑えてコントロールしなくてはならない、そういう状態ね。だから、とても、とても厄介。というか、(本に書かれた2014年までの頃よりも)いまのほうがもっと難しいことになっている。
■ああ、そうなんですね……。
コージー:ええ。
■これについて質問したかったのは、あなたをなんとしてでも来日させたがっている友人がひとりいるからなんですよ。
コージー:でも、この症状があるからわたしには無理ね(苦笑)。行きたくても行けない、その主な理由が心臓の病気だから。
■長時間のフライトができない、と?
コージー:そう。それはいまや、アメリカも含んでいて(※2008年頃まではコージーもアメリカでツアーや展示をおこなっていた)。
■ああ、そうなんですか。
コージー:ええ。それに……だからこれまでも、ブラジルだとか、世界各地から招聘は受けてきたのね。ただ、とにかく肉体的に、わたしにはそれらの招きに応じることができない、という。そんなわけで、わたしは来る日も来る日も自分の体調を管理しなくてはならないし、ときにはとても体調が良い日もあって、「よし、不調は消えた!」なんて思うわけだけど(笑)、2〜3日したら症状がぶり返して、安静にして薬を服用しなくてはならなくなったり……。ただ、これに関しては自分でもあまりえんえんと話したくはないの。というのも、いわゆる、病弱でめそめそした、そういう人間にはなりたくないから。
そんなわけで、どうしてわたしが一部の招待や依頼を断るのか、そこを理解してくれない人は多いのよね。ただ、そうやって様々な招待を辞退している最大の理由は、実のところ、わたしが自分にあるエネルギーを使って仕事をやろうとしているから、であって。もちろん、ライヴだってわたしたちの仕事の一部ではある。けれどもいまの時点では、わたしは物事に優先順位をつけていかなくてはならない。というのも……とにかくいまのわたしにとって、(長旅を含む海外渡航は)肉体的にあまりに課題が大きいから。
■日本の側でファン・ツアーを組織して、あなたがパフォーマンスするのを観にイギリスに出向くしかないかもしれませんね。
コージー:(苦笑)そうね。ただ、イギリス国内のギグですら難しいかもしれない。というのも、多くの人間は気づいていないでしょうけど、ギグというのは……たとえば、わたしはもう夜遅くまで演奏し続けることはできない。ところが、イギリスではライヴのトリは普通、夜が更けてから出演するものと思われているわけで(※イギリスのコンサートではヘッドラインは早くて9時半頃に登場。クラブ系のイヴェントでは出演が深夜を回ることもある)。単純な話、わたしにはそれは無理。そんなわけで、誘ってくれてどうもありがとう、でも、お断りします、という。
■分かりました。今日は、お時間いただけて本当にありがとうございました。長々喋ってしまいすみません。
コージー:いいのよ、気にしないで。良い質問だったわ。
■ありがとうございます。本の日本語版出版が楽しみですし──
コージー:わたしも。実際に本を目にするのが待ち遠しいわ! 素晴らしいでしょうね。
■お元気になられることを願っていますので。どうぞ、お大事に。
コージー:ええ、ちゃんと自分の面倒は見るわ。あなたも、元気でね。
取材:坂本麻里子+野田努(2018年9月12日)
INTERVIEWS
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー
- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る
- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会
- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから
- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”
- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン
- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー
- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く
- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー
- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る
- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー
- interview with Gazelle Twin - UKを切り裂く、恐怖のエレクトロニカ ——ガゼル・ツイン、本邦初インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE