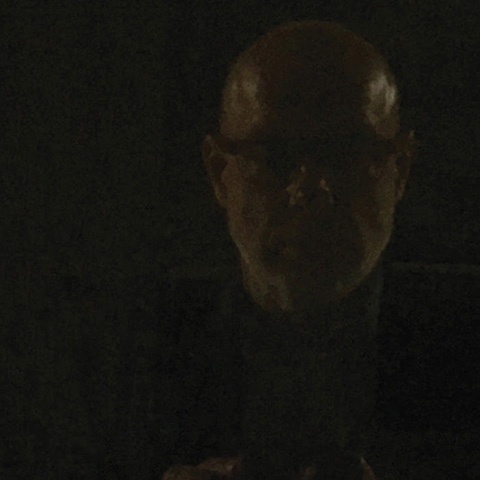MOST READ
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- 橋元優歩
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- Jlin - Akoma | ジェイリン
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- 『成功したオタク』 -
- interview with agraph その“グラフ”は、ミニマル・ミュージックをひらいていく | アグラフ、牛尾憲輔、電気グルーヴ
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- ソルトバーン -
Home > Interviews > interview with Tom Rogerson - 穏やかな岸辺、侵された楽器
ピアノ自体が体現するものは19世紀であり、それが人気だった時代なんだよね。〔……〕ピアノで新しいことをやろうと思うなら、やり方を工夫する必要がある。社会的にも政治的にも歴史的にもさまざまな背景を背負った、侵食された楽器なんだから。
 Tom Rogerson with Brian Eno Finding Shore Dead Oceans / ホステス |
■クラシックの海を航海するうちにジャズの島に辿り着き、また海に出てロックの島に寄り、気がついたら出航した岸辺に戻っていて、そのトイレでブライアン・イーノに出会った。
TR:ははは、正確にはトイレの外で、だけどね。僕は彼女を待ってたんだよ。もちろん、彼女は女子トイレに入ってて(笑)、出てくるのを待ってたらブライアンが通りかかった。トイレに行こうとしてたのかどうかはわからない。とにかくトイレの前だった。で、顔を見たらブライアンだったから、挨拶しちゃおうかな、と思って、したんだ(笑)。そして一緒にレコードを作るに至ったんだから、なかなかすごい展開だよね。当然だけど、まさかこんなことになるなんて、そのときは思ってなかった。ただ「ハロー」って声をかけただけで……なんて言ってるうちにこの話がとんでもなく美化されてしまうと困るのでいまのうちに言っておくと、彼と僕は同じ町の出身なんだよ。イングランド東部の、海に近いほんとうに小さな町の、ね。だから、いつかブライアン・イーノに会うことがあれば、それが話のきっかけになるとはずっと思ってた。彼は地元の有名人で、僕も音楽的にずいぶん影響されていたからね。もちろん大きな影響を与えてくれた音楽家は他にも大勢いるけど、そういう人たちと話す機会がもしあっても「あなたに影響されました。ありがとう」くらいしか言えないのに対して、ブライアンには「すごく影響されました。しかも僕もウッドブリッジ出身なんです」と言えるぞ、と(笑)。同郷っていうのは興味を惹くだろ? たとえそれっきりもう会うことがなくても、その場ではその話題だけで5分は盛り上がれるんじゃないか、と思ってた。じっさい、僕らはその場で5分は喋ったし、連絡先を交換してその後もつきあいが続いたんだ。僕がTTTの話をしたらライヴを観に来てくれたから、メンバーにも紹介した。僕らのライヴには何度も足を運んでくれて、バンドとの共演もしたし、彼がキュレイトしたフェスティヴァルに僕らを呼んでくれて、そこで一緒にセッションしたこともある。いつか個人的に彼と組んでやってみたいと、ずっと思っていたのが今回実現したんだよ。
■出会ったのは何年ですか?
TR:2012年だな。
■そうでしたか。じつはこの雑誌が2012年の終わりにブライアンにインタヴューしているんですが〔註:紙版『ele-king vol.8』。『AMBIENT definitive 1958-2013』にも再録〕、そのときに注目しているバンドを挙げてもらったらTTTの名前が出てきたんですって。
TR:それってたぶん、ノルウェーで彼がキュレイトしていたフェスティヴァルに僕らを出してくれたすぐ後じゃないかな。あのときの演奏は僕ら史上有数の出来だったんだ。
■ブライアンからの影響、もしくはブライアンの音楽の初体験はなんでしたか?
TR:これがすごく単純なんだけど、U2の『Rattle and Hum』のビデオなんだ。意外に思うんじゃない? 僕が5~6歳の頃、兄がU2に夢中で、うちに初めてのビデオプレイヤーが来たとき、わが家で初めて観たVHSのテープはU2の『Rattle and Hum』だった。『The Joshua Tree』のツアーを網羅したやつ。ほとんどモノクロで、半ばでいきなり画面が真っ赤になる、あのシーンに圧倒されて。こうして話しているだけでも鳥肌が立つくらいなんだけど……とにかく、その真っ赤な画面に“Where the Streets Have No Name”のイントロが流れてくる。『The Joshua Tree』の1曲目だ。美しいVX7の音。ブライアン・イーノが録音した音だ。あのレコードは彼がプロデュースしたんだからね。それがほんとうに印象的で、赤い画面に彼らのシルエットが浮かび上がり、ステージに上がってきた彼らが位置につくとラリー・マレンが叩き始める……いや、タタン! と鳴らして、そこでストップするんだ。そこであのアイコニックなジ・エッジのギターリフが鳴り始めるんだ。ティリリリリ~♪ で、ドラムがタタンタタンタタン、ドゥドゥドゥドゥ、タンッ! ときて、いきなりスタジアムが明るくなる。スタジアム全体が明るくなって、ヘリコプターからの映像に切り替わり、そこがアメリカンフットボールのスタジアムで、8万人だかでビッシリ埋まっているのがわかるんだ。もう最高。そしてバンドは“Where the Streets Have No Name”の演奏に突入、と……、その影にブライアン・イーノがいたことは当時は知らなかったけど、あのなんとも劇的な瞬間はずっと印象に残っていて、大好きだった。僕の兄は7歳、いや8歳年上なんだけど、U2が好きだったからブライアンが関わっていることも知っていて、「このブライアン・イーノって人はウッドブリッジ出身なんだぜ」と教えてくれて、以来僕も「『The Unforgettable Fire』や『The Joshua Tree』や『Achtung Baby』はこの町から生まれたんだ!」ぐらいに思っていた。ブライアンにはロジャーっていう弟がいて……、ブライアンのお母さんは2005年頃に亡くなっているんだけど、彼女がずっとウッドブリッジ在住だったからイーノ家の男の子ふたりもあの町の育ちで、ロジャーに至っては4×4の車のナンバープレイトに「ENO」って書いてあった。「R15ENO」とか、そんな感じだったと思う。
■へえ……(笑)。
TR:子どもの頃、「ENO」って書いてあるナンバープレイトの車とすれ違うと大騒ぎしたもんだよ。
■すごいですね。小さい町と言いながら、ずいぶん音楽的な町だったんじゃないかと思えてきました。
TR:考えるとすごいよね。ブライアンは運転しないから、そんなナンバープレイトはおろか、そもそも車を持ったことがないらしいけど(笑)。
■そうですか、U2が最初だったんですか。よく知られている彼のアンビエント的なものではなくて。
TR:アンビエント・ミュージックを初めて知ったのは16歳のときで、アメリカのバング・オン・ア・キャンというクラシックのグループだった。『Music for Airports』のカヴァーをアコースティックでやっていたんだ。ロイヤル・アルバート・ホールのBBCプロムス〔註:プロムナード・コンサート〕で、生楽器で演奏していた。まだ僕もクラシックに入れ込んでいた時期で、(BBCの)ラジオ3を熱心に聴いていたら、そのプロムスが流れてきて、僕がピアノでやっていたインプロっぽいことと少し似ているという意味でも驚いたし、刺戟的だった。その後、あんな感じの音楽を書いてみようと努力した記憶もある。『Music for Airports』のピアノの旋律はロバート・ワイアットが弾いていたはずだけど、いまだに僕には印象的で参考にしたくなるんだよね。そこからスティーヴ・ライヒにも興味を持ったし、ロンドンの音楽仲間……さっき話したインディーズのシーンの連中に教えられてデイヴィッド・ボウイとかトーキング・ヘッズとか、ブライアンが手がけてきたいろんな音楽のおもしろいコラボレイションを知ったんだ。デイヴィッド・バーンもそうだし、ロバート・フリップとか、ジョン・ハッセルとか、すごいのがたくさんあった。そうこうするうちに、僕も立派なブライアンおたくさ。
■(笑)。
TR:そうなったのは20代になってからだけそね。その前の、8歳と16歳でじつは彼の音楽に遭遇していた、ということ。
■今回、作業はどう進めたんですか? じっさいにブライアンと同席して一緒にやった?
TR:そうだよ。ロンドンにある彼のスタジオで、アップライト・ピアノが1台と、彼が試してみたいと言っていたモーグ・ピアノというやつを、いい機会だから使ってみようということで持ち込んで、彼は僕と背中合わせに近い形で座って……お互い直角ぐらいの位置かな、手を伸ばせば届く距離だよ。その状態で僕はピアノを弾き、彼はデスクトップ・コンピュータをいじりながら音を作ったりミックスしたりしていた。僕が弾くピアノの音を彼が録って……ピアノからのMIDIシグナルを彼がコンピュータに録音して、その後、加工していったんだ。たしか作業は15日間。すごい量の音楽を録音したよ。
■すみません、もう予定の30分を過ぎているんですが、まだ大丈夫ですか? あと10分でもいただけたら嬉しいんですが。
TR:ぜんぜん大丈夫だよ。僕はいつまでだって喋っていられる。
■(笑)。ありがとうございます。助かります。えぇと、ブライアンが試してみたかったというのはモーグ・ピアノ、でいいですか?
TR:うん。モーグ・ピアノ・バー、かな、正確には。
■有名なプリペアド・ピアノではなく。
TR:そう。モーグっていうあの楽器の会社が2003年……だったと思うけど、に作ったやつで、ピアノの上に設置してアコースティック・ピアノをデジタル・ピアノに転じるという……。でもプリパレイションはまったく絡んでいない。弦には触れないんだ。鍵盤に触れるだけで。なんか、不思議なセンサーだけで技術的にはじつは極めて基本的なものらしくて、2003年に製造したものの評判はいまいちで、数もあんまり作られなかったらしいよ。たまたまブライアンが1台持っていたんだけど……。
■彼はうまく使いこなしていました?
TR:と、思う。なかなかクールな機材だった。うまく機能しないというか、ピアニストからすると不安定で使いづらい。単純な仕組みなのに気分屋で、当てにならないから使い勝手はよくないね。
ケータイに記録しておこう、なんて思った途端に本質から外れて台なしだ。体験することの価値、その場にいることの価値、その瞬間にそのミュージシャンがやっていたことは瞬時に消えて二度と戻らないという刹那の価値。
■アルバムの構成ですが、最初のほうに美しいピアノのメロディが印象的な曲が続き、終盤に向けて実験性の高い曲が出てくるようですね。これは流れを考えて意識的にそうしたんでしょうか?
TR:スタジオで15日間作業して、毎日何時間もやっていたから……基本すべて即興で、終わったところで編集というか、音量調整したりすることはあっても、ほとんどはその場で僕が演奏したものそのままなんだ。で、すべて曲が揃ったところでアルバムに仕立てるのは僕に任された仕事だった。だから、ぜんぶ持ち帰って必死でやったよ。要は曲選びってことだけど、ふたりで好きなようにやった結果だから、ものすごく幅広い音世界が網羅されていて、下手したらちょっとゴチャゴチャした印象のアルバムになってしまうんじゃないかと僕は懸念した。ありとあらゆることをやっていて、おもしろいけどとっ散らかってしまうんじゃないか、と。そこで一体感を持たせるために追求したのは、ブライアンの音楽言語である彼の音世界……これはつねにけっこうな一貫性があって、オルガンだろうがベルだろうが徹底しているんだけど、僕の側の音世界は僕の感覚によるメロディでありハーモニーなので、それを彼の世界と擦り合わせて全体としての説得力を持たせなければ……と、まあ、それが音の整合性なわけだけど、他に曲を並べたときに自然な曲線が描かれるような……しかるべきところで頂点に達して、ストーリーを感じさせながら聴き手を旅に誘うような、どこかへ連れ出してしまうような……、いや、違うかもしれないな……、おかしな話だけど、あちこち旅して回って最後には出発した場所に戻っていくという感じを出したかったのかもしれない。ぐるっと長い環状線を歩いて、出発点に戻ってきたときに、最初とはまったく違う新しい視点で同じ場所を眺められるようになっている……、旅をしてきたおかげで、ね。まあ、そんなことをそこまで意識して曲順を決めたわけではないけれど、後から考えるとそんな感じがする。おっしゃる通り、穏やかに、ピアノ重視な始まりから段々とエレクトロニックになっていく中盤、そしてけっこういろんなことをやった上で最後にまた穏やかなエンディングに辿り着く、という感じかな。
■穏やかな岸辺、ですね。タイトルが示すように。
TR:そういうことだね。
■ピアノはとくにクラシックの分野では昔から主要なメロディ楽器でしたが、発明された当初は非常に馴染みのない、いまでいうデジタルな感触の響きと受け止められたのでは? と質問者は言っているのですが、どうでしょう、意味はわかりますか?
TR:あぁ、もちろん! わかるよ。その通りだと思う。いい指摘だ。まず、ピアノが音楽に与えたインパクトは驚くほどラディカルなものだったはずだ。ああいう形でスケールを鳴らせる楽器が登場したんだから。バッハもピアノでは作曲していない。彼が使ったのはキイボード……クラビコードもしくはハープシコードだ。バッハの音楽は非常に音数が多い。タンタンタンタンタンタン……♪ と、ぎっしり音で埋まっている。考えてみるとそれはアルペジオだろう。モーツァルトやハイドンですら、あるいはスカルラッティあたりの音楽もティラリラティラリラ……♪ と延々と繰り返すことをやっているが、あれだってつまりはアルペジオさ(笑)。おもしろいよね。ショパンだって、ショパンというとみんな叙情的なメロディで有名だと思っているだろうけど、彼の音楽には音の連なりがものすごく多い。いわば16分音符だ。古いエテュードなんか、ティラリラリラ……♪ って(笑)、あれをピアノが支えたことは驚くべき音盤を……音世界を得たことになる。うん、そのジャーナリストの指摘はまったくその通りだと思う。現代におけるシンセサイザーのように、音的にいろんなことを可能にしてくれたはずだ。とくにペダルを使うと巨大な音を鳴り響かせることができるし、サステインも効くし、それ自体がオーケストラだという印象を与えたんじゃないかな。それが一般の人の居間にふつうに置かれるようになり……、いまのピアノの興味深い点は、ピアニストとしては逆にそれが古代の技術であることを意識すべきだということ。もちろん、いまもって優れた楽器であり、インターフェイスが機能していることは後のキイボードもシンセサイザーもピアノのそれを模していることからも明らかだけれど、ピアノ自体が体現するものは19世紀であり、それが人気だった時代なんだよね。エレクトリック・ギターが50年代から60年代、70年代あたりの新しさを象徴しているのと同じだ。いま、エレクトリック・ギターを弾きながら新たな文化を創造している感覚を味わうのは難しい。ジミ・ヘンドリックスがしたように。ね? ピアノにも同じことが言えると僕は思う。ピアノで新しいことをやろうと思うなら、やり方を工夫する必要がある。社会的にも政治的にも歴史的にもさまざまな背景を背負った、侵食された楽器なんだから。そう考えると、これだけピアノ音楽が溢れている現状は興味深い。ここ数年のピアノ音楽は……、こちらの状況で話しているけれどもおそらく日本もそうだろう、日本は昔からピアノに親しみがあるから。
■ヤマハの国ですから。
TR:あはは、そうだった。間違いなく最高のピアノを造っている。シンセサイザーも最高だと僕は思うが……、まあ、それはいいとして、ヨーロッパではピアノ音楽の人気の高まりがこの数年顕著でね。たぶんそれは時代を超えて人間に共鳴する馴染み深い音……アコースティックな音をいままた人びとが求め始めていることの証なんじゃないだろうか。デジタル・ライフを象徴するソーシャル・メディア的な、刺戟の多い複雑な混乱した世の中からの逃避、というか。それがいま、より静かな(stiller)ピアノ音楽の再評価という形で表出しているんじゃないか、と僕は思うんだけど、どうだろう。だとしたら、その嗜好は僕にもよくわかる。ただ、僕のレコードがやっていることはそれとは違う。僕のレコードは相変わらず……、なんて言うんだろう、僕のレコードにはデジタルが存在しているから……、なんだろうなあ、べつにラディカルなことをやって驚かせてやろうとか、そんなつもりはぜんぜんないけれど、なんかちょっと他とは違うことをやりたかったんだよね。自分なりの出口を模索した結果、というのかな。ピアノで何ができるのか、と考えた結果、こういう突破口を見つけた、と。TTTについて話したときに言ったように、僕はつねに電子音楽をライヴでやる手法に興味を持って探求してきた。どうすればライヴで優れた電子音楽を披露できるのか。電子音楽はそもそもライヴなものではなかった。シーケンサーやサンプラーやドラムマシーンといった機械を操作して動かすわけだけど、そこに人間という要素が入り込んできて電子音楽を演奏しようとしたら……あるいは電子音楽的なスタイルやサウンドや技術で演奏しようとしたらどうなるか、というのが僕のかねてからの関心事で、ドラムマシーンのように完璧なプレイができるドラマーなんていないし、完璧じゃないがゆえに人間を補おうとしてAIだなんだって洗練された技術が追い求められるのは、それはそれでけっこうなことだが、だったら人間にしかできないことってなんなんだろう、と思うよね。
■不完全であること、ですよね。
TR:そうだよね。だから僕らのレコードではそれを許容することにしたんだ。
■このレコードもいずれライヴで演奏することを想定して作っていたんですか?
TR:もちろん! 当然だよ。というか、もうやってる。このアルバムはライヴ映えしそうだ。もう少しするとビデオが公開されるから、それを観れば具体的にどうライヴで展開しているかわかるだろう。
■そうなんですね。
TR:あと2週間くらい、かな。さっきも言ったようにレコードは即興演奏を文字通り記録(record)したものだけど、曲のもとになっているコンセプトの多くは永遠に拡大可能なんで、どんどん発展させて演奏することができるんだ。コンサートでは、たとえば最初の曲で最初の音を弾いたら、記憶しているその曲を数分弾き進め、どこかの時点でさらなる即興に転じる。あとはどうなるかわからない。もとが即興なんだから、1音1音完全に再現したところで無意味だ。その日のその瞬間にしか生まれえなかった曲なんだから、その精神を再現するという意味でライヴこそが僕にとっては生命線なんだ。レコーディング以上にライヴは興味深い。一度作った曲を世界へ持ち出して、行く先々で、みんなが観ている前で、さらに発展させてみせる。それがライヴの醍醐味。もちろん、そうかけ離れたものにはならないよ。でも、毎晩やるたびに曲が変わるという楽しみや、お客さんに彼らだけの経験をしてもらえるという喜び。曲単位ではなく、一晩ごとにそのときしか存在しない何かを体験するという、まさにそれこそが即興だよ。デジタル文化においては、撮った写真がぜんぶそのまま永久に保存されるけれど、即興は瞬時のものだけにものすごく集中力を要するし、その場にいなければ味わえないという、いまの文化に逆行するとても価値のある体験だと思うんだよね。ケータイに記録しておこう、なんて思った途端に本質から外れて台なしだ。体験することの価値、その場にいることの価値、その瞬間にそのミュージシャンがやっていたことは瞬時に消えて二度と戻らないという刹那の価値。やってる側もだけど、お客さんも思い切り集中しないと体感できないだろうね。
■長らくありがとうございました。日本でもライヴを聴けますように。
TR:ああ、ぜひそうしたい。僕はまだ日本に行ったことがなくて、TTTもある程度ファンが日本にいたようだけど機会がなかったから……うん、日本に行けたら楽しいだろうな。音楽的に日本のカルチャーはすごく進んでいる印象がある。遠くから見ている印象だけど、なんだかすごくおもしろそうだ。とにかく、話を聞いてくれてありがとう。
質問・文:小林拓音(2018年2月28日)
| 12 |
Profile
小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。
INTERVIEWS
- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について
- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩
- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー
- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由
- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」
- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー
- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る
- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会
- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから
- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”
- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン
- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー
- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く
- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー
- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る
- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー
- interview with Gazelle Twin - UKを切り裂く、恐怖のエレクトロニカ ——ガゼル・ツイン、本邦初インタヴュー


 DOMMUNE
DOMMUNE