MOST READ
- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー
- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く
- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回
- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈
- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン
- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について
- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く
- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から
- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売
- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース
- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS
- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -
- Rafael Toral - Spectral Evolution | ラファエル・トラル
- 『成功したオタク』 -
- Bobby Gillespie on CAN ──ボビー・ギレスピー、CANについて語る
- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日
- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー
- ソルトバーン -
- Claire Rousay - a softer focus | クレア・ラウジー
Home > Regulars > 女たちの暴力映画列伝 > 第1回 序文~タランティーノが描く女たち
女の暴力映画
いま、女性と暴力の問題を書くのはことさら慎重さが必要になるので、とても怖い。久々に女性にまつわるテーマで新連載を始める機会をいただいたが、うかつなことを書いてしまったらどうしようとビビリ腰になっている。とりあえず第一回目なので最後まで読んでいただけると嬉しい。
映画で描かれた「女の暴力」。とはいっても今回は、女が振るわれる暴力についてではない。もうそんなものは映画史に溢れかえっているし、改めて解説されるのも読者は疲れるだけだろう。現在でも現実に、女が様々な形のハラスメントや抑圧、そしてまさに肉体的な暴行を受ける事案が日常的に起こっている。文明が進んだらマシになるのかと思いきや、全然性差別は解決していないうえ、それを声に出した女性がSNSなどで受ける二次的なハラスメントを、リアルタイムで見つめてさえいる時代だ。
そんな暗雲の下で暮らしながらも女が抵抗し、戦い、もちろん良いことだけではなく利己的な欲望で他人を傷つける振る舞いは行われてきた。現実と同様に、映画も女が肉体的にも精神的にも他人にヴァイオレンスの矛先を向ける瞬間を描いている。それは華麗なアクションであったり、現実の我々にも訪れそうなリアリティに満ちたものだったり様々だ。
映画業界は男性主導の世界である。だからこそ2017年にはハリウッドで驚くような、完全に犯罪の域である悪質なセクハラが明るみになり、それがまかり通ってきたことが改めて認識された。でもそういった報道に対して、逆に被害者をバッシングする反応が多いのも目についた出来事だ。そんな齟齬がある中で、男性の作り手が撮った女性主演のアクション映画は、本当に女性的なアクションといえるのかは判断に悩んでしまう。そもそも男性の監督や脚本家によっても、女性心理にうとい人/感受できる人は様々な度合いがある。それに女性監督が作った女性アクションだったら、正統だとか真実だともいえないだろう。女性なら女性心理が完全に汲めるのか? という疑問もある。それにわたしたち女性だって、長年男性が作った男性主体のアクション映画を観てきているので、映画ではそのことに慣れてしまっているのだ。これは男性であっても同様で、現実と表現は違うため、もし格闘技の経験のない人が「アクション映画を撮れ」と言い渡されたら、自身の経験から引き出すのではなく、これまで観てきた映画のヴァイオレンスを参考に表現を組み立てていくことになるだろう。日常の経験でも、見栄えのするアクションに街中ではそうそう遭遇しないものだし。
暴力の多面性
そして暴力は肉体的なものに限らない。ひとは裏切りや嘘でも心にダメージを受ける。マスコミによる著名人の不倫報道はいっとき病的なほど過熱していた。それは視聴者や読者の関心をひいて激しいバッシングを引き起こしたが、不貞がかまびすしく非難を浴びるのは、自分の身に受けることを想像しやすい精神的な暴力のひとつだからだ。わかっていて人を裏切るのはひどい行いである。とはいえ当事者にも事情は色々あるだろうし、不倫は申し開きをするほど「反省していない」といった反発をくらうため、甘んじて批判を受けるしかない。そこに付け込んだ報道のあり方や過剰なバッシングも、当事者に与えるダメージを見越した一種の暴力である。これらのような精神を傷つけ心を壊す行為も、やはりヴァイオレンスの形として見過ごせない。
映画において、女が暴力を振るう場面は娯楽だろうか。確かにシャーリーズ・セロンが戦う姿は、問答無用にかっこよくて魅了される。それでも女が振るってはダメな暴力という表現もあるのだろうか。それらの線引きは何を根拠になされるのか――考えると頭がグルグルしてしまうことばかりだ。だから映画の中で女優が繰り出すキックを観つつ、改めて女性と暴力についてゆっくり考えてみよう。
変遷するタランティーノの女性と暴力
タランティーノはなんといっても『レザボア・ドッグス』(91年)を封切りで観て以来の付き合いという感がある。ハーヴェイ・ワインスタインの事件で名をあげたり下げたり色々あったうえ、新作がマンソンファミリーによるシャロン・テート殺害事件の映画化というのも物議を醸しそうだ。それでも完成すれば必ず観にいくだろうし、これまでもすべての作品は劇場で観ている監督である。
登場人物が男だけの映画『レザボア・ドッグス』でメジャー監督デビューしたクエンティン・タランティーノは、現在では女性アクションの監督というイメージも強い。ユマ・サーマン主演の『キル・ビル』2部作(03年、04年)は、とても虚構性の強いアクション作品だ。ヒロインの“ザ・ブライド”は、元々暗殺者集団に所属する凄腕の殺し屋だった。しかし足を洗い、普通の女性として人生を送ろうとした矢先に、かつてのボスであり愛人であったビル(デヴィッド・キャラダイン)の命令によって、仲間の殺し屋たちに夫とお腹の子どもを殺され、彼女も死の縁をさまようことになる。映画は長い昏睡から目覚めたザ・ブライドが、彼女の人生を台無しにしたビルと殺し屋たちへ、復讐を果たしていく物語だ。
荒唐無稽な大殺戮に潜ませた愛憎劇
1作目の見せ場は、伝説の名刀を求めて日本を訪れたザ・ブライドが、青葉屋という料亭で繰り広げる殺戮劇だ。この一連のシーンで、ザ・ブライドはブルース・リーを彷彿とさせるトラックスーツを着ているし、復讐の的であるオーレン・イシイ(ルーシー・リュー)の用心棒が鉄球使いの女子高生であったり、イシイの配下“クレイジー88”が日本刀を持った学生服集団であったりと、元々リアリティは意識していない設定である。
男性監督や脚本家にとって主人公が女性であることは、地続きで想像できてしまう男性主人公と比べて、虚構として想像を膨らませやすいのだろう。今では女性アクション映画といえば『キル・ビル』は必ずタイトルがあがる。ザ・ブライドの殺した人数のインパクトが記憶に残るのもわかりやすいし、そんな過剰な復讐劇の動機が、最終的には母性に集約されていくのも、強い女性を想像する際のふんわりした理由やイメージの例だ。
男性の主人公が娘の復讐のために立ち上がる映画だと、地に足のついた作品が次々と頭に浮かぶ。男が考える男の復讐劇は、リアリズムから逸脱しない。しかし女性の復讐劇である『キル・ビル』は、大量殺戮の面白さを見せることが一番の目的であって、動機に母性を持ってくるのはもっともらしく見せるためだけに思える。むしろビルとザ・ブライドの間にある、愛と憎しみの交じり合ったメロドラマ性の方が、言い知れぬ動機として魅力的であり物語を豊潤にしている。「愛しているけれどもくびきから逃れたい」「愛するあまり許せないから殺したい」「愛が招いた因果応報を素直に受け入れる」という感情の交錯が、本作を荒唐無稽なだけでは終わらないドラマとして成立させていた。
より生身の暴力へ
その後の女性をヒロインに迎えたタランティーノ作品は、反動のように「女にも可能なヴァイオレンス」を追求していく。『デス・プルーフ in グラインドハウス』(07年)は、『キル・ビル』でユマ・サーマンのスタントをしていたゾーイ・ベルが、彼女自身として主演を務める。改造車を使った殺人鬼スタントマン・マイク(カート・ラッセル)に狙われた、ゾーイをはじめとする女性だけの車。なんとか逃げ延びたあと、命の危険にさらされた彼女たちは怒りに燃えて復讐に出る。本作でみせるゾーイ・ベルの身体能力が素晴らしい。ボンネットに掴まったままのカーチェイスや、彼女が走り出す車へ手にパイプを持ったままスルッと滑り込むように箱乗りする場面など、本当にゾーイ自身が演じているリアリズムによって、有無を言わせぬ効果をあげる。
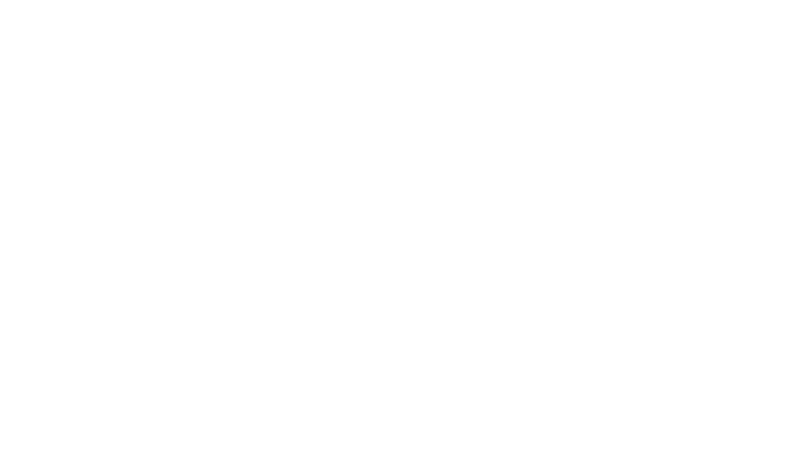
©2007 The Weinstein Company, LLC. All rights reserved.
本作はマイクの凶行を見せるための二部構成になっていて、まずは酒に溺れエロティックな危険を冒す女性グループが登場する。前半では彼女たちと、「グラインドハウス」のカップリング作品『プラネット・テラー in グラインドハウス』の主演ローズ・マッゴーワンが、被害者として恐怖に慄きむごい目に遭う。
タランティーノの映画は被害者が男性であっても、監禁の恐怖や、観ていて痛みや凄惨さを強く覚える時がある。映画に耽溺してきた彼の「映画は虚構」という骨身にしみる感覚ゆえか、表現が細やかなあまり暴力シーンには過剰なサディズムが漂っているようだ。確かに映画は所詮作り物にすぎない。だから暴力表現において、創造の面白さに興味が傾くのも当然だ。だが同時に、スクリーンで何が起ころうと真に受けない感性が試されるような、逃げ場のなさや妙に皮膚感覚に迫る暴力性には、観ていて時々居心地の悪い気持ちがする。
『デス・プルーフ』はそんな陰惨さと、白昼の勧善懲悪という晴れやかさが共存する作品だ。現実にスタントをこなせる女性が等身大のアクションを演じるのは、荒唐無稽な『キル・ビル』と正反対のアプローチである。『デス・プルーフ』で女が発揮する暴力は、「女性でも出来ること」の域を押し広げるリアルな強靭さがあり、これはゾーイ・ベルの存在なくしてありえない生身のアクションだった。
フィルムを操る手
『イングロリアス・バスターズ』(09年)ではまたアプローチを変え、女性にも可能な、策略による大掛かりな殺戮劇が描かれる。第二次世界大戦中のナチス統治下のフランス。かつてユダヤ人狩りによって家族を皆殺しにされたショシャナ・ドレフュス(メラニー・ロラン)は、一人だけ逃げ延び、今ではパリの映画館で働いている。ドイツ軍の狙撃兵フレデリック・ツォラー(ダニエル・ブリュール)が街でショシャナを見染めたのをきっかけに、ナチスのプロパガンダ映画が彼女の映画館でプレミア上映されることになった。その日はヒトラーをはじめとする、ナチスの最高幹部たちも集まるという。機を見たショシャナによるレジスタンスの幕開けだ。
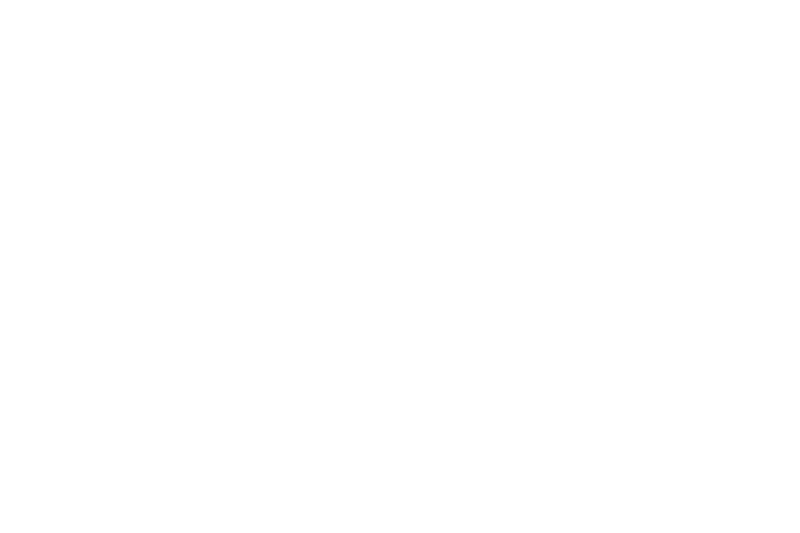
Film (C)2009 Universal Studios. ALL RIGHTS RESERVED.
彼女と同時進行して、アルド・レイン中尉(ブラッド・ピット)を中心とする連合軍特殊部隊のナチス狩りもいる。彼らは男の子らしく得意技がバットのフルスウィングだったり、ナチであった身分を戦後に詐称できないよう、額へハーケンクロイツを刻み込んだりする。相対して、ショシャナが用いるのは手間暇をかけたフィルムでのメッセージと炎だ。この映画で一気呵成なヴァイオレンスシーンを繰り広げるのはショシャナだが、それは肉体を酷使するアクションではない。彼女が操るのはフィルムやスプライサーや映写機だけだ。そしてプレミア上映はショシャナ以外にも複数の思惑が交錯したことによって、甚大な被害をナチス陣営に与えることになる。
ここでも特殊部隊やレジスタンスの活動以外に、フレデリック・ツォラーの恋心がショシャナの復讐劇に別のドラマを生むことになる。フレデリックの熱烈さは復讐に燃えるショシャナに絶好の機会をもたらすと同時に、彼女の家族を殺したハンス・ランダ大佐(クリストフ・ヴァルツ)との再会というショッキングな出来事も引き起こす。クライマックスでも彼はショシャナの企みの妨げとなる。フレデリックは執拗にショシャナを追い回し、プレミアの夜も最悪のタイミングで映写室に入り込もうとする。だがその後に起こる男女のアクシデントでは、ショシャナが思わず行動に出てしまった「復讐の邪魔だてを消す」行為だけにはとどまらず、敵とはいえ自分に恋している男を心配する心を起こしてしまう。ここで男女の姿を切り取る俯瞰のカメラワークは、とても悲劇的でロマンティックなものだ。タランティーノは『キル・ビル』や『ジャンゴ 繋がれざる者』(12年)においても、ドラマを持つ人物の死体の写し方が滅法うまい。いま活躍している監督の中で、死体の転がり方に毎回ハッとさせられ、落涙してしまう演出力ではタランティーノが最高峰だろう。その悲哀が本作においても、後を引く余韻のあるものとなる。
より生々しい暴力へ
群像劇『ヘイトフル・エイト』(15年)の主要人物の中で、女性はジェニファー・ジェイソン・リー演じるデイジー・ドメルグだけだ。彼女は首に賞金をかけられた極悪人で、屈強でしたたかな賞金稼ぎの男たちを向こうに回して引けを取らない。
彼女が映画の中で振るうのは、汚い言葉や罵詈雑言による暴力である。デイジーは登場した時点ですでに目の周りにあざができており、賞金稼ぎのジョン・ルース(カート・ラッセル)に手ひどいやり方で捕らえられたのがわかる。それでも彼女は落ち着いており、新たに出会った賞金稼ぎのマーキス・ウォーレン(サミュエル・L・ジャクソン)に、ニタニタと笑いながら「ニガー」と侮蔑的な呼びかけをする。住んでいる世界が元々暴力に満ちているから、殴られる恐怖の限界値が最初から無いに等しく、歯が折れるほど殴打されてもふてくされる程度の反応しか示さない。
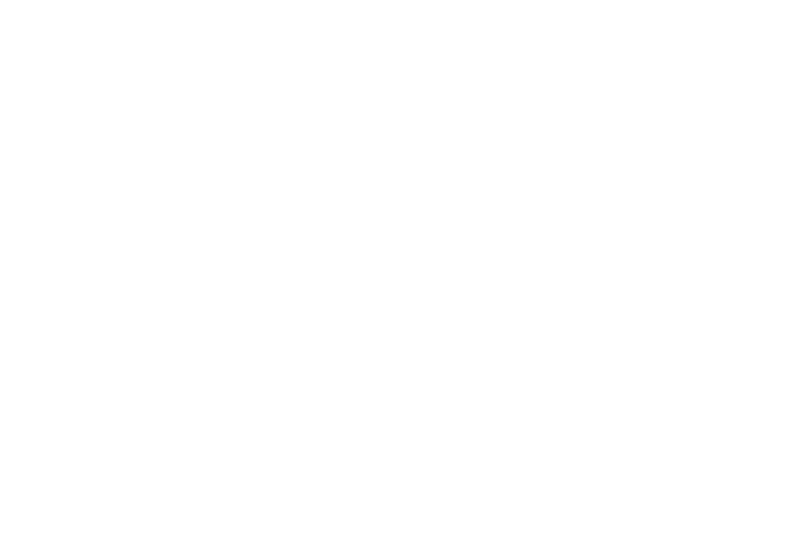
© Copyright MMXV Visiona Romantica, Inc. All Rights Reserved. Artwork © 2015 The Weinstein Company LLC. AllRights Reserved.
この映画の中で一番不穏な空気を放ち、殺人すら気にも留めない匂いがするのはデイジーだ。クセモノな俳優たちが揃い、それぞれの役柄が並々ならぬアウトローとしての背景を背負っている中で、拳をあげたり銃を撃ったりしないのに、一番暴力的な存在感を放つ女。平然と人を侮蔑し、窮地に立った人間にひとかけらも憐れみを抱かない、根っからの悪党という新たな暴力の体現である。これまでタランティーノが描いてきた女たちは、暴力を振るうにあたって、徐々にみずからの肉体を使う機会を減らしてきた。そして『ヘイトフル・エイト』は芸達者なジェニファー・ジェイソン・リーを迎えることで、ナイフのような言葉と、邪悪な人間はそこにいるだけで暴力性を醸しだす状態を描いた。
女の首、という点でも本作は興味深い。殺人にまつわる「首」と「距離」は意味を持つ。手で首を絞めるという行為は当然至近距離で行われ、エロティックなプレイでも試す人々がいるほどだ。そもそも密接な姿勢には性的な気配が漂うのに、なおかつ殺すには凄まじい力が必要なため、殺人者は被害者と強いつながりを持つのは避けられない。それは恐ろしいほど、感触や感情に強い記憶を残すだろう。しかし絞首刑となると、ロープの介在は処刑人を死ぬ者から物理的に遠ざける。それは人の死を感覚に響かせないための冷酷な距離だ。映画においてはロープだけでなく、表現そのものもカメラがかなりの引きになったり、編集でショットが切り変わったりして、死ぬ過程を露骨に見せることは避けられる。
だが『ヘイトフル・エイト』は処刑について、かなり踏み込んだ表現がされる。男が二人がかりでテコの原理を応用し、女の首にかけた縄をズルズルと引き上げていき吊るす。むごたらしいようだが、吊るされるデイジーはか弱く憐れな者という域を超えた邪悪さに満ちているので、観ていてもそういった心苦しさが少ない。カメラも近くて、彼女を引き上げるための労力が生々しい人の体重であるのを伝える。それと同時に、処刑のように落下での首吊りではないぶん、じりじりと引き上げられる姿は、彼女の邪悪さがまだ地から離れることを拒否するような悪魔的な重みに見える。デイジーの暴力性を見せるためには手段もカメラも編集も、ここまでしないと釣り合いがとれないほどなのだ。
アクションは荒唐無稽なほど、スタントマンやCGの処理を漂わせて、誰が演じようと構わないものとなる。だからタランティーノの変化は面白い。スター俳優から、現実にそのアクションをできる女優、または女でも振るえる暴力という現実味への変遷。これは女性を描く際にフィクションへと追いやらず、男性と同じような存在としてキャラクターを見つめている証であると思う。
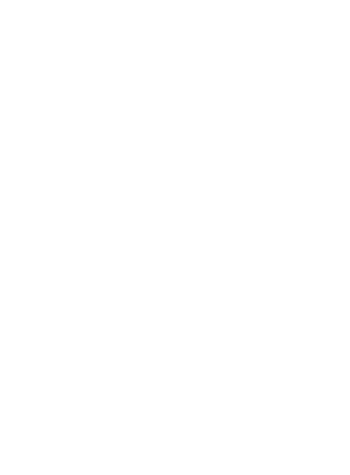
「デス・プルーフ」発売中。
Blu-ray 1,886円(税別)/ DVD 1,429円(税別)。
発売元:ブロードメディア・スタジオ
販売元:NBCユニバーサル
(C)2007 The Weinstein Company, LLC. All rights reserved.
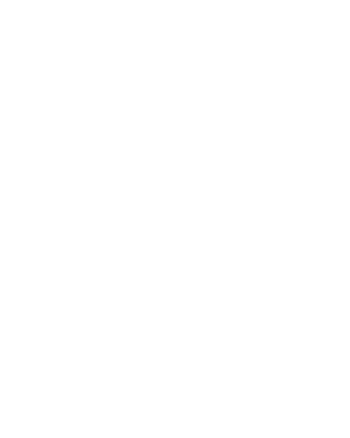
『イングロリアス・バスターズ』
Blu-ray:1,886 円+税/DVD:1,429 円+税
発売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント
Film (C)2009 Universal Studios. ALL RIGHTS RESERVED.
**2018年6月の情報です。
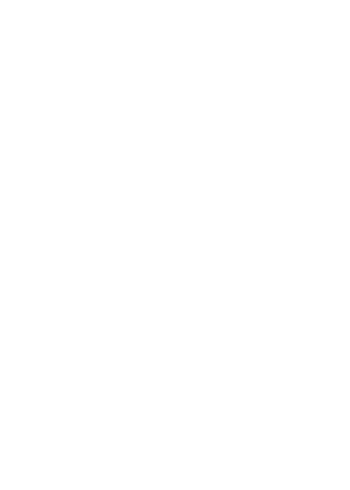
『ヘイトフル・エイト』
価格:¥1,143(税抜)
発売・販売元:ギャガ
© Copyright MMXV Visiona Romantica, Inc. All Rights Reserved. Artwork © 2015 The Weinstein Company LLC. AllRights Reserved.
Profile
 真魚八重子/Yaeko Mana
真魚八重子/Yaeko Mana映画評論家。愛知県生まれ。朝日新聞、文春オンライン、映画秘宝、WEBサイト「ハニカム」等で執筆中。著書の『映画系女子がゆく!』(青弓社)『映画なしでは生きられない』『バッドエンドの誘惑~なぜ人は厭な映画を観たいと思うのか~』(共に洋泉社)が絶賛発売中。
COLUMNS
- Columns
♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns
3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns
ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns
♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns
攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns
2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns
♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns
早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns
♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns
『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns
1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論
第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー - Columns
♯1:レイヴ・カルチャーの思い出 - Columns
12月のジャズ- Jazz in December 2023 - Columns
11月のジャズ- Jazz in November 2023 - 音楽学のホットな異論
第1回目:#Metoo以後のUSポップ・ミュージック - Columns
10月のジャズ- Jazz in October 2023 - Columns
ゲーム音楽研究の第一人者が語る〈Warp〉とワンオートリックス・ポイント・ネヴァー - Columns
〈AMBIENT KYOTO 2023〉現地レポート - Columns
ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー・ディスクガイド- Oneohtrix Point Never disc guide


 DOMMUNE
DOMMUNE